寸々語
寸々語(すんすんご)とは、秋聲の随筆のタイトルで、「ちょっとした話」を意味します。
秋聲記念館でのできごとをお伝えしていきます。
2021年、〝150年〟の終幕 |
| 2021.12.26 |
秋聲満150歳のお誕生日であった12月23日、生誕150年記念事業のメインかつフィナーレとなる朗読劇「赤い花」が無事終幕いたしました。蓋を開けてみればなんと540人のお客様がご来場くださったとのこと! おかげさまで初日たった12枚というチケット売上数に背筋の凍り付く思いをしたことも、今や笑い話となりました。当然これだけの豪華キャスト・スタッフが揃っているのですから、人が来ないはずがありません。 秋聲作品の深く世に根ざし生き続けるしぶとさを、客席に力強く語りかけてくださった林恒宏さん、可憐かつ情熱的な米子をその身で体現してくださった松岡理恵さん、病弱ながら瑞々しく柔らかな青年の呼吸と感性で米子も聴衆をも魅了してくださった渡辺拓海さん、友・母・語りという難しい三役を見事にこなしてくださったうえだ星子さん、舞台全体を一気にダンスホールという空間へと誘ってくださったダンサーの中嶋秀樹・美喜カップル、そのダンスから朗読の背景にさらりと溶け込み、プロのなせる絶妙の間合いで「赤い花」の世界観を盛り上げてくださったオーケストラ・アンサンブル金沢のみなさま、そしてこの方なくしては何もかもが成り立たなかった、出演兼総合演出として表も裏も舞台の一切を取り仕切ってくださった板倉光隆さんに、深く深く感謝を申し上げます。 秋聲作品の深く世に根ざし生き続けるしぶとさを、客席に力強く語りかけてくださった林恒宏さん、可憐かつ情熱的な米子をその身で体現してくださった松岡理恵さん、病弱ながら瑞々しく柔らかな青年の呼吸と感性で米子も聴衆をも魅了してくださった渡辺拓海さん、友・母・語りという難しい三役を見事にこなしてくださったうえだ星子さん、舞台全体を一気にダンスホールという空間へと誘ってくださったダンサーの中嶋秀樹・美喜カップル、そのダンスから朗読の背景にさらりと溶け込み、プロのなせる絶妙の間合いで「赤い花」の世界観を盛り上げてくださったオーケストラ・アンサンブル金沢のみなさま、そしてこの方なくしては何もかもが成り立たなかった、出演兼総合演出として表も裏も舞台の一切を取り仕切ってくださった板倉光隆さんに、深く深く感謝を申し上げます。またリハーサルから長時間お付き合いくださり演者さんの魅力を最大限に引き出しつつ、演者さんたちがほっとする場となってずっとお見守りくださったヘアメイクの角谷美由紀さん、それら舞台の土台を支え、小さな記念館のふわふわとした夢でしかなかったものを美しい形にしてくださった舞台監督・駒井誠さんをはじめとする金沢舞台のみなさまにも、心よりお礼を申し上げます。 そして何より、秋聲生誕150年の祝賀会のためご参集くださったお客さま、遠くから応援してくださったみなさま、本当にありがとうございました。 きのう館内に設置していたクリスマスの飾りを撤去しながら、例のサンタ盛りツリーを持ち上げると「きよしこの夜」が流れはじめてびっくりしました。そういえばあのツリーはオルゴール機能を備えているのでした。その瞬間、プログラムに敢えて載せなかったOEKさんによる「きよしこの夜」のサプライズ演奏が蘇り、「それから、メリークリスマス。良い夜を。」とサンタ面を携えた秋聲役・林さんが脳内で優雅に一礼をしました。そして、舞台が終わったことを実感いたしました。 この最後の一言は舞台用の演出ですが、林さんによって滔々と語られた壇上挨拶は「赤い花」連載ど同年、昭和6年開催の秋聲還暦祝賀会についての本人の感想を元にしています。その原文「この頃の心境」を「不定期連載」にアップいたしました。ちょこちょこ端折ったり舞台用に文脈をいじったりと脚色は施させていただきましたが、ご興味ございましたらぜひご一読ください。 さて、明日27日でもって記念館の今年の活動は終了いたします。来年は1月5日(水)より開館いたします。厳密にいうと150年の年は終わりますが、一応〝年度〟で動いておりますので、来年3月までが生誕150年イヤーです。あと3ヶ月、よろしくお願いいたします。なお年内の寸々語の更新は本日が最後。当館の活動を支えてくださったすべてのみなさまに、この場を借りて厚くお礼を申し上げます。 それでは来年またお会いいたしましょう。みなさま、どうか良いお年を! |
ラストサムライ2 |
| 2021.12.17 |
| ツイッターのほうで、金沢湯涌夢二館さんの館内にいらっしゃる「黒船屋」の女性が胸に抱いている黒猫ちゃんが冬毛になってました~~! と呟いたっきり、展示のご紹介もせず申し訳のないことです。ちなみににわかに冬毛になったわけでなく、正確には長毛種になったのだとか…また折々に変化を見せてゆく黒猫ちゃんなのかもしれません。今後ともご注目ください。 さて、猫の毛のことばかり考えている間に早くもその会期終了があさって19日に迫りました夢二館さんの展示です。同時開催の秋聲協力展示コーナーももちろん、ご紹介すべきメイン展示は「夢二の次男・竹久不二彦の画業(前期)」。題のとおり、同館にまとめて寄託された夢二さんご次男・不二彦さんの作品が一堂に公開される非常にレアな展示です。猫のプーとか気になるところは多々ありつつ、まず展示冒頭のあたりで秋聲的にンッ?となるのが、不二彦さんが養女に迎えたという竹久野生(のぶ)さんについての記述。竹久野生、その実のご両親が画家で詩人の辻まことと武林イヴォンヌ…武林イヴォンヌとは秋聲とも交流のあった武林無想庵の娘さん…と、ここで思い出されるのが秋聲のダンスについて記した寸々語2017年3月4日記事「ラストサムライ」、以下再掲です。  〈ご子息一穂さんの随筆「父の思い出」(「小説新潮」昭和32年2月号)のなかにそんな記述がございまして、(中略)「年齢でもあり、体にしない(撓い)がないので、踊りはまるで能のように固苦しかつた。(中略)その時分、巴里(パリ)から日本に来た武林無想庵氏のお嬢さんのイヴォンヌさんが、ダンス場で父に逢い、はじめて『サムライ』を見たと云つたくらいだから、父のダンスは社交ダンスなどと云うよりも、確かに能に近いようなものであつた。」〉――秋聲がサムライなことはいったん脇へ置き、ここで秋聲にサムライを見た武林イヴォンヌの娘さんこそ野生さん、そしてその養父が不二彦さん…! とんだ行きつ戻りつで着地点を見失いそうです。 〈ご子息一穂さんの随筆「父の思い出」(「小説新潮」昭和32年2月号)のなかにそんな記述がございまして、(中略)「年齢でもあり、体にしない(撓い)がないので、踊りはまるで能のように固苦しかつた。(中略)その時分、巴里(パリ)から日本に来た武林無想庵氏のお嬢さんのイヴォンヌさんが、ダンス場で父に逢い、はじめて『サムライ』を見たと云つたくらいだから、父のダンスは社交ダンスなどと云うよりも、確かに能に近いようなものであつた。」〉――秋聲がサムライなことはいったん脇へ置き、ここで秋聲にサムライを見た武林イヴォンヌの娘さんこそ野生さん、そしてその養父が不二彦さん…! とんだ行きつ戻りつで着地点を見失いそうです。へーーーとなって観覧の足を進め、さらに秋聲コーナーで紹介されるのが不二彦さんと秋聲に面識があったというお話。不二彦さんご自身が「父の思い出」(『夢二美術館1 宵待草のうた』所収)なる随筆に記していらっしゃることを、当館も以前に東京の竹久夢二美術館さんから教えていただきました。夢二さんと山田順子が交際をしていた頃、順子のお供で秋聲宅へ〝ノコノコ出かけていく〟ようなこともあったそう。不二彦さんの単独展に、秋聲がすこし顔を出させていただくゆかりという名の着地点を、ここに発見いたしました。 |
生誕150年記念協力展示㉒㉓ |
| 2021.12.16 |
秋聲満150歳のお誕生日まであと一週間となりました。そんな本日、協力展示最後の2施設のご紹介です。まずは22館目、同じ財団仲間である谷口吉郎・吉生記念金沢建築館さんによる徳田秋聲生誕150年記念コーナー展示「徳田秋聲文学碑」! ご存じ、卯 辰山の秋聲文学碑の設計者が他ならぬ谷口吉郎氏。本郷の秋聲宅へと足を運び、日が暮れるまで縁側から庭を眺めて構想を練ったというこの碑について、館内にコーナーをもうけてご紹介くださいます。谷口氏曰く碑の前にある丸い台座は「小さい花台の石」で「それに四季の花を籠か壺にさしてお供えしてもらう」ためのものだそう(「芸林閒歩」昭和22年11月号掲載、設計者の言葉より)。先日「北國新聞」さんにも朗読劇「赤い花」の作品紹介として書かせていただきましたとおり(14日掲載)、ことのほかお花を愛した秋聲です。 辰山の秋聲文学碑の設計者が他ならぬ谷口吉郎氏。本郷の秋聲宅へと足を運び、日が暮れるまで縁側から庭を眺めて構想を練ったというこの碑について、館内にコーナーをもうけてご紹介くださいます。谷口氏曰く碑の前にある丸い台座は「小さい花台の石」で「それに四季の花を籠か壺にさしてお供えしてもらう」ためのものだそう(「芸林閒歩」昭和22年11月号掲載、設計者の言葉より)。先日「北國新聞」さんにも朗読劇「赤い花」の作品紹介として書かせていただきましたとおり(14日掲載)、ことのほかお花を愛した秋聲です。また谷口吉郎氏といえば四高のご出身、四高といえば秋聲の母校でもあり、そして現在の金沢大学前身校のひとつ――と、そんな繋がりも発見される協力展示のしんがりをつとめてくださるのは金沢大学附属図書館さんでございます! こちらは中央図書館さんを会場に、秋聲お誕生日のその日から企画展示「金大生のための徳田秋聲入門」をご開催くださいます。金沢大学所蔵の秋聲関連図書が展示されるほか、ホームページに当館学芸員によるおすすめの秋聲関連図書10冊をご掲載くださるうえ、附属図書館報「こだま」で記念特集を組んでくださるとか…い、いたれりつくせり…! 先日、同学講義にゲストとしてお招きいただいた際、図書館さんにご挨拶にお寄りしました。作成中の館報もゲラをちらと見せていただき、マスクの下でニヤニヤしながら100名の学生さんに向けその日が花袋さんの150歳のお誕生日であったこと(13日)、もう10日寝ると秋聲のお誕生日であることをお話しさせていただきました。そう、23日がお誕生日。今年の春から全国で順次ご開催をいただいてきました協力展示も意図せぬところで全23施設。振り返れば9月23日に特設サイトを公開し、10月23日には北村薫先生のスペシャルトークイベント開催、11月23日は花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会を記念した来館者プレゼント+この日に合わせた「秋聲祝皿」の発送、そして12月23日メインイベント「赤い花」。「23」が当館にとってラッキーナンバーとなりました。 改めまして、こちらの無茶なお願いに快く応じてくださった23にも及ぶ全国各地の施設のみなさま、本当にありがとうございました。終幕までもう一息、よろしくお願いいたします。 |
朗読劇「赤い花」ができるまで⑤ |
| 2021.12.6 |
| 11月2日記事でも少し触れましたように、ダンスホールを舞台とする「赤い花」は、昭和6年、その前年に社交ダンスを習い始めた秋聲がそれまでの創作不振から抜けださんとしていた頃の作品です。初出紙「信濃毎日新聞」の連載予告には「巨匠徳田秋聲氏
更正第一回の力作」と銘打たれ、次のような紹介文が続きます。 「わが徳田秋聲氏が、明治以来今日に至るまで、日本の文壇に残して来た功績の偉大なことは、既に周知の事実であります。名作『黴』以来、明治、大正、昭和を通じて氏のたゆまざる努力と、豊かな天分の錬磨とは、実に世界の大作家にも比肩すべき特異の芸術作品を残して来たのであります。この大作家が、身辺のやむなき事情のため、久しく小説の筆を絶つてゐたことは、一方氏の人間的苦悩の如何に大きかつたかを物語るものであると共に、その久しき沈黙こそは、やがてより偉大なる物を生むための生きた試練だつたのです。いま、時来り、想成つて、果然われ等の前に展開されようとする小説『赤い花』は、正に氏の更正を告ぐる暁鐘であり、昭和文壇の一大収穫たらんとするものであります。過般、東京に於ける作者の還暦六十年祝賀会の席上で、『これから大いにやる』と語つた氏の言葉によつても、新作『赤い花』に対する抱負のほどが窺はれます。なほ、帝展派閨秀作家有岡好子氏の優美な挿絵は、更に一段の精彩を添へるでせう。切に御愛読を乞ふ。」 すなわち「赤い花」と今回の企画展「祝賀会のこと」とは、スランプに陥った秋聲を折々に支えてくれた各○○会の活動および予告文中にある「還暦六十年祝賀会」の記録とで繋がってくるのです。秋聲還暦祝賀会が開催されたのは昭和6年11月3日、「赤い花」の連載開始は同年11月26日。100名近くの出席者によって祝われ、パワーをもらった秋聲による新しい意欲作としての「赤い花」…さらにこの「還暦祝賀会」にはダンサー星玲子も出席してくれていたことが秋聲の随筆「祝賀会席上の感想」によって語られます。「現在では、かかる職業婦人が、どんな席へ出たつて、他の貴婦人達に対して少しも失礼でないと信じたから」――その語り口から、当時ダンサーが社会的にどう見られる存在であったかが窺えるようです。  と、そういった作品の背景も含めて、先日「赤い花」のお稽古風景をご取材くださった北陸朝日放送さんの放送日が決まりました! 12月10日(金)18時15分~「HABスーパーJチャンネル」中のどこかにて。先だってより、演出の板倉光隆さんをはじめキャストのみなさまが精力的に広報活動にご協力くださっております。その他メディア情報とあわせて、ぜひ確認ください。 と、そういった作品の背景も含めて、先日「赤い花」のお稽古風景をご取材くださった北陸朝日放送さんの放送日が決まりました! 12月10日(金)18時15分~「HABスーパーJチャンネル」中のどこかにて。先だってより、演出の板倉光隆さんをはじめキャストのみなさまが精力的に広報活動にご協力くださっております。その他メディア情報とあわせて、ぜひ確認ください。インタビューを受ける舞台の大黒柱・林さん→ (この撮影風景の写真撮影はヒロイン松岡さん) |
『爛(ただれ)』出版記念会 |
| 2021.12.4 |
昨日お誕生日であった永井荷風といえば『濹東綺譚』、『濹東綺譚』といえば木村荘八による挿画、木村荘八挿画といえば秋聲の『爛』、『爛』といえば『爛』出版記念会! というわけで、現在の企画展「祝賀会のこと」は大正2年『爛』(新潮社)刊行の翌日に開催された『爛』出版記念会のお話から始まります。会場は神楽坂の東陽軒、出席者は中村武羅夫、本間久雄、生方敏郎、瀧田樗陰、岩野泡鳴、小川未明、正宗白鳥、上司小剣、鈴木三重吉、森田草平…当日出席の水守亀之介曰く〈妙な顔ぶれ〉の彼らによるこの会の寄せ書きも今回初公開いたしております。おそらくお酒も入った現場のノリで、「ビール」(草平)とか「カフエエ」(小剣)とかちょっと不思議な文言の並ぶ一風変わった寄せ書きがこちら↓ またこのとき一堂がなにせ主役の秋聲を上座へ上座へと促した、ということを小剣が記録してくれており、そのエピソードに、現在、田山花袋記念文学館さんで紹介されている西園寺公望が召集した雨声会の席上で、花袋と秋聲が互いに上座を譲り合ったというエピソードが思い出されます。「読売新聞」に載ったコラムで、そのタイトルも「ビールの泡」。詳しくは同館にてご確認ください(当館所蔵の花袋秋聲ほか揮毫「雨声会」寄せ書き書幅を展示していただいています!)。さらに、この『爛』の会が「秋聲会」の第一回となればいいよね、とも語る小剣曰く、その席で秋聲が「花袋会やろうよ、花袋会なら意義があるよ」と発言したとのこと。後年、「花袋会」が結成されたとき、花袋とともに秋聲がばっちりど真ん中に写る集合写真と当日の寄せ書き写真を花袋記念文学館さんよりお借りしてパネル展示させていただいております。 またこのとき一堂がなにせ主役の秋聲を上座へ上座へと促した、ということを小剣が記録してくれており、そのエピソードに、現在、田山花袋記念文学館さんで紹介されている西園寺公望が召集した雨声会の席上で、花袋と秋聲が互いに上座を譲り合ったというエピソードが思い出されます。「読売新聞」に載ったコラムで、そのタイトルも「ビールの泡」。詳しくは同館にてご確認ください(当館所蔵の花袋秋聲ほか揮毫「雨声会」寄せ書き書幅を展示していただいています!)。さらに、この『爛』の会が「秋聲会」の第一回となればいいよね、とも語る小剣曰く、その席で秋聲が「花袋会やろうよ、花袋会なら意義があるよ」と発言したとのこと。後年、「花袋会」が結成されたとき、花袋とともに秋聲がばっちりど真ん中に写る集合写真と当日の寄せ書き写真を花袋記念文学館さんよりお借りしてパネル展示させていただいております。といったところで次のコーナーは秋聲を囲む○○会のお話。「二日会」から「秋聲会」「あらくれ会」とともに「秋聲後援会」にまつわる資料を展示しています。後者は昭和初期に創作不振の時期を送った秋聲を支援するため中村武羅夫、島崎藤村らが中心になって結成した会で、新潮社につとめ「秋聲会」発起人にもなった楢崎勤の著書『作家の舞台裏』によれば、(おそらくこの会の)概要は〈知名の、政界、学界、作家、画家たちに、短冊、色紙、軸物などに揮毫してもらい、それを屏風に仕立てて、売り立てる。その売上金を先生に贈るというのであった。西園寺公望、平福百穂、島崎藤村たちが積極的に支援したが、とくに、藤村は、『小諸なる古城のほとり』の長詩を、何枚も書いて厚い友情をしめした〉とのこと。その長詩…いつか徳田家で拝見したような…? そしてこのコーナーにしれっとお出ししているのが、秋聲の長篇「赤い花」の自筆原稿… (つづく) |
「祝賀会の後」前編 |
| 2021.12.3 |
 11月23日(火・祝)という日が終わりました。この日は100年前の花袋秋聲誕生五十年祝賀会の開催日ということにちなみ、花袋記念文学館さんと共同で来館者プレゼントを実施。両館の生誕150年ロゴカラーをあしらったややデザインの異なるふたりのツーショットイラスト缶バッジです。お配りは各館でそれぞれ1個ずつのものを、館保存用に両館ver二個セットを作ってみましたらばアラ不思議。まるでパ○の実のファミリーパック仕様みたいになりました。 11月23日(火・祝)という日が終わりました。この日は100年前の花袋秋聲誕生五十年祝賀会の開催日ということにちなみ、花袋記念文学館さんと共同で来館者プレゼントを実施。両館の生誕150年ロゴカラーをあしらったややデザインの異なるふたりのツーショットイラスト缶バッジです。お配りは各館でそれぞれ1個ずつのものを、館保存用に両館ver二個セットを作ってみましたらばアラ不思議。まるでパ○の実のファミリーパック仕様みたいになりました。また同日は当館主催連続講座第3回「同志・田山花袋と秋聲」を開催。尾形明子先生ご解説による〝闘将〟花袋の勇ましさと切なさ、その闘争の跡を後世に伝えんとした秋聲の花袋評について改めて思いを馳せました。この回だけは延期の許されない日程でしたので、大荒れのお天気にはなってしまいましたが無事に開催できましたこと、記念館一同心からほっとしております。お足元のわるいなかご参加くださったみなさまと尾形先生、いつも快く会場をお貸しくださる偉人館さんに厚くお礼を申し上げます。 と、あれよあれよと11月23日が過ぎてしまいましたので、なんとなく似た数字の構成員で出来ている12月3日の今日この日、「不定期連載」に、秋聲による祝賀会の感想「祝賀会の後」前編をアップしてみました。不定期を謳いながらせめてもの信条として〝少なくとも一年放置しない〟という甘すぎる不文律が実は心の中にあり、前回の更新日が2020年12月26日「菊池寛賞を受けて」…おっとあぶないギリギリセーフ…! そう、この日は菊池寛のお誕生日に合わせての更新だったのでした。あれから早いもので一年が経とうとしています。今回の企画展でも菊池寛賞についてご紹介させていただいておりますし、菊池寛記念館さんの協力展示で、より詳しくそのあたりをご紹介くださっています。 今回アップした「祝賀会の後」には、花袋さんとの誕生五十年記念祝賀会について語るなかで〈二十五年の文壇的生活〉という言葉が出てきます。同じニュアンスなのでしょう、菊池寛の著書『文藝春秋』(大正11年、金星堂)には、「秋聲、花袋二十五年祝賀会の次ぎは、おそらくは武郎、白鳥、荷風の二十五年祝賀会ならん。三氏は同庚なれば、文運の進歩に伴ひて、祝賀会の盛んなる、秋聲花袋祝賀会の比にあらざるべし。」とあり、たしかに秋聲が上京して紅葉門下に入ったのは数えで25歳のとき(花袋さんはもっと早いです)。この祝賀会には、ざっくりその節目の意味も込められていたようです。 |
生誕150年記念協力展示㉑ |
| 2021.11.23 |
 本日11月23日(火・祝)は100年前の花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会の開催日。そんな嬉しい日には嬉しいお知らせです。生誕150年記念協力展示に北は青森県近代文学館のご登場です! 今月26日(金)~1月11日(火)までの会期で、同館ご所蔵の秋聲の俳句色紙を2点公開してくださいます(←画像クリックでPDF開きます)。ほぼほぼ初公開に近いお品だとか。ひとつは「折々は妻のうとまし冬ごもり」、石川近代文学館さんの秋聲展でも展示されているもので、秋聲がわりと気に入っていた一句。もうひとつは当館にも所蔵のない珍しい一句「つくづくと桜さびしき真昼哉」です。とても良いバランスの二点ですのでぜひこの機会にご覧ください。そして秋聲と青森さんに何のゆかりがあろうかと言えば青森県弘前出身の葛西善蔵によって深く繋がってまいります。善蔵は秋聲の16歳年下で、秋聲に師事した作家。彼の「酔狸州七席七題」には「初めて先生のおうちへお伺ひしたのは、僕の十九の年だつた」と記されています(数えで20歳、ということは秋聲が36歳ですね)。それから14年、この作品にはかの祝賀会時におけるすったもんだにも言及があり、当館の企画展「祝賀会のこと」でも少しだけご紹介をば。当時この会の〝接待係〟に任命されていたという善蔵さん。秋聲先生のお祝いだから~という気持ちで当日出席してみれば、紋付羽織を着ていかなかったがために自分にだけ接待係の徽章がもらえない! そんな仕打ちあるか!! 講演に登壇した白鳥さんだって着てないのに!(しかし白足袋は履いている白鳥)と、この日がとても苦い思い出になってしまったことが語られているのです。他の人のお祝いの席にはむしろ秋聲から紋付を借りて出席したことだってあるし白足袋だって履いて行く。けれども秋聲先生のお祝いの席だからこそ着ては行けない、そんな自分じゃないんだ、かえっておかしいんだ……というたいそう複雑な善蔵の心持ち…。結局、接待係の方にも秋聲のいる主賓室にも行かれず大広間に座っていると、どうやら秋聲がやってきて花袋さんに善蔵を紹介してくれたようで、それを一代の喜びであった、とも語っています。 本日11月23日(火・祝)は100年前の花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会の開催日。そんな嬉しい日には嬉しいお知らせです。生誕150年記念協力展示に北は青森県近代文学館のご登場です! 今月26日(金)~1月11日(火)までの会期で、同館ご所蔵の秋聲の俳句色紙を2点公開してくださいます(←画像クリックでPDF開きます)。ほぼほぼ初公開に近いお品だとか。ひとつは「折々は妻のうとまし冬ごもり」、石川近代文学館さんの秋聲展でも展示されているもので、秋聲がわりと気に入っていた一句。もうひとつは当館にも所蔵のない珍しい一句「つくづくと桜さびしき真昼哉」です。とても良いバランスの二点ですのでぜひこの機会にご覧ください。そして秋聲と青森さんに何のゆかりがあろうかと言えば青森県弘前出身の葛西善蔵によって深く繋がってまいります。善蔵は秋聲の16歳年下で、秋聲に師事した作家。彼の「酔狸州七席七題」には「初めて先生のおうちへお伺ひしたのは、僕の十九の年だつた」と記されています(数えで20歳、ということは秋聲が36歳ですね)。それから14年、この作品にはかの祝賀会時におけるすったもんだにも言及があり、当館の企画展「祝賀会のこと」でも少しだけご紹介をば。当時この会の〝接待係〟に任命されていたという善蔵さん。秋聲先生のお祝いだから~という気持ちで当日出席してみれば、紋付羽織を着ていかなかったがために自分にだけ接待係の徽章がもらえない! そんな仕打ちあるか!! 講演に登壇した白鳥さんだって着てないのに!(しかし白足袋は履いている白鳥)と、この日がとても苦い思い出になってしまったことが語られているのです。他の人のお祝いの席にはむしろ秋聲から紋付を借りて出席したことだってあるし白足袋だって履いて行く。けれども秋聲先生のお祝いの席だからこそ着ては行けない、そんな自分じゃないんだ、かえっておかしいんだ……というたいそう複雑な善蔵の心持ち…。結局、接待係の方にも秋聲のいる主賓室にも行かれず大広間に座っていると、どうやら秋聲がやってきて花袋さんに善蔵を紹介してくれたようで、それを一代の喜びであった、とも語っています。そんなふたりのゆかりを、金沢から遠く青森県の葛西善蔵コーナーにて感じていただけましたら幸いです。当館の祝賀会展開催にあたりましても青森県近代文学館さんには上記について教えていただくなどたいへんお世話になりました。なお、このあと14時から連続講座「同志・田山花袋と秋聲」の開催を控える本日の金沢はなかなかの雨。善蔵も触れているとおり、100年前の今日もまた雨の日だったそうです。 |
生誕150年記念協力展示⑳ |
| 2021.11.18 |
本日こそ秋聲忌です。おかげさまで去る14日、今年も催事としての「秋聲忌」をつつがなく執りおこなうことができました。ご参加のみなさま、お経をあげてくださった静明寺さん、共催の石川近代文学館さん、そして記念講演にご登壇くださった松本徹先生、本当にありがとうございました。秋聲忌が終わると次はお誕生日だねぇという気持ちになります。実は生誕150年記念企画展「祝賀会のこと」チラシにおける誕生五十年記念祝賀会における秋聲とのツーショット写真を元にしたイラストにもこっそり刷り込みましたとおり(探してみてください!)、花袋さんは12月13日、秋聲はその10日後の23日がお誕生日。花袋記念文学館さんにおける連携展「情熱の人
田山花袋 ―《新しく》《真面目》な文学を求めて」第3部も、秋聲誕生日までを意識して会期を組んでくださっております。 そして12月生まれといえばもうひとり…12月26日生まれの菊池寛御大でございます! 12月生まれブラザーズとして生誕150年記念協力展示に香川県は高松市の菊池寛記念館さんがご参画です! ありがとうございます! すでに終わってしまいましたが花袋記念館さんの特別展第2部タイトル「文学維新運動の第一人者」というのも菊池寛のお言葉であったそうですね。秋聲とのゆかりは同館におけるコレクション展「生誕150年記念
徳田秋聲と菊池寛」にてご確認ください。11月23日(火・祝)、祝賀会のまさにその日から(気が利いていらっしゃる…!)来年2022年1月10日(月・祝)までの会期となっております。 そして12月生まれといえばもうひとり…12月26日生まれの菊池寛御大でございます! 12月生まれブラザーズとして生誕150年記念協力展示に香川県は高松市の菊池寛記念館さんがご参画です! ありがとうございます! すでに終わってしまいましたが花袋記念館さんの特別展第2部タイトル「文学維新運動の第一人者」というのも菊池寛のお言葉であったそうですね。秋聲とのゆかりは同館におけるコレクション展「生誕150年記念
徳田秋聲と菊池寛」にてご確認ください。11月23日(火・祝)、祝賀会のまさにその日から(気が利いていらっしゃる…!)来年2022年1月10日(月・祝)までの会期となっております。当館の今回展でも寛のお名前はしっかり出てまいります。秋聲の受賞歴のくだりで菊池寛賞にまつわる資料を少しと、先日もこちらでご紹介した野間文芸賞の賞金を藤村と秋聲にあげましょうよ~と提案してくれたというくだり(その提案について寛が記した「話の屑籠」掲載の「文芸春秋」誌を展示中です)。そしてまた誕生五十年を記念して出版された島崎藤村、長谷川天溪、有島武郎、片上伸編『田山花袋 徳田秋聲誕生五十年祝賀記念 現代小説選集』(大正9年11月23日刊行)編集時におけるすったもんだを題材にして寛が制作したのが小説「入れ札」であるというのもまた有名なお話で、同作を収録する作品集『道理』初版をあわせて展示しています。 なにせ寛は秋聲の生涯にとってなくてはならぬ人。昭和18年11月21日、青山斎場でおこなわれた秋聲葬儀委員長は、今回展でも頻出の中村武羅夫とともに菊池寛がつとめています。 |
虚子と秋聲―俳句展の終わりに |
| 2021.11.12 |
本日、展示替え最終日。新しい企画展「祝賀会のこと」のことは追ってご紹介することとして、撤去してしまった「俳句と遺墨」展会期中に書き切れなかった高浜虚子と秋聲についてギリギリ滑り込ませてまいります。 今回の俳句展では虚子の俳句短冊2点を初公開させていただきました。「或時は布団のおごり好もしき」「移されて淋しき藤の咲きにけり」。いずれも、明治末期しばし小説に傾倒していた虚子が久々に俳壇に復帰した大正初期の作品ということで、明治末期…小説…虚子…とここに秋聲を加えれば「新世帯」の完成ですね! 虚子が「国民新聞」文化部長に就任した際、その依頼により同紙に連載されたのが秋聲の自然主義の出発点とも言われる「新世帯」(明治41年)であったのです(初版本が花袋記念文学館さんに出張中!) 今回の俳句展では虚子の俳句短冊2点を初公開させていただきました。「或時は布団のおごり好もしき」「移されて淋しき藤の咲きにけり」。いずれも、明治末期しばし小説に傾倒していた虚子が久々に俳壇に復帰した大正初期の作品ということで、明治末期…小説…虚子…とここに秋聲を加えれば「新世帯」の完成ですね! 虚子が「国民新聞」文化部長に就任した際、その依頼により同紙に連載されたのが秋聲の自然主義の出発点とも言われる「新世帯」(明治41年)であったのです(初版本が花袋記念文学館さんに出張中!)ちょうどこの頃、雑誌「趣味」明治43年1月号で「文芸家相互評」という企画があり、たとえば白鳥と荷風、藤村と花袋、霜川と未明らが互いの印象を書き合うといったなか、秋聲とペアを組んだ(組まされた?)のは虚子でした。秋聲は虚子について振られ「そいつは大いに困ったな」とこぼしながら(談話なのですね)「兎に角氏の作を見ると、物を観(み)ものを描くに当つて、物其の儘の姿が顕れて居て、別の作者の主観を持つて特殊の色彩(いろどり)を着けたと云ふ処がない。所謂(いわゆる)色眼鏡をかけて物を観且つ描いたと云ふ風な処が殆んど全く無いと云つて可(い)い」、とはいえ描かれたものは「立体的」と、単に「写生派の作家以上」の「異彩」を放った存在であると高く評価しています。また虚子のタイプとして「何の作も筆を執るまで充分熟慮して、少なくとも作者自身満足する程度まで熟して来なければ、決して漫然筆を執るやうなことはしないと云ふ処が、明らかに見られる」とも。そして虚子の「俳諧師」から、今後小説方面での活躍への期待が語られてゆきます。 一方、虚子は秋聲について、「秋聲と云ふ人は自分の傑(えら)くないと云ふ事に気のついてゐる人らしい。夫故(それゆえ)に当込み気は更になく、しつとりと滋味ある作に接することが出来る。現作家の多くはそうでないやうな顔をしてゐて其実(そのじつ)衒気満腹なのが多い。秋聲氏は其中(そのうち)に立つて詐(いつわ)らず、飾らず、淋しい心持で自分の力一ぱい出来るだけの仕事をしてゐるやうに見える。」(全文)と、少しその人間性にも踏み込む内容(「滋味」がでました)。 実は今回、俳句展を開催するにあたり、虚子記念文学館さんにたいへん親切にしていただきました。おかげさまで無事に閉幕となりました。その節は本当にありがとうございました! |
「偉い友達 芥川龍之介」展 |
| 2021.11.5 |
昨日、野間文芸賞の発表がありました。第74回野間文芸賞はリービ英雄氏の「天路」に授与されたそう。今年で74回目ということはその第1回はざっくり1940年代にまで遡ります。昭和16年、先年に死去した講談社社長・野間清治の遺志を受け創設された賞で、第1回受賞者は野間もその作品を愛読し常々支援していたという劇作家の真山青果。選考委員は島崎藤村、菊池寛、武者小路実篤、そして秋聲! 気づけばわりとどこにでも(かつ、主要なところに)いる秋聲! 翌年の第2回は該当者なく、菊池寛のはからいにより文学賞の中でも超高額で知られた賞金一万円を長きにわたる文壇の功労者である藤村と秋聲にあげましょう~となったというエピソードについても次回企画展「祝賀会のこと」でご紹介する予定です(※詳しくは昨年9月9日記事「宿老たちの友情」参照)。その関連資料として、野間奉公会から秋聲に上記を連絡する長いお手紙(たぶんケースに入りきらないので全文はパネルにて)と賞金が入っていたと思われるのし袋、そして表彰状を初公開。思えば現在も続く菊池寛賞の始まりにも、野間文芸賞の始まりにも秋聲は深くかかわっているのでした。 また野間清治といえば、前回展「秋聲の家」の際にその著書『私の半生』を展示しておりました。何故なら書斎にいる秋聲の写真の手元に同書が写っているため。秋聲旧蔵書そのものではありませんが、当館蔵の同じ本で、その下に積まれているのは『芥川龍之介読本』(昭和11年、三笠書房)にみえますね。これも展示したほか(現在は再現書斎机のうえに同じように積んでいます)、室生犀星記念館さんの企画展「偉い友達 芥川龍之介」に出品されているのを先日確認いたしました。というのもこの編纂にあたったのが他でもない犀星さんで、今は亡き親友の本を編むにあたり、口絵・巻頭語・巻末「芥川龍之介氏を憶ふ」にいたる随所から犀星さんの息づかいが聞こえるようなつくりになっています。 また野間清治といえば、前回展「秋聲の家」の際にその著書『私の半生』を展示しておりました。何故なら書斎にいる秋聲の写真の手元に同書が写っているため。秋聲旧蔵書そのものではありませんが、当館蔵の同じ本で、その下に積まれているのは『芥川龍之介読本』(昭和11年、三笠書房)にみえますね。これも展示したほか(現在は再現書斎机のうえに同じように積んでいます)、室生犀星記念館さんの企画展「偉い友達 芥川龍之介」に出品されているのを先日確認いたしました。というのもこの編纂にあたったのが他でもない犀星さんで、今は亡き親友の本を編むにあたり、口絵・巻頭語・巻末「芥川龍之介氏を憶ふ」にいたる随所から犀星さんの息づかいが聞こえるようなつくりになっています。たいへん失礼なことながらとにもかくにも1階の特集コーナー「徳田秋聲生誕150年記念展示」を見に行かなくっちゃ! と遅ればせながら駆け込んだわけですが(ありがとうございました! 展示中の秋聲文学碑文の下書き原稿で欄外に何度も練習されているのは「新世帯」の「帯」の字ですね…!)それももちろんのこと2階の芥川展の資料の豪華さと犀星さんとの友情のさまにあてられ、犀星さんとぶつかったり楽しげにやりとりをしているさまを知れば知るほど最終的にぐっとなって、フゥーーーーーと同館を出た瞬間、深く息をつくことととなりました。こちらの展示、なんと当館と同じあさって7日(日)までです。 |
生誕150年記念協力展示⑲(というより連携展) |
| 2021.11.4 |
満を持してご紹介申し上げます。生誕150年のもうひとりの主役・秋聲と同い年の田山花袋を顕彰される田山花袋記念文学館さんにおける特別展です! といいながらこちらの生誕150年記念特別展「情熱の人 田山花袋 ―《新しく》《真面目》な文学を求めて」は7月からすでに始まっていらっしゃるのでした。早くご紹介しなければしなければ、と思いながらタイミングを逃しに逃して時すでに11月…花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会の月まで食い込んできてしまいました。まことに申し訳ございません…! 展示は3部構成になっており、すでに終わってしまった第1部「録弥から〝花袋〟へ―小説家への道のり」、現在開催中の第2部「花袋、『文学維新運動の第一人者』となる」が7日の日曜日まで、そして来たる第3部「峠を越えて―大正期の文壇と花袋―」のキーパーソンこそわれらが徳田秋聲でございます。 この第3部でもって、ご存じ大正9年、共同で開催された花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会についても紹介されるわけですが、今回この祝賀会における記念品のひとつ、国民新聞社から贈られた平福百穂画による末広一対があっちでもこっちでも公開されます! あっち=花袋館さん、こっち=秋聲館。当館でも7日に現在の俳句展を終了し、花袋館さんの第3部と同じ13日(土)より新企画展「祝賀会のこと」を開催するなかで、花袋と秋聲お揃いで持っている末広一対を両館同時公開しようという試みです。実はデザインが異なりまして、当館におきましては本邦初公開。これだけでなく、大阪朝日新聞社からもらった書斎の違い棚も花袋さんとお揃いですし、便宜的に協力展の枠に入れさせていただきましたが、両館におけるとてもゆるいしばりの連携展となっております。そのほか花袋館さんでは秋聲に宛てられた徳田家蔵の花袋筆書簡が一挙公開されようかと存じますので(向こうさまに集合しているので逆に当館にはナイのです)花袋館では秋聲エキスが、秋聲館では花袋さんエキスが存分に摂取していただけ…存分…いえ当館は狭いので、向こうさまに比べるとだいぶん薄味かも…しょ、書斎の書幅を花袋さんの自筆にかけかえました! この第3部でもって、ご存じ大正9年、共同で開催された花袋秋聲誕生五十年記念祝賀会についても紹介されるわけですが、今回この祝賀会における記念品のひとつ、国民新聞社から贈られた平福百穂画による末広一対があっちでもこっちでも公開されます! あっち=花袋館さん、こっち=秋聲館。当館でも7日に現在の俳句展を終了し、花袋館さんの第3部と同じ13日(土)より新企画展「祝賀会のこと」を開催するなかで、花袋と秋聲お揃いで持っている末広一対を両館同時公開しようという試みです。実はデザインが異なりまして、当館におきましては本邦初公開。これだけでなく、大阪朝日新聞社からもらった書斎の違い棚も花袋さんとお揃いですし、便宜的に協力展の枠に入れさせていただきましたが、両館におけるとてもゆるいしばりの連携展となっております。そのほか花袋館さんでは秋聲に宛てられた徳田家蔵の花袋筆書簡が一挙公開されようかと存じますので(向こうさまに集合しているので逆に当館にはナイのです)花袋館では秋聲エキスが、秋聲館では花袋さんエキスが存分に摂取していただけ…存分…いえ当館は狭いので、向こうさまに比べるとだいぶん薄味かも…しょ、書斎の書幅を花袋さんの自筆にかけかえました!また11月23日(火・祝)には当館でもって花袋講座があり(会場は金沢ふるさと偉人館さん)、同時に両館でもって来館者プレゼントがあり、そして12月4日(土)には花袋館さんでもって当館初代学芸員・現東海大学教授の大木志門先生による秋聲講座の開催がございます。えぇ、花袋と秋聲、とても入り乱れて現場も混乱しております。 |
朗読劇「赤い花」紙チケット販売開始のお知らせ |
| 2021.11.2 |
先月発売いたしました12月の朗読劇「赤い花」チケットにつきまして、このコロナ禍において最悪興行中止になった場合の払い戻し処理等々を考え「チケットぴあ」のみの販売とさせていただいていたのですが、なかなかオンラインでのご購入に不慣れとお見受けするみなさまよりたびたびお問合せを賜り、このたび遅ればせながら記念館受付でも紙チケットの販売に踏み切ることにいたしました。すでにオンラインでご購入くださったみなさま、またコンビニエンスストアへお出かけくださったみなさま、手数料・ご足労の件、心よりお詫びを申し上げます。シミュレーションが行き届かず、本当に本当に申し訳ございません。記念館で売ってくれたら行けるのに…というお声をどうしても無視することができず、とにかくたくさんの皆様にご覧いただきたい、とその一心でもって確実に払い戻しの出来る方法など内部で検討を重ねまして、明日3日(水・祝)よりお取り扱いを開始いたします。なお、またも消極的なことで恐縮ながら、こちらの紙チケットは記念館までお越しいただける方のみの販売とさせていただき、ご郵送および当日までのお取り置き等には対応いたしかねますので何卒ご容赦ください。販売数次第で、会場における当日券は出せそうな気がしております。また様子を見ながら、適宜ご案内を申し上げます。 月末の夜間開館日の館内では、午前中はZOOMを使ったご出演者さまの読み合わせ、午後はプログラム原稿の作成、夜にはひたすらハンコを押すマンと化しておりました(複製防止の)。いかんせん初めての規模のイベントで、何もかも手探りにつき段取りがわるく、各所に多大なるご迷惑をおかけしております。申し訳なく存じております。 月末の夜間開館日の館内では、午前中はZOOMを使ったご出演者さまの読み合わせ、午後はプログラム原稿の作成、夜にはひたすらハンコを押すマンと化しておりました(複製防止の)。いかんせん初めての規模のイベントで、何もかも手探りにつき段取りがわるく、各所に多大なるご迷惑をおかけしております。申し訳なく存じております。しかしながら回を重ねるにつれ、だんだんと当日の舞台の様子が想像できるようになり、12月23日、秋聲150歳のお誕生日をたくさんの方とお祝いできることが今から楽しみで仕方がありません。繰り返しお声がけをしながら、おひとりでも多くの方にご来場いただけるよう、今後とも記念館職員一同がんばってまいります。 ちなみに次回企画展「祝賀会のこと」では、原作である長篇小説「赤い花」の秋聲自筆原稿も展示予定です。長いお話のうち原稿はほんの一部だけしか残っていないのですが、この作品は旧友・桐生悠々の斡旋により彼のいた「信濃毎日新聞」に連載されたきり単行本になっておりませんので、今読めるとすれば信毎初出紙か、8枚だけ残された自筆原稿か、八木書店版『徳田秋聲全集』第39巻でだけ…なんともレアな作品なのです。 |
生誕150年記念協力展示⑱ |
| 2021.10.30 |
| 今日明日は金沢マラソン開催にあわせ夜8時まで開館延長をいたします。マラソン当日である明日31日(日)は市内に交通規制が敷かれますので、お出かけの際はご注意ください。早いもので気がつけばもう月末。臨時休館により会期の短くなってしまった「俳句と遺墨」展も残すところ一週間となりました。と、名残を惜しんでいる間に、また新たに生誕150年協力展示に与してくださる施設さまが増えました! 当館が展示替え休館に入っても! 他館さまがカバーしてくださる…! というわけで、今回ご紹介するのは金沢海みらい図書館さんです! 玉川さん、泉野さんと並び、これで金沢市立の図書館全館がご協力くださった形となりました。〝金沢〟の三文豪の名に偽りなし、お忙しいなかありがとうございます!(なお、石川県立図書館さんは施設移転のため今月末でご休館です。当館ももちろんのこと、いつも調べ物で同館のお世話になっている各所から悲鳴があがっています) 立派な生誕150年記念パネルのほか、おすすめの秋聲作品にポップなど付していただいておりますので、海みらい図書館さんへ行かれた際にはぜひ覗いてみてください。  また、折よく〝金沢の三文豪〟をテーマにした朗読会のご案内も届きました。シニア演劇集団Agクルーさんによる「読みあわせの会」。11月6日(土)・7日(日)に市民芸術村にて、某K花さんの「紅玉」、犀星さんの「大槻伝蔵」、そして秋聲の「余震の一夜」が披露されます。本作はその名のとおり、大正12年、関東大震災後の混乱を描く短篇小説。震災当日、たまたま金沢に単身帰省していた秋聲がその当時の体験を綴った「不安のなかに」に続き、ようやく東京の自宅に帰り着いた後のお話です。各地で地震の報の相次ぐ今、また違った響き方をするのではないでしょうか。発表は「改造」大正13年1月号で、同誌目次に「古い家と人」という名で掲載されているところから、前回展「秋聲の家」でその初出誌を展示しておりました。〈地震をおそれる私は、二階屋が嫌ひであつた〉そうですし、さらにその家を日陰にしてしまった隣の三階建ての下宿(おそらく公盛館)は〈(※管理人や住人でなく)建物其物が咀(のろ)はし〉かったそうです(本文より)。本公演のチケットはAgクルーさんのFacebookからお求めください。この公演とともに「秋は金沢三文豪」スタンプラリーも終了、犀星館さんの「偉い友達 芥川龍之介」展も終了です! また、折よく〝金沢の三文豪〟をテーマにした朗読会のご案内も届きました。シニア演劇集団Agクルーさんによる「読みあわせの会」。11月6日(土)・7日(日)に市民芸術村にて、某K花さんの「紅玉」、犀星さんの「大槻伝蔵」、そして秋聲の「余震の一夜」が披露されます。本作はその名のとおり、大正12年、関東大震災後の混乱を描く短篇小説。震災当日、たまたま金沢に単身帰省していた秋聲がその当時の体験を綴った「不安のなかに」に続き、ようやく東京の自宅に帰り着いた後のお話です。各地で地震の報の相次ぐ今、また違った響き方をするのではないでしょうか。発表は「改造」大正13年1月号で、同誌目次に「古い家と人」という名で掲載されているところから、前回展「秋聲の家」でその初出誌を展示しておりました。〈地震をおそれる私は、二階屋が嫌ひであつた〉そうですし、さらにその家を日陰にしてしまった隣の三階建ての下宿(おそらく公盛館)は〈(※管理人や住人でなく)建物其物が咀(のろ)はし〉かったそうです(本文より)。本公演のチケットはAgクルーさんのFacebookからお求めください。この公演とともに「秋は金沢三文豪」スタンプラリーも終了、犀星館さんの「偉い友達 芥川龍之介」展も終了です! |
| まるで嵐 |
| 2021.10.25 |
22日、MROラジオさんの生中継で宣伝させていただきましたアレもコレも、この週末にバァッとやってきて、バァッと去ってゆきました。まるで嵐のようでした。そうそうラジオクルーさん、普段使いなら白、仕事使いなら黒、か…とさんざん悩んで生誕150年記念トートバッグをお買い上げくださいましてありがとうございました。そして23日、24日にご来館くださったたくさんのお客さまにも心よりお礼を申し上げます。 23日には、生誕150年スペシャルを冠し作家・北村薫先生のトークイベントを金沢21世紀美術館シアター21で開催いたしました。北村先生と当館とのご縁はこれまでにも折々にご紹介してまいりましたが、今回はそれらの背景について改めてご本人の口からお聞かせいただけるのみならず、5割? 6割? 専ら秋聲の話題で進行するという主催者としても驚きの秋聲率! その場に求められている話をこそ、何かを聴きたくて僕を呼んだんでしょう? というのが北村先生のお心で、生誕150年スペシャルにふさわしい、楽しくも今後の秋聲文学の未来にかかわる貴重なお話をたくさん頂戴いたしました。この成果はきっと、何かの形で…。 23日には、生誕150年スペシャルを冠し作家・北村薫先生のトークイベントを金沢21世紀美術館シアター21で開催いたしました。北村先生と当館とのご縁はこれまでにも折々にご紹介してまいりましたが、今回はそれらの背景について改めてご本人の口からお聞かせいただけるのみならず、5割? 6割? 専ら秋聲の話題で進行するという主催者としても驚きの秋聲率! その場に求められている話をこそ、何かを聴きたくて僕を呼んだんでしょう? というのが北村先生のお心で、生誕150年スペシャルにふさわしい、楽しくも今後の秋聲文学の未来にかかわる貴重なお話をたくさん頂戴いたしました。この成果はきっと、何かの形で…。そして翌日は「文豪とアルケミスト×OEK 金澤演奏會」。当館も物販にお邪魔いたしまして、秋声役の声優・渡辺拓海さんが舞台でご朗読くださった講談社文芸文庫『あらくれ』をしこたま積んでお待ちしておりましたら、結果なんと39冊も売れました! 秋聲作品が! 1日に39冊も売れた日! ご購入ありがとうございました。それもこれもこのコンサートと渡辺さんのおかげさま…(渡辺さんのあのお声で聴くとよりドキドキする一場面でしたね…! アーカイブが27日まで見られるそうです) 間もなく岩波文庫さんからも『あらくれ』が新刊で出ますので、ぜひこの150年の記念としてお買い求めください。そして、秋聲館さん150年でお忙しいでしょうから、と物販の手続きのすべてを引き受けてくださった犀星記念館さんにもこの場を借りて厚くお礼を申し上げます。もともとの楽曲のよさとOEKさんのことですから当日のご演奏が圧巻であったことは言うまでもなく、本番前に館にわざわざご挨拶に来てくださった作曲家・坂本英城さんをはじめとするノイジークロークのみなさまのお心配りにも感激いたしましたし、犀星役の逢坂良太さんのご朗読、さらに司会っぷりがすばらしかったです。なんでしょう、あのあたたかみと安心感…(そして渡辺さんに秋声くんの役作りについて振ってくださってありがとうございます!)。 さて、残すところは秋聲忌、花袋さんの連続講座、展示替えに朗読劇「赤い花」…嵐のあとに赤い花が咲きますように…! |
| 朗読劇「赤い花」ができるまで④ |
| 2021.10.22 |
 朗読、ダンスのみならず、朗読劇「赤い花」では金沢の誇るオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)から9名のみなさまにご出演をいただきます。なんと豪華! 数年前からナイトミュージアムの一環で館でデュオ演奏をご披露いただくという好機にめぐまれ、その企画担当者さまにお願いをして顔を繋いでいただいての「赤い花」。まさか、当館の企画でかのOEKさまに生演奏していただけるだなどとは夢にも思っておりませんでした。が、思い切って距離を縮めてみればみなさまいい方…! 決してとって食われたりはいたしませんで(※イメージです。すみません。雲の上の方々でしたので…!)、ご担当者さまには超ご多忙のなか何度もお打ち合わせの席をつくっていただき、こちらのああしたい、こうしたい、をじっくりと聞いていただいたうえ、良い舞台にしましょうね! と快くそのお力をお貸しくださることになったのです。そして現在、演奏予定曲の編曲をお願いしているところ…まだまだこれからが本番ではありますが、その節は本当にありがとうございました。またそこから繋がった5月の「風と緑の楽都音楽祭2021」でも秋聲コンサートをどうもありがとうございました。あさっての文アルさんコンサートにかかわるアレコレでも親切にしていただきありがとうございます。 朗読、ダンスのみならず、朗読劇「赤い花」では金沢の誇るオーケストラ・アンサンブル金沢(OEK)から9名のみなさまにご出演をいただきます。なんと豪華! 数年前からナイトミュージアムの一環で館でデュオ演奏をご披露いただくという好機にめぐまれ、その企画担当者さまにお願いをして顔を繋いでいただいての「赤い花」。まさか、当館の企画でかのOEKさまに生演奏していただけるだなどとは夢にも思っておりませんでした。が、思い切って距離を縮めてみればみなさまいい方…! 決してとって食われたりはいたしませんで(※イメージです。すみません。雲の上の方々でしたので…!)、ご担当者さまには超ご多忙のなか何度もお打ち合わせの席をつくっていただき、こちらのああしたい、こうしたい、をじっくりと聞いていただいたうえ、良い舞台にしましょうね! と快くそのお力をお貸しくださることになったのです。そして現在、演奏予定曲の編曲をお願いしているところ…まだまだこれからが本番ではありますが、その節は本当にありがとうございました。またそこから繋がった5月の「風と緑の楽都音楽祭2021」でも秋聲コンサートをどうもありがとうございました。あさっての文アルさんコンサートにかかわるアレコレでも親切にしていただきありがとうございます。さらにご縁はどんどん繋がり、今回設営・操作・監督と舞台にかかわるすべてをご担当くださる金沢舞台さん、ヘアメイクに携わってくださる角谷美由紀さん、と気がつけば、「赤い花」はビッグプロジェクトになっておりました。当然このような大きな舞台を職員6名のちいさな記念館の力だけで運営しきれるはずもなく、その主催は「秋聲生誕150年記念事業実行委員会」ってなにそれ実在する団体…? いまだ、4年前の夢の中にいるようです。 あの日、ご来館くださったお客さまと「ぜひ秋聲フェスティバルをいつか開催いたしましょう!」「となれば黴フェスですね!!」と盛り上がったものですが、蓋を開ければ「黴フェス」ならぬ「赤い花」フェスになりました(豆皿も中村記念美術館さんご提供のコラボ菓子も現状、草花しばり…)。『黴』ももちろん名作には違いありませんが、それだけでない、秋聲のモダンで華やかな一面をお届けしたいと思います。ご来場のみなさまは、ぜひ当日、胸に赤い花を挿してお出かけください。 |
| 朗読劇「赤い花」ができるまで③ |
| 2021.10.21 |
昨日、例月のMROラジオ「あさダッシュ!」さんでも熱弁をふるってまいりましたとおり(宣伝させていただきありがとうございます!)、来る12月23日、秋聲生誕日に開催予定の朗読劇「赤い花」の会場は金沢市文化ホールです。あのステンドグラスで有名な尾山神社の近くと言えばわかりよいでしょうか。会場の収容人数は約800名…! え~記念館主催イベントでは20人集めるのにもヒィヒィ言ってる~!(「秋聲忌」定員20名受付中…あと数席ございます) ちょっと大きく出すぎた感もありながら、生誕150年ですから! と、気を確かにも持つよう日々言い聞かせている記念館です。 今年はまだコロナの影響も色濃いですので、いったん会場キャパの半数400名という想定にしておりますが、それでもかなり規格外…ぜひお誘いあわせの上ご参加をいただけましたら幸いです。なお予算の都合上、オンライン配信の予定はございません。ご遠方のみなさまには心よりお詫びを申し上げます。 今年はまだコロナの影響も色濃いですので、いったん会場キャパの半数400名という想定にしておりますが、それでもかなり規格外…ぜひお誘いあわせの上ご参加をいただけましたら幸いです。なお予算の都合上、オンライン配信の予定はございません。ご遠方のみなさまには心よりお詫びを申し上げます。また、出演は9月25日付の①の記事でご紹介いたしました朗読者のほか、なんとダンサーさんもいらっしゃいます。原作となる長篇小説「赤い花」がダンスホールのナンバーワン・ダンサーであるヒロイン米子の半生を描く作品であるため、その舞台の雰囲気をさらに盛り上げるため実際にダンサーさんにもご出ましいただこう! といった趣向により。もともとは、平成29年に開催した「踊る文豪~秋聲とダンス!」展の際、秋聲のダンスの師匠である玉置眞吉監修によるダンスのステップ図を展示したことからこの構想は始まりました。これをご覧になったお客さまからせっかくだからダンスのステップが見られるイベントを企画しては?? とご提案いただき、お知り合いのダンスの先生までご紹介いただき、市内のダンススクールロイヤルさんをひょっこりお尋ねしたのです。すぐすぐには無理ですが、きっと生誕150年のおりに…! とのお約束だけを残してあれから4年…ようやく念願かなってダンスを取り入れた今回の企画に漕ぎ着けたというわけです。そしてダンススクールロイヤルさんにご紹介いただいたのが全国にその実力を知られ、国内外で受賞歴多数の中嶋秀樹・中嶋美喜ペア。今回の舞台では米子が所属するダンスホールの場面でワルツのステップをご披露いただく予定です。 |
舞台「文豪とアルケミスト 捻クレ者ノ独唱(アリア)」 |
| 2021.10.15 |
 昨日今日と怒濤の二日間でございました。昨日は東京の徳田家に次回企画展資料の借用に出かけており、まさかの道路事情で目的の新幹線に乗り遅れてギャーーーとなりながら名誉館長をはじめ関係各所のみなさまの優しさに生かされ(写真は徳田家書斎に着いた秋聲豆皿→)、東京滞在賞味3時間、帰り際にいま日本中で噂の小早川秋聲氏(@東京ステーションギャラリー)の前をペコリと一礼しつつ通り過ぎ(すみません、資料運搬中だったものですから)新幹線に乗ってようやくホッと一息ついてTwitterをぽちぽち遡って見ておりましたら、ご存じ秋聲がキャラクターとなって登場する「文豪とアルケミスト」さん舞台版第4弾にいよいよ秋声くんのご登場…えっ、となって、えっ? となってからのいったんスッとスマホを置き、翌日のりんご配りのことを考えました。アァ…シールに生誕150年って入れられたらよかったな…つくる余裕がなかったな…そうそう、舞台「赤い花」チケットの発売日でした明日…祝皿も発売か…10時と17時、間違えないようにしなくっちゃ…あれっ映画「縮図」も最終回…? フフ、明日は盛りだくさんだね…ウン盛りだくさんだ…と言っているのに、もう器からこぼれそうなのにまだニコニコ盛ろうとしてくるまんぷく食堂の気のいいご亭主みたいな方が急に横から現れ食欲の秋だよねーとかなんとか言いながらどんどん超高級な秋の味覚をよそってくるので(蓋! 蓋をください!)と8号車の真ん中で叫びました。キャパオーバーです。降る紅葉の真ん中にしゃがんでいらっしゃるあの青い御方はどなたですか?? どうも初めましてですね、初めまして!!! 昨日今日と怒濤の二日間でございました。昨日は東京の徳田家に次回企画展資料の借用に出かけており、まさかの道路事情で目的の新幹線に乗り遅れてギャーーーとなりながら名誉館長をはじめ関係各所のみなさまの優しさに生かされ(写真は徳田家書斎に着いた秋聲豆皿→)、東京滞在賞味3時間、帰り際にいま日本中で噂の小早川秋聲氏(@東京ステーションギャラリー)の前をペコリと一礼しつつ通り過ぎ(すみません、資料運搬中だったものですから)新幹線に乗ってようやくホッと一息ついてTwitterをぽちぽち遡って見ておりましたら、ご存じ秋聲がキャラクターとなって登場する「文豪とアルケミスト」さん舞台版第4弾にいよいよ秋声くんのご登場…えっ、となって、えっ? となってからのいったんスッとスマホを置き、翌日のりんご配りのことを考えました。アァ…シールに生誕150年って入れられたらよかったな…つくる余裕がなかったな…そうそう、舞台「赤い花」チケットの発売日でした明日…祝皿も発売か…10時と17時、間違えないようにしなくっちゃ…あれっ映画「縮図」も最終回…? フフ、明日は盛りだくさんだね…ウン盛りだくさんだ…と言っているのに、もう器からこぼれそうなのにまだニコニコ盛ろうとしてくるまんぷく食堂の気のいいご亭主みたいな方が急に横から現れ食欲の秋だよねーとかなんとか言いながらどんどん超高級な秋の味覚をよそってくるので(蓋! 蓋をください!)と8号車の真ん中で叫びました。キャパオーバーです。降る紅葉の真ん中にしゃがんでいらっしゃるあの青い御方はどなたですか?? どうも初めましてですね、初めまして!!!そういったわけで、とうとう秋声くんが舞台にお出になるそうですね。おめでとうございます。昨日はたくさんの方が当館におめでとうとあたたかいお言葉をかけてくださいましたが、その実「秋声くん」にとって何者でもない当館ですのでそのおめでとうはそっくりそのまま秋声くんと全国の秋声くんファンのみなさまにお返ししたいと思います。舞台へのご出演、おめでとうございます。 そしてこののちは大事な舞台のお邪魔にならぬよう、そっと静かに見守らせていただければと思います。大きな会場におけるいろいろな催しを見るにつけ、アァ秋聲にも満員の客席から降りしきる拍手の音を聞かせてあげたい、と、手前勝手なそんな思いでこれまでさまざまに企画してまいりました。力不足でそううまくはいかないことばかりでしたが、その思いの延長にあるのが今年の朗読劇「赤い花」です。同じステージ、そして同じ人物ではないにせよ、秋聲と同じ名をもつ秋声くんが彼自身の輝ける場所で愛と喜びをもって迎えられ、そして大きな拍手と声援を浴びるのだとすれば、それはきっとその先にいるやはりどこか捻くれ者の秋聲の耳にも届くのだろうと思っています。 |
「秋便り」 |
| 2021.10.9 |
 ハイ、今週のお菓子はりんごです! 先週同様、この土日も中村記念美術館さんにて「生菓子の日」が開催され、生誕150年を記念いたしまして先週と異なる秋聲モチーフのお菓子が登場! 前回の柿に引き続き、まるで徳田果樹園のようになってまいりましたが、秋聲は秋の果物が好き! ましてりんごといえば秋聲に因んで名付けられた石川県産ブランドりんごの「秋星」が燦然と輝くこの季節ですから柿を見ても秋聲、りんごを見ても秋聲、秋の果物は秋聲総どりで間違いありません。なお、りんごについては好きと言ったりきらいと言ったりいつもながらの一筋縄ではいかぬモニョモニョの秋聲ながら、金沢のお菓子に関してはことあるごとに賞讃しており、「菓子は好きだ。私の郷里金沢にはなかなかいい菓子がある。(中略)夏は夏の菓子、春は春の菓子、といふ風に、季節々々に菓子が変つて、冬には秋の菓子はないといふやうな、菓子には非常に贅つたところだ。」そしてまた、「菓子をたべたあとなどに、煎茶とか抹茶とかを飲むのはいいものだ。」とのこと(「現代十作家の生活振り」大正14年)。11月に入ればまた違ったお菓子をお抹茶とともに提供…という今回の企画にぴったりのお一言をいただきました。実は本日こそ「秋星」初出荷の日。そんなギリギリの時期に吉はしさんがとてもがんばってご手配くださいました。季節のものを、何より秋聲にちなんだものでなくては、という職人魂をひしひしと感じた今回のお菓子「秋便り」には中に秋星のシャリシャリ果肉も入ってございました。果実の方はこれから本格的に市中に出回りますのでお近くのお店でお買い求めいただけるかと存じます。「秋便り」は明日10日もご提供いただきます。 ハイ、今週のお菓子はりんごです! 先週同様、この土日も中村記念美術館さんにて「生菓子の日」が開催され、生誕150年を記念いたしまして先週と異なる秋聲モチーフのお菓子が登場! 前回の柿に引き続き、まるで徳田果樹園のようになってまいりましたが、秋聲は秋の果物が好き! ましてりんごといえば秋聲に因んで名付けられた石川県産ブランドりんごの「秋星」が燦然と輝くこの季節ですから柿を見ても秋聲、りんごを見ても秋聲、秋の果物は秋聲総どりで間違いありません。なお、りんごについては好きと言ったりきらいと言ったりいつもながらの一筋縄ではいかぬモニョモニョの秋聲ながら、金沢のお菓子に関してはことあるごとに賞讃しており、「菓子は好きだ。私の郷里金沢にはなかなかいい菓子がある。(中略)夏は夏の菓子、春は春の菓子、といふ風に、季節々々に菓子が変つて、冬には秋の菓子はないといふやうな、菓子には非常に贅つたところだ。」そしてまた、「菓子をたべたあとなどに、煎茶とか抹茶とかを飲むのはいいものだ。」とのこと(「現代十作家の生活振り」大正14年)。11月に入ればまた違ったお菓子をお抹茶とともに提供…という今回の企画にぴったりのお一言をいただきました。実は本日こそ「秋星」初出荷の日。そんなギリギリの時期に吉はしさんがとてもがんばってご手配くださいました。季節のものを、何より秋聲にちなんだものでなくては、という職人魂をひしひしと感じた今回のお菓子「秋便り」には中に秋星のシャリシャリ果肉も入ってございました。果実の方はこれから本格的に市中に出回りますのでお近くのお店でお買い求めいただけるかと存じます。「秋便り」は明日10日もご提供いただきます。ちなみに果実の方の「秋星」は、当館にて来週末の15日(金)・16日(土)のご来館者さま計50名にお配りする予定です。詳しくは150年特設サイトをご参照ください。というわけでお菓子を食べたら、やわやわりんごを狩りに行ってきます。 |
「23日」のこと |
| 2021.10.8 |
| 昨日、次回企画展「祝賀会のこと」について触れました。これが生誕150年を冠した今年度最後の展示となります。今から100年前の大正9〈1920〉年11月23日、文壇において同年生まれの田山花袋・徳田秋聲誕生50年記念祝賀会が開催(数え年)。現在、犀星記念館さんの秋聲コーナーでもご紹介くださっているとおり、ゆかりの文士たちの講演、演奏会、晩餐会など盛りだくさんで150名ほどが参加したと言われています。この10年後の昭和6〈1931〉年11月3日には、秋聲還暦祝賀会が開催されますが(こちらは満年齢)、その時すでに花袋の姿はなし…花袋はこの前年に死去しており、秋聲は当日、隣に並ぶべき人のいない寂しい心のうちを語っています。 この展示ではそれら祝賀会のほか出版記念会や秋聲を中心とする会合「二日会」「秋聲後援会」「足迹会」のこと、また秋聲の受賞歴についてなど、(花袋さんを早くに喪ったことを除き)華々しい事柄ばかりを集めてご紹介いたします。そしてこの流れを汲んでいるのが、今年12月23日に控える生誕150年記念祝賀会としての朗読劇「赤い花」! 基本的に秋聲の長編小説「赤い花」を主軸として物語は進行いたしますが、「祝賀会のこと」で紹介される史実を知っておかれるとよりスッとストーリーが入ってくる仕掛けになっておりますので、ハッハ~ン秋聲ってばこんな祝賀会を折々に開いてもらっていたんだね~という前提のもとご覧いただけましたら幸いです。こちらの入場券も祝皿発売と同日15日の午前10時から「チケットぴあ」での発売となります。 と、俯瞰してみると9月23日に150年特設サイト公開、10月23日には北村薫氏スペシャルトークイベント、11月23日(火・祝)は連続講座「花袋と秋聲」、12月23日に「赤い花」…と奇しくも23日しばりでお送りしております記念のもろもろ。中でも11月23日にはもうひとつ、群馬県は館林市の田山花袋記念文学館さんと当館の両館共同で来館者プレゼント企画がございます! この日、祝賀会当日のふたりの有名  なツーショット写真をもとにしたオリジナル缶バッジを、両館の来館者先着75名さまずつ(計150名)に贈呈いたします。詳しくは特設サイトよりご確認ください。 なツーショット写真をもとにしたオリジナル缶バッジを、両館の来館者先着75名さまずつ(計150名)に贈呈いたします。詳しくは特設サイトよりご確認ください。また、現在「協力展示」をご開催くださっているこおりやま文学の森資料館さんの企画展チラシを拝見しておりましたらこの日は久米正雄氏のお誕生日ということで、同館でもプレゼント企画がございました(クリックでPDF、裏面にご記載→)。久米氏…ほかでもない50年記念祝賀会の司会をつとめてくだすったお方! 今年生誕130年、おめでとうございます! |
「秋聲祝皿」発売情報更新 |
| 2021.10.7 |
金沢市立中村記念美術館さんで提供がはじまりました秋聲モチーフの和菓子の件、先日新聞に大きくご掲載いただきまして、そのお尻のほうにしれっと書き込まれておりましたように、あわせて生誕150年記念グッズのうち金彩入バージョン「秋聲祝皿」のご注文受付日が決定いたしました! 10月15日(金)17時~、生誕150年記念事業特設サイトからご制作元である三栄工業さんのサイトにリンクする形でご注文ページにお進みいただけます。 金彩なしの「秋聲豆皿」は個数制限もなしで記念館でいつでもお買い求めいただける一方(逆に通販はなしです)、「秋聲祝皿」のほうは限定150個という多いのか少ないのかちょっとはかりかねる個数限定のお品ですので、ご興味おありの方はお早めにご注文ください。こちらも吉はしさんにお願いして特別につくっていただいた少しお日持ちのするお菓子、その名も「秋聲」と、同じくご近所・東山の天野茶店さんの棒茶がセットでついてまいります。昨年開催された金沢21世紀工芸祭さんご考案による「オンライン茶会」のシステムがとても画期的ですばらしかったものですからそれをそのままパク…オマージュを捧げつつ、今回は決まった時間にお茶会こそ開催いたしませんけれども、このお品がみなさまのお手元に届くであろう11月20日~23日という日程のほうにひそかに意味を込めました。11月23日といいましたら、今から100年前の花袋と秋聲ふたりの誕生50年記念祝賀会の日! うまいことに祝日のうえ、大正9年のこの日も令和3年のその日も同じ火曜日でした。このようなご時世ですからさァみなさんご一緒に! というわけにはまいりませんが、それぞれのご環境でもって、美味しい金沢のお菓子とお茶、そしてこの美しい祝皿でふたりをお祝いしていただけましたら幸いです。いや、まったくもって新しい形!(改めまして21世紀工芸祭さんと三栄工業さん、ご協力ありがとうございます) 金彩なしの「秋聲豆皿」は個数制限もなしで記念館でいつでもお買い求めいただける一方(逆に通販はなしです)、「秋聲祝皿」のほうは限定150個という多いのか少ないのかちょっとはかりかねる個数限定のお品ですので、ご興味おありの方はお早めにご注文ください。こちらも吉はしさんにお願いして特別につくっていただいた少しお日持ちのするお菓子、その名も「秋聲」と、同じくご近所・東山の天野茶店さんの棒茶がセットでついてまいります。昨年開催された金沢21世紀工芸祭さんご考案による「オンライン茶会」のシステムがとても画期的ですばらしかったものですからそれをそのままパク…オマージュを捧げつつ、今回は決まった時間にお茶会こそ開催いたしませんけれども、このお品がみなさまのお手元に届くであろう11月20日~23日という日程のほうにひそかに意味を込めました。11月23日といいましたら、今から100年前の花袋と秋聲ふたりの誕生50年記念祝賀会の日! うまいことに祝日のうえ、大正9年のこの日も令和3年のその日も同じ火曜日でした。このようなご時世ですからさァみなさんご一緒に! というわけにはまいりませんが、それぞれのご環境でもって、美味しい金沢のお菓子とお茶、そしてこの美しい祝皿でふたりをお祝いしていただけましたら幸いです。いや、まったくもって新しい形!(改めまして21世紀工芸祭さんと三栄工業さん、ご協力ありがとうございます)なお、そんな祝賀のあれこれをご紹介するのが次回企画展「祝賀会のこと」。花袋記念文学館さんとお互いに無理のない形でゆるりとさりげなく連携しながらお届けする予定です。 |
生誕150年記念協力展示⑮ |
| 2021.10.6 |
嬉々として「もしょがきもしょがき」連呼していたあの日、東京は田端においてまたひとつありがたき展示がこの世に生まれ出でていたのでした。当館の俳句展でも秋聲が河童忌に詠んだ俳句をめぐっていろいろとご教示いただき、さらに芥川の八回忌のお写真(菊池寛とならび秋聲も写っています)もご提供いただいております田端文士村記念館さんの新企画展「愛とサヨナラの物語~芥川龍之介・田端文士たちの一期一会~」が去る2日(土)にご開幕の由! しかもその中のワンケースを秋聲資料の出品に用いてくださっている由!! ご案内が遅くなりまして申し訳ございません!!! ご存じ第1回菊池寛賞受賞作『仮装人物』に描かれる山田順子・竹久夢二がかつて田端に暮らし、そのご縁でもって秋聲にもご言及くださった次第です。河童忌以前にも田端には生前の芥川を訪ねて出かけておりますし、順子・夢二の〝愛とサヨナラ〟には不可欠な秋聲ですから、ここに出てきちゃっても何もオカシクナイオカシクナイ…。田端文士村記念館さん、お心遣いありがとうございます。ありがたく(そしてかなり強引に迫った形で)「生誕150年記念協力展示」に加えさせていただきます。あらあら同じく『仮装人物』にちろっと登場する佐多稲子に関する資料もおありですね。その他、芥川の親友・菊池寛、犀星さんご夫妻をはじめ、師・漱石(漱石と芥川の師弟関係、そして漱石の死に対する芥川のリアクションに、秋聲は自身の師・紅葉との死別を重ねていろいろ語っていたりもいたします)のお名前も見られます。毎度ご案内するたび二度見してしまうまさかの入場無料ですので、お近くの方ぜひお運びください。 また、同時開催の特別展「芥川龍之介 旧居跡地に刻まれた記憶~出土品から辿る渋沢栄一との繋がり~」では大河ドラマで話題のかの人ゆかりの資料が芥川龍之介記念館建設予定地から発掘されたというドラマティックな内容です。渋沢については実は秋聲も随筆「老年と死」(大正15年7月)でその印象を語っています。このころ実業家・大倉喜八郎の「隠退祝い」の催しが、かつて大倉や渋沢により設立された帝国劇場で開催され、秋聲もお招きにあずかったもよう。そこに渋沢の顔があり、秋聲曰く〈舞台で演説した大倉翁と渋沢翁と、いづれも九十とか八十幾歳とか云ふ、池の主のやうな怪物を見た〉とな…そのようなわけで、もし大河ドラマがこの時をまで描くなら、その会場に秋聲もいた、と想像しながらご覧ください。 また、同時開催の特別展「芥川龍之介 旧居跡地に刻まれた記憶~出土品から辿る渋沢栄一との繋がり~」では大河ドラマで話題のかの人ゆかりの資料が芥川龍之介記念館建設予定地から発掘されたというドラマティックな内容です。渋沢については実は秋聲も随筆「老年と死」(大正15年7月)でその印象を語っています。このころ実業家・大倉喜八郎の「隠退祝い」の催しが、かつて大倉や渋沢により設立された帝国劇場で開催され、秋聲もお招きにあずかったもよう。そこに渋沢の顔があり、秋聲曰く〈舞台で演説した大倉翁と渋沢翁と、いづれも九十とか八十幾歳とか云ふ、池の主のやうな怪物を見た〉とな…そのようなわけで、もし大河ドラマがこの時をまで描くなら、その会場に秋聲もいた、と想像しながらご覧ください。 |
| 「最初柿」 |
| 2021.10.2 |
| 昨日ご紹介いたしました金沢市立中村記念美術館さんにおける「生菓子の日」、本日2日より始まりましたので、さっそく潜入してまいりました! 今日明日と来週9日・10日、それから12月までの毎月第2週の土日にやってくるプレミアムデーです。2日ずつ季節によってお菓子は変わる予定で、いろいろな秋聲エピソードのなかからどんな姿で登場するのかは各月のお楽しみ。 そして今回は、アァッ!? 柿! 柿ですね! 秋ですし! 柿でした! でも、すごく青い…!(そしてかわいい) 連続講座最終回となる尾崎紅葉回サブタイトルにもありますとおり、「柿も青いうちは」はすでに当館内の合言葉といって過言ではありません。桐生悠々とともに紅葉に弟子入りをしようとしてこう一蹴されたという秋聲若かりし日のエピソードより。本来でしたら、そんな未熟なモン鴉だって突つかんわーい! と続くのですが、そこは吉はし製。こ、こらァ鴉に見つかったらえらいことに…! というやさしい甘さでたいへん美味でございました。中村記念美術館さんによりしっかり解説ペーパーもつけていただいておりますので、ここに込められたメッセージもあわ  せてお届けできようかと存じます。さらに喫茶室内にはこの呈茶イベント用に特別に製作された秋聲モチーフ角皿バージョンのご紹介ブースももうけていただき(「生菓子の日」限定と思われます)本当にいたれりつくせりです。中村記念美術館さん、ご協力ありがとうございました。12月まで何卒よろしくお願いいたします。 せてお届けできようかと存じます。さらに喫茶室内にはこの呈茶イベント用に特別に製作された秋聲モチーフ角皿バージョンのご紹介ブースももうけていただき(「生菓子の日」限定と思われます)本当にいたれりつくせりです。中村記念美術館さん、ご協力ありがとうございました。12月まで何卒よろしくお願いいたします。 当然ながらお菓子は食べたらなくなる、お茶は飲んだらなくなるものですので、右から左から超険しい顔で撮影する、喜びが顔にでないタイプの記念館一味。を現行犯で撮りおさえていた中村記念美術館一味。ウゥ…うしろのお庭の緑がとってもきれい…お茶はお熱いうちにいただきましょう。ご無礼お許しくださいませ! 当然ながらお菓子は食べたらなくなる、お茶は飲んだらなくなるものですので、右から左から超険しい顔で撮影する、喜びが顔にでないタイプの記念館一味。を現行犯で撮りおさえていた中村記念美術館一味。ウゥ…うしろのお庭の緑がとってもきれい…お茶はお熱いうちにいただきましょう。ご無礼お許しくださいませ!末雄時代にはまだ未熟な青柿であった秋聲ですが、こちらのお菓子をよくよく鑑賞すると端からほんのりと色づいてきていることがわかります。御銘は「最初柿(もしょがき)」。初日にふさわしいお名前をいただきました。秋が深まるにつれ、秋聲も生誕150年企画もここから熟してまいります。 |
朗読劇「赤い花」ができるまで②―チラシ編― |
| 2021.10.1 |
おかげさまで本日1日、当館を含む金沢市の文化施設が一斉に再開館を遂げました。朝一番からのご来館、ありがとうございました。金沢にもすこし台風の影響が及んでおり、小雨が降ったりやんだり、今晩の新内上演のうち、「生誕150年記念特別編」の〝特別編〟部分を担う茶屋街のなかの〝流し〟は難しいかもしれないな、などと思いながら久々の開館の雰囲気のなか過ごしております。 さて、本日より発売の「秋聲豆皿」。秋聲の著作の表紙を彩る草花のモチーフを集めた…とは特設サイトの紹介文にあるところですが、あれあれこちら、舞台「赤い花」チラシともふんわり雰囲気が重なっているね…? とお気づきの方いらっしゃいますでしょうか。実は、先日情報解禁となりました生誕150年記念朗読劇「赤い花」のチラシ・ポスターに使わせていただいているのはこの豆皿デザインの下絵なのです。専門用語ではエスキース? スケッチ? 豆皿完成稿の完成された美、生誕150年祝賀のバチッと華やかなる雰囲気はもちろんのこと、この下絵におけるいまだ行く末を定めきれず、ふんわりと未成熟、だけれども瑞々しいこの空気感が、生誕150年記念事業のフィナーレを飾る舞台「赤い花」のテーマにも通じるのではないかしら…との判断のもと、デザイナーさんにご無理を言ってこの段階のイラストをご提供いただいたのです。おや「赤い花」なのに〝赤い花〟がないのはこれいかに? 人とはその進む道により赤い花にも白い花にもなろうというもの…(実は『赤い花』原作には「白い花」の章がございます)。その他、苺はご存じ『あらくれ』ですし、白い花代表・百合は紅葉門下生時代の作『後の恋』表紙から。そしてこれからが季節本番の柿は、当館図録表紙にも用いた秋聲愛用のティーカップのほか、若き日に紅葉先生から「柿も青いうちは鴉も突き申さず候」と言われた体験をもとにしているとかなんとか…そうそう、明日2日(土)には同じ財団仲間の金沢市立中村記念美術館さんの喫茶室において秋聲モチーフの生菓子の提供があるのですが、そのお菓子のモチーフが柿だとかなんとか…? そんな風の噂を聞きました。実際の造形はぜひ現地で、また今後の提供予定は特設サイトでご確認ください。当館で今春呈茶会を中止した無念を中村記念美術館さんがカバーしてくださった形です。そしてお菓子は当館ご近所の名店「吉はし」さん製! 生誕150年を象徴する同じ花輪をあしらった特別なお皿でご提供いただけることになっています。 さて、本日より発売の「秋聲豆皿」。秋聲の著作の表紙を彩る草花のモチーフを集めた…とは特設サイトの紹介文にあるところですが、あれあれこちら、舞台「赤い花」チラシともふんわり雰囲気が重なっているね…? とお気づきの方いらっしゃいますでしょうか。実は、先日情報解禁となりました生誕150年記念朗読劇「赤い花」のチラシ・ポスターに使わせていただいているのはこの豆皿デザインの下絵なのです。専門用語ではエスキース? スケッチ? 豆皿完成稿の完成された美、生誕150年祝賀のバチッと華やかなる雰囲気はもちろんのこと、この下絵におけるいまだ行く末を定めきれず、ふんわりと未成熟、だけれども瑞々しいこの空気感が、生誕150年記念事業のフィナーレを飾る舞台「赤い花」のテーマにも通じるのではないかしら…との判断のもと、デザイナーさんにご無理を言ってこの段階のイラストをご提供いただいたのです。おや「赤い花」なのに〝赤い花〟がないのはこれいかに? 人とはその進む道により赤い花にも白い花にもなろうというもの…(実は『赤い花』原作には「白い花」の章がございます)。その他、苺はご存じ『あらくれ』ですし、白い花代表・百合は紅葉門下生時代の作『後の恋』表紙から。そしてこれからが季節本番の柿は、当館図録表紙にも用いた秋聲愛用のティーカップのほか、若き日に紅葉先生から「柿も青いうちは鴉も突き申さず候」と言われた体験をもとにしているとかなんとか…そうそう、明日2日(土)には同じ財団仲間の金沢市立中村記念美術館さんの喫茶室において秋聲モチーフの生菓子の提供があるのですが、そのお菓子のモチーフが柿だとかなんとか…? そんな風の噂を聞きました。実際の造形はぜひ現地で、また今後の提供予定は特設サイトでご確認ください。当館で今春呈茶会を中止した無念を中村記念美術館さんがカバーしてくださった形です。そしてお菓子は当館ご近所の名店「吉はし」さん製! 生誕150年を象徴する同じ花輪をあしらった特別なお皿でご提供いただけることになっています。 |
明日の準備 |
| 2021.9.30 |
27日は、金沢文芸館さんご主催による出前授業で、浅野町小学校さんに派遣されてまいりました。テーマは「金沢の三文豪」、金沢市の教育方針により4年生でもって“金沢の偉人を学ぶ”というカリキュラムが組まれております。また、先日21日・22日・24日の3日間、高砂大学校さんの三文豪講座にも出講いたしまして、イベント月間「秋は金沢三文豪」を前に三文豪三昧のこの月末。 明日10月1日よりはじまる「秋は金沢三文豪」は今年生誕150年を記念して当館がメインを張らせていただき、犀星・某K花館さんのお気遣いによりチラシも秋聲の代表作『縮図』初版の元気のでるお色味に。裏面には毎年恒例、三館をめぐって景品のブックカバーをもらおうスランプラリーのほか、当館主催の北村薫先生のトークイベント(今朝ほど満席となり受付終了いたしました)、三文豪に関連する映画上映、明日あさって犀星館さんと当館で開催予定の新内流しなど、秋の行事が盛りだくさんです。三館および金沢文芸館さん、石川近代文学館さんもこぞって再開館する明日10月1日からの開幕となります(~11月7日(日))。どうぞよろしくお願いいたします。 明日10月1日よりはじまる「秋は金沢三文豪」は今年生誕150年を記念して当館がメインを張らせていただき、犀星・某K花館さんのお気遣いによりチラシも秋聲の代表作『縮図』初版の元気のでるお色味に。裏面には毎年恒例、三館をめぐって景品のブックカバーをもらおうスランプラリーのほか、当館主催の北村薫先生のトークイベント(今朝ほど満席となり受付終了いたしました)、三文豪に関連する映画上映、明日あさって犀星館さんと当館で開催予定の新内流しなど、秋の行事が盛りだくさんです。三館および金沢文芸館さん、石川近代文学館さんもこぞって再開館する明日10月1日からの開幕となります(~11月7日(日))。どうぞよろしくお願いいたします。さて、7月末の展示替え休館からあれよあれよと丸二ヶ月ちょっとお休みいたしました当館、いよいよ明日から再開館するにあたり館内も職員もフワッフワです。中途にしていた企画展設営をようやく仕上げ、書斎のお花も書幅も掛け替え(すみません、以前10月は「生きのびて」の句幅にすると申し上げていたのですが、やはり夏の句の違和感がすごかったので「石上の水に雲あり今朝の秋」なる秋聲自筆のものにしました。お許しください)、それから康成文学館さんの協力展示への感謝を込めて川端康成制作秋聲文学碑建設記念のお湯のみをお出しし、夢二館さんの協力展示への感謝を込めて、お机のうえを夢二装幀『めぐりあひ』ほか愛子叢書シリーズ(復刻)で飾り、1日から販売予定と謳っておりました新グッズ「秋聲豆皿」をいよいよショップに陳列…というわけで「秋聲豆皿」新発売でございます!(通販なし) サンタ豆皿に引き続き、三栄工業株式会社さんによるオリジナルデザインで、植物を愛した秋聲にちなみその著作の装幀にあしらわれた草花を九谷の豆皿に大集合させた美しい逸品。お祝いにふさわしいその装いは、見ているだけでうっとりいたします。こちらは記念館現地のみでの販売となります。また追って発売予定の金彩入限定版「秋聲祝皿」というのもありますが、こちらは通販のみのお取り扱い(10月中旬~)。いずれも詳しくは生誕150年記念特設サイトをご確認ください。 |
生誕150年記念協力展示⑮⑯ |
| 2021.9.27 |
 昨日ご紹介いたしました協力展示⑪~⑭の続きも実は上がっております。⑮にはいつもお世話になりすぎていていろいろ積み上がりすぎてもはやご恩返しのしようもない金沢湯涌夢二館さん。常設展示室でも秋聲のことをご紹介くださったうえ(協力展示⑧)、10月6日(水)からご開幕予定の企画展「夢二の次男・竹久不二彦の画業(前期)―「竹久家コレクション」にみるイラストレーター・画家・美術教師としての実像―」チラシにまで新たにご掲載くださったコーナー展示「秋聲と夢二―徳田秋聲著・竹久夢二装幀本を中心に―」…チラシにまで? …こんな美しいチラシにまで一枠ちょうだいして? 夢二さんの生誕150年っていつですか? 2034年ですね…へぇ13年先…心得ました…! というわけで、当館からも資料を提供させていただき、秋聲×夢二さんの関連資料コーナーを改めてもうけていただくことになりました。本当にありがとうございます。なお、夢二さんつながりでこの協力展示の切り込み隊長をつとめてくださった東京の竹久夢二美術館さんの企画展「夢二×文学『絵で詩をかいてみた』―竹久夢二の抒情画・著作・装幀―」(協力展示⑦)が昨日をもちまして会期終了。長い期間、たいへんお世話になりました。東京から金沢へ、バトンを繋いでいただような気持ちでおります。両館に報いるため、2034年、しかと心に刻んでおきます。 昨日ご紹介いたしました協力展示⑪~⑭の続きも実は上がっております。⑮にはいつもお世話になりすぎていていろいろ積み上がりすぎてもはやご恩返しのしようもない金沢湯涌夢二館さん。常設展示室でも秋聲のことをご紹介くださったうえ(協力展示⑧)、10月6日(水)からご開幕予定の企画展「夢二の次男・竹久不二彦の画業(前期)―「竹久家コレクション」にみるイラストレーター・画家・美術教師としての実像―」チラシにまで新たにご掲載くださったコーナー展示「秋聲と夢二―徳田秋聲著・竹久夢二装幀本を中心に―」…チラシにまで? …こんな美しいチラシにまで一枠ちょうだいして? 夢二さんの生誕150年っていつですか? 2034年ですね…へぇ13年先…心得ました…! というわけで、当館からも資料を提供させていただき、秋聲×夢二さんの関連資料コーナーを改めてもうけていただくことになりました。本当にありがとうございます。なお、夢二さんつながりでこの協力展示の切り込み隊長をつとめてくださった東京の竹久夢二美術館さんの企画展「夢二×文学『絵で詩をかいてみた』―竹久夢二の抒情画・著作・装幀―」(協力展示⑦)が昨日をもちまして会期終了。長い期間、たいへんお世話になりました。東京から金沢へ、バトンを繋いでいただような気持ちでおります。両館に報いるため、2034年、しかと心に刻んでおきます。 そしてまた当館とご近所の金沢文芸館さんでは徳田秋聲記念館共催事業「フォト&五・七・五(秋編)」なる公募展をご企画いただきました。「秋聲(秋声)」の筆名にちなみ、〝私の好きな秋のこえ、秋のいろ〟をテーマに、ご自身で撮られた写真に自作の俳句・川柳・一行詩のいずれかを添えてご提出いただき、10月13日(水)~11月20日(土)の会期で同館で展示されるというもの。こちら11月21日(日)には、俳人の中田敏樹氏による合評会もおありだそう。あさって29日(水)から募集開始となりますので、くわしくはチラシおよび同館HPをご確認ください(クリックでPDF開きます)。 そしてまた当館とご近所の金沢文芸館さんでは徳田秋聲記念館共催事業「フォト&五・七・五(秋編)」なる公募展をご企画いただきました。「秋聲(秋声)」の筆名にちなみ、〝私の好きな秋のこえ、秋のいろ〟をテーマに、ご自身で撮られた写真に自作の俳句・川柳・一行詩のいずれかを添えてご提出いただき、10月13日(水)~11月20日(土)の会期で同館で展示されるというもの。こちら11月21日(日)には、俳人の中田敏樹氏による合評会もおありだそう。あさって29日(水)から募集開始となりますので、くわしくはチラシおよび同館HPをご確認ください(クリックでPDF開きます)。 当館でもちょうど俳句展が始まりますし、「秋聲(秋声)」の号は発句(俳句)でもするときに適当につけた~と相変わらずの淡泊な調子で自ら言うておりますので、とてもタイムリーなご企画です。季語にもある一般名詞としての「秋声」の意味は「秋風など、秋を感じさせる音の響き。秋の声。」(『広辞苑』より)。ちょうど今の季節にぴったりなフレーズです。 |
生誕150年記念協力展示⑪⑫⑬⑭ |
| 2021.9.26 |
 特設サイトオープンとともにありがたいことにトトトッと一気に増えました協力展示! まずは⑪福島県のこおりやま文学の森資料館さんが再開館を迎えられた9月24日(土)より、ご収蔵の秋聲資料を贅沢にも一挙放出してくださいました! ご存じ同地で育った久米正雄を顕彰されており、久米さんといえば秋聲とも懇意であったところから今回の協力展示にご参加くださいました。ありがとうございます! 特設サイトオープンとともにありがたいことにトトトッと一気に増えました協力展示! まずは⑪福島県のこおりやま文学の森資料館さんが再開館を迎えられた9月24日(土)より、ご収蔵の秋聲資料を贅沢にも一挙放出してくださいました! ご存じ同地で育った久米正雄を顕彰されており、久米さんといえば秋聲とも懇意であったところから今回の協力展示にご参加くださいました。ありがとうございます!秋聲は「大正文壇の回顧」(昭和2年)という文章の中で、大正期には「赤門出の作家、久米正雄、芥川龍之介、菊池寛三氏の出現が、一般的にはむしろ目ざましかつた」と特筆し、「芥川氏はスタイリスト」、「久米氏は脚本で起(た)つた人で芥川氏などよりは迥(はる)かに世間的で作家肌であるのみならず、人としての品質が、色々の意味で流行作家といふ一つの型その物ではないかと思はれる」、そして「最も自然主義に近い感触のするのは菊池寛氏の芸術」など各氏の特徴を述べています。のちにダンスという共通の趣味をもつことになるインテレでモダンな通人・久米氏とは個人的にも交遊深く、秋聲を囲む「二日会」にもゲスト枠としてこないだは近松秋江君が来てくれたし、正宗白鳥君にも参加してもらったし、そのうち久米君にもきてもらうことにしてるんだ~と語っています(「二日会」)。秋聲唯一となる映像を撮ってくださったのもこの方。ともに写ったお写真や、秋聲筆久米氏宛書簡などの貴重資料を展示していただいております。お近くの方はぜひぜひご観覧くださいませ。 そして、⑫⑬は三文豪から犀星館さんと某K花館さんのお出ましです! 三館ともに10月1日からの再開館に向け準備するなかで、両館がそれぞれ秋聲にまつわる資料をご出品くださいました。秋聲と仲良しの犀星さんのところでは「特集コーナー 徳田秋聲生誕150年記念展示」と題して堂々たる特集ブースを、秋聲とアレコレあった某K花さんのところでは、例の紅葉先生が弟子たるふたりほかの似顔絵を描いた巌谷小波宛書簡のご出品がある…のですけれどもこれは協力展示、です、ね? 数にかぞえてしまってよいでしょうね…?? 秋聲が出ているからわざわざご手配くださったのですよね??? えったまたま…? いやいや! えったまたま?? あとでまたチガイマース、タマタマデースとスンッとしてそっぽを向かれるのかもしれませんが、某K花館さんで秋聲をご紹介いただけるというのはとてもレアなことですので勢いのままに協力展示に入れさせていただきました! ⑭にスライドさせていただいた石川近代文学館さんとあわせて、今年の秋はどこにいっても秋聲と遭遇! |
朗読劇「赤い花」ができるまで① |
| 2021.9.25 |
 9月23日(木・祝)、「秋聲の日」ならぬ「秋分の日」に秋聲生誕150年記念事業特設HPがオープンいたしました! イベントや新グッズ情報盛りだくさんの中でもメインイベントとなる朗読劇「赤い花」のご出演者さまが解・禁…! ようやくお披露目することができました。 9月23日(木・祝)、「秋聲の日」ならぬ「秋分の日」に秋聲生誕150年記念事業特設HPがオープンいたしました! イベントや新グッズ情報盛りだくさんの中でもメインイベントとなる朗読劇「赤い花」のご出演者さまが解・禁…! ようやくお披露目することができました。林恒宏さんは昨年の当館主催朗読劇「薔薇の円舞曲」にご出演いただき、先日のナイトミュージアム「土耳其王の所望」でも素晴らしい熱演を披露してくださったお方。秋聲を思わせる“男”を演じていただくのに林さんのほかになし! と全面的にご信頼のうえお任せすることにいたしました。ヒロイン格の松岡理恵さんは絵の描けるラジオパーソナリティとしてご活躍。当館も何度となくご取材いただき、その唯一無二の存在感がザ・米子! とシナリオを作りながらにしてすでに脳内で松岡さんがしゃべりはじめてしまったがため迷いなくご依頼をば。その相手役となる渡辺拓海さんは言わずと知れたゲーム「文豪とアルケミスト」に秋声役でご出演の声優さん。近年の秋聲の知名度アップに最も貢献してくださったお方であり(ゲームそれ自体と制作会社さまはもちろんのこと)、キャラクターを演じるにあたり、モデルとなった秋聲の作品をもお読みくださったという真摯なご姿勢に感動し(当時のインタビュー記事より)、今回はゲームを離れたところでひとりの俳優さんとしてお招きをさせていただきました。10月24日の文アルさんコンサートでも秋聲作品をご朗読くださるほか、今回の舞台でもまた新しい魅力をお見せくださることと存じます。それからうえだ星子さんは秋聲作品の朗読配信でいつもお世話になっている当館にとっての大恩人。今回はナレーションに加えいくつかの重要な配役をご担当いただき、ご朗読をお聴きになってもおわかりのとおり登場人物全員を魅力的に演じてくださる作品へのご理解の深さ、役者としての引きだしの多さをぜひぜひご堪能ください。 そして、総合演出には板倉光隆さん! これまでいくつかの催事を主催してきて、「演出」の力の大きさを知りました。今回はナレーターさんや声優さんなど、お立場の異なる演者さんにご集結いただいたこともあり、ご自身も役者として舞台に立たれるほかナレーター、声優、演出その他幅広く手がけられる板倉さんのご手腕と広い視野とが舞台をギュッとひとつにまとめてくださる大きな助けとなります。館の意向を汲みつつ、より良いものを、と模索してくださる板倉さんの強い求心力がこの舞台の未来を握る…! といったわけで、今日から船長とお呼びすることにいたします。 (つづく) |
協力展示⑩補記 |
| 2021.9.16 |
昨日ご紹介いたしました川端康成文学館さんにおける協力展示の件、だいぶん言葉足らずでした、申し訳ございません! この展示は今夏、博物館実習にいらした学生さんが手がけられたものだそうです。それにあたり秋聲のことを調べ、作品を読み、準備を重ね、工夫を凝らして展示してくださったとのこと…あらあら川端先生をお好きできっと実習にいらしたのでしょうに急に秋聲が踊り出てきて恐縮です…! とはいえ、秋聲←(愛読)―康成←(愛読〔推定〕)―実習生さん…であるならば範疇ですね?? そこまでの無理は生じてございませんね!? 康成が秋聲を愛読し始めたのは十五六歳頃のこと。古本屋さんで『黴』を買って授業中に堂々読み耽ってみたり、『あらくれ』を一読のうえ再読してみたり、石川近代文学館さんの今度の朗読会テーマ「感傷的の事」 を読んでいたりなどすることが当時の手帖に書き付けられています。また横光利一と初めて出会ったという大正10年11月、その数ヶ月前の5月には水守亀之助の新著『愛着』出版記念会に出席し、参加者の集合写真に秋聲とともに収まっている康成このとき22歳(「文章倶楽部」7月号口絵より)。まだ東京帝大の学生さんでしたので、学生服を着て出かけたよう。そして昨日もご紹介いたしましたとおり秋聲は満50歳(和服です)。おそらくここが初めましてなのでは、と思うのですが(とすると秋聲とも出会って100年??)、こりゃあちょうど実習生さんたちと同じ年頃で秋聲(実物)に出会っているということになるんじゃなかろうか! と……かなりのオフロードを力技で駆け抜けましたけれども、川端康成履修の道には秋聲の道も自ずと繋がってくる、ということにさせていただき実習生さんと秋聲の出会いに乾杯!(もっとずっと前に出会っていたならすみません!) 秋聲展示へのお取り組み、本当にありがとうございました。燻し銀、大人向け、と言われる作家作品に対する若き実習生さんのご視点を今すぐ観覧にうかがえないのがなんとも口惜しゅうございますが、これをご縁といたしまして今後とも徳田秋聲を何卒よろしくお願いいたします。 を読んでいたりなどすることが当時の手帖に書き付けられています。また横光利一と初めて出会ったという大正10年11月、その数ヶ月前の5月には水守亀之助の新著『愛着』出版記念会に出席し、参加者の集合写真に秋聲とともに収まっている康成このとき22歳(「文章倶楽部」7月号口絵より)。まだ東京帝大の学生さんでしたので、学生服を着て出かけたよう。そして昨日もご紹介いたしましたとおり秋聲は満50歳(和服です)。おそらくここが初めましてなのでは、と思うのですが(とすると秋聲とも出会って100年??)、こりゃあちょうど実習生さんたちと同じ年頃で秋聲(実物)に出会っているということになるんじゃなかろうか! と……かなりのオフロードを力技で駆け抜けましたけれども、川端康成履修の道には秋聲の道も自ずと繋がってくる、ということにさせていただき実習生さんと秋聲の出会いに乾杯!(もっとずっと前に出会っていたならすみません!) 秋聲展示へのお取り組み、本当にありがとうございました。燻し銀、大人向け、と言われる作家作品に対する若き実習生さんのご視点を今すぐ観覧にうかがえないのがなんとも口惜しゅうございますが、これをご縁といたしまして今後とも徳田秋聲を何卒よろしくお願いいたします。 |
生誕150年記念協力展示⑩(注・こちらが先でした) |
| 2021.9.15 |
9月10日付記事で、石川近代文学館さんの「大秋聲展」こと「生誕150年記念 徳田秋聲」展が臨時休館のため10月1日開幕にずれこみました~と悲しいお知らせをしておりましたところ、落ち込む当館を救う神あらわる…! その神は大阪府茨木市におわしました。西方よりたちのぼるフワーーーと神々しい光に顔を上げれば「9月4日から秋聲特設コーナーができています~~」との有り難いお告げをくださったのです。えっ神様、それすでに10日も過ぎ(以下略)茨木市立川端康成文学館さん、このたびのご参加まことにありがとうございます! ご連絡が遅くなって…とお詫びくださいましたが、ほんとうのところは同日ご開幕の(というか本体の)企画展「川端康成と横光利一―100年目の邂逅―」のご開催準備で超ご多忙のなか、そんな愚痴めいたことは一言も洩らさず秋聲生誕150年記念展示にご協力くださったのです。しかも会期のお尻も上記ご企画展と揃えてくださいましたので、あわせて長くご覧いただけようかと存じます。「1921年(大正10年)に川端康成と横光利一が邂逅してから本年は100年目となります。二人の交誼は横光が亡くなる1947年(昭和22年)までの四半世紀に渡ります。」とは同館HPでのご紹介…とするとおふたりが出会ったころ秋聲は満50歳ってわけですね。おめでたい年と言えますね(次回企画展でご紹介する花袋秋聲誕生50年祝賀会はその前年、数え年で開催)。そして横光が亡くなる昭和22年は、卯辰山の秋聲文学碑が建った年。川端康成が除幕式に参加して、前夜の記念講演会でその口から飛び出し現在に語り継がれるのが例の「日本の小説は源氏から始まって西鶴に飛び、西鶴から秋聲に飛ぶ」の名句です。おふたりの深いご交誼に右から左からひょこひょこと茶々を入れまして申し訳ございません。けれども昭和15年2月20日の秋聲日記に「帰りに横光君と銀座へ出て、資生堂でフリオンか何か呑みながら、川端君の目の病気についての話など聞き、やがて別れる」とありましたので一応お三方に共通の話題ございます! ご連絡が遅くなって…とお詫びくださいましたが、ほんとうのところは同日ご開幕の(というか本体の)企画展「川端康成と横光利一―100年目の邂逅―」のご開催準備で超ご多忙のなか、そんな愚痴めいたことは一言も洩らさず秋聲生誕150年記念展示にご協力くださったのです。しかも会期のお尻も上記ご企画展と揃えてくださいましたので、あわせて長くご覧いただけようかと存じます。「1921年(大正10年)に川端康成と横光利一が邂逅してから本年は100年目となります。二人の交誼は横光が亡くなる1947年(昭和22年)までの四半世紀に渡ります。」とは同館HPでのご紹介…とするとおふたりが出会ったころ秋聲は満50歳ってわけですね。おめでたい年と言えますね(次回企画展でご紹介する花袋秋聲誕生50年祝賀会はその前年、数え年で開催)。そして横光が亡くなる昭和22年は、卯辰山の秋聲文学碑が建った年。川端康成が除幕式に参加して、前夜の記念講演会でその口から飛び出し現在に語り継がれるのが例の「日本の小説は源氏から始まって西鶴に飛び、西鶴から秋聲に飛ぶ」の名句です。おふたりの深いご交誼に右から左からひょこひょこと茶々を入れまして申し訳ございません。けれども昭和15年2月20日の秋聲日記に「帰りに横光君と銀座へ出て、資生堂でフリオンか何か呑みながら、川端君の目の病気についての話など聞き、やがて別れる」とありましたので一応お三方に共通の話題ございます!また、川端さん絡みでさらにお詫び申し上げねばならぬことには、今月18日に開催予定であった「康成と秋聲」講座を臨時休館により10月9日に延期した結果、今月25日にご開催の予定であった石川近代文学館さん主催・秋聲作「感傷的の事」朗読会の延期日ときれいにバッティング…! Oh…そんなことって… |
「小日本」第41号 |
| 2021.9.13 |
 「秋聲の俳句が載ってるよ②」のご紹介です。当館の初代学芸員で現東海大学教授の大木志門先生より、坂の上の雲ミュージアム通信「小日本」の最新号(第41号)に秋聲の俳句について寄稿するよ~とご連絡をいただき、いくつか館蔵のお写真をご提供申し上げました同誌が本日当館に届きました! 坂の上の雲ミュージアムさま、ありがとうございます!(いつかの漱石生誕150年記念展のときにもたいへん親切にしていただきました…みなさま、あちらさまはとてもあたたかいすばらしい館ですよ…) 改めまして、題は「秋聲から見た子規」。あわせてご宣伝くださいました当館の「俳句と遺墨」展vol.2にも“秋聲から見た子規”をご紹介している手前、大きく方向性が違っていたらどうしよう…!? と、どぎまぎしたものですが、こちらのパネルではまったく不十分な秋聲の子規観を詳しくご紹介くださっていてあわせてパネルにして展示させていただきたい内容でした(いま当館周辺で話題沸騰の「生きのびて」も載っています!)。なにせ平成21年、「俳句と遺墨」展vol.1を手がけたのが他ならぬ当館学芸員時代の大木先生。また中にご言及のある秋聲の署名の書き癖についても、大木先生から教えていただきパネルのほうでもご紹介予定です。当館企画展をわざわざ9月13日~と延期後の日程でご紹介いただいておりますが、残念ながら10月1日~とさらに延期になりましたことだけ、ご来館をご計画の際にはご承知おきくださいませ。なお、「小日本」はこちらから詳細をご覧いただけますが、通販のご対応の可否につきましては同館にご確認ください。 「秋聲の俳句が載ってるよ②」のご紹介です。当館の初代学芸員で現東海大学教授の大木志門先生より、坂の上の雲ミュージアム通信「小日本」の最新号(第41号)に秋聲の俳句について寄稿するよ~とご連絡をいただき、いくつか館蔵のお写真をご提供申し上げました同誌が本日当館に届きました! 坂の上の雲ミュージアムさま、ありがとうございます!(いつかの漱石生誕150年記念展のときにもたいへん親切にしていただきました…みなさま、あちらさまはとてもあたたかいすばらしい館ですよ…) 改めまして、題は「秋聲から見た子規」。あわせてご宣伝くださいました当館の「俳句と遺墨」展vol.2にも“秋聲から見た子規”をご紹介している手前、大きく方向性が違っていたらどうしよう…!? と、どぎまぎしたものですが、こちらのパネルではまったく不十分な秋聲の子規観を詳しくご紹介くださっていてあわせてパネルにして展示させていただきたい内容でした(いま当館周辺で話題沸騰の「生きのびて」も載っています!)。なにせ平成21年、「俳句と遺墨」展vol.1を手がけたのが他ならぬ当館学芸員時代の大木先生。また中にご言及のある秋聲の署名の書き癖についても、大木先生から教えていただきパネルのほうでもご紹介予定です。当館企画展をわざわざ9月13日~と延期後の日程でご紹介いただいておりますが、残念ながら10月1日~とさらに延期になりましたことだけ、ご来館をご計画の際にはご承知おきくださいませ。なお、「小日本」はこちらから詳細をご覧いただけますが、通販のご対応の可否につきましては同館にご確認ください。と、これを書いている最中に、大木先生からも「遅くなってすみません~」と同誌が複数冊到着いたしました! いつも気にかけていただきありがとうございます。有効に活用させていただきます。記念館の発信力だけではとても及ばないところに、こうして館の外から援護射撃を仕掛ける味方がいてくださるというのは本当に心強いことです。 「俳句と遺墨」展は先日半分ほど設営をしたところにさらなる休館が決まりましたので、また少し作業中断中…全面ケースに入れようと思って入らず今回の展示候補からはずすことになりそうな秋聲の俳句をひとつ最後にご紹介いたします。「土砂ぶりとなりし銀座や五月雨」、こちらはきちんとした短冊や色紙でなく、原稿用紙の端っこに書かれ、そこだけ切り取られたペロリとした状態で残されています。全集にも未収録ながら、秋聲の姿が浮かんでくる一句です。 |
「本の雑誌」10月号 |
| 2021.9.11 |
 「秋聲の俳句が載ってるよ」と不意に教えていただき、慌てて今日本屋さんに走ってまいりました。ご近所の本屋さんになく、ちょっと街中の本屋さんにもなく、三件目でようやく入手いたしました「本の雑誌」10月号! ポストと本屋さんいってきまーす、と言い残し、お財布と郵便物だけ持ってふらっと出てゆき、結果、思いもかけない長旅となってしまいました。その旅の末に手に入れた一冊…(そうそう沢野ひとし氏のところと仰っていたな…)と目次を確認し、該当ページを拝読して、ん? 全編夢二さんのお話だな…? となって再読、もう一回――と繰り返しながらふと思い出し、いただいたメールを見返すと「25ページです」の追記あり。それに従い25ページを開きましたら、ありましたありました! 同じ沢野ひとし氏のミニコラムの中に秋聲の俳句「生きのびてまた夏草の目にしみる」が引用されておりました。ズルズルと延期続きではありますが、次回「俳句と遺墨」展を控える身にとってはなんともありがたいタイミングです。沢野先生、秋聲に触れてくださいましてありがとうございました。 「秋聲の俳句が載ってるよ」と不意に教えていただき、慌てて今日本屋さんに走ってまいりました。ご近所の本屋さんになく、ちょっと街中の本屋さんにもなく、三件目でようやく入手いたしました「本の雑誌」10月号! ポストと本屋さんいってきまーす、と言い残し、お財布と郵便物だけ持ってふらっと出てゆき、結果、思いもかけない長旅となってしまいました。その旅の末に手に入れた一冊…(そうそう沢野ひとし氏のところと仰っていたな…)と目次を確認し、該当ページを拝読して、ん? 全編夢二さんのお話だな…? となって再読、もう一回――と繰り返しながらふと思い出し、いただいたメールを見返すと「25ページです」の追記あり。それに従い25ページを開きましたら、ありましたありました! 同じ沢野ひとし氏のミニコラムの中に秋聲の俳句「生きのびてまた夏草の目にしみる」が引用されておりました。ズルズルと延期続きではありますが、次回「俳句と遺墨」展を控える身にとってはなんともありがたいタイミングです。沢野先生、秋聲に触れてくださいましてありがとうございました。同様に、昨日天啓のごときメールをくださったのは他でもない北村薫先生です。いつもありがとうございます…! 沢野氏と聞いたこの人はきっと目次で繰って見るだろう、だけど目次で繰っても出ないところに書いてあるんだよ~という細やかなお気遣いによる「25ページです」の追記でした。ひとさまのお話はきちんと最後まで聞いて心に留め置かねばなりません。とはいえせっかく夢二さんの話題とめぐりあいましたので、現在、生誕150年記念協力展示を開催してくださっている東京の竹久夢二美術館さんと金沢湯涌夢二館さん(9月末まで臨時休館中)のお顔を思い浮かべて別に二冊購入いたしました。追って送らせていただきます。 秋聲の「生きのびて」は秋聲界隈では有名な一句ですね。昭和11年、大病から奇跡的に回復した秋聲(66歳)がその喜びを詠んだものとして知られています。という気持ちでハイみなさま、昨日の記事の石川近代文学館さんのチラシをご覧ください! もういちど画像クリックでPDFを開いてみてくださいませ! ご確認いただけましたでしょうか、秋聲自筆になる「生きのびて」の句がレイアウトされているのでござます。当館の俳句展でも、展示の最後の犀星さんのご紹介パネルで少しだけ触れております。いつもはこれが詠まれた7月に、この句の自筆書幅を当館内再現書斎に展示しているところ、このご縁に感謝して、今年は北村先生をお招きする10月の床の間をこちらで飾りたいと思います。 |
| 生誕150年記念協力展示⑩ |
| 2021.9.10 |
| 本日、石川県のまん延防止等重点措置の適用期間延長にともない、臨時休館も月末まで延長されることが決まりました。「俳句と遺墨」展、ぼちぼち設営を始めていたのですが再びてっしゅ~~~う! ちょうど今日定期清掃が入って館内をピカピカにしていただいたところでしたのにお客さまをお迎えできずにもったいない限りです。ブラインドがずっと閉めきりになっているのは職員がピカピカの床でくつ下スケートをしてあそぶのを外から見られないようにするためかもしれません。いえそんなまさか、休館だからといって中で遊んではおりませんで、よーしガイドペーパーができたぞォ…って休館かーーーい! よーし講座の資料がとどいたぞォ…って延期かーーーい! と折々に天に向かって叫んだりしております。 臨時休館延長により、そこに含まれてしまった9月18日の連続講座・川端康成の回もあえなく延期。講師(石川則夫國學院大學教授)を東京からお招きする関係で、どうにか確実に開催できないか、と、お忙しい石川先生を何度もつかまえZOOMによるリモート開催の練習を重ねていたところの延期…(講師は慣れていらっしゃいますが、お恥ずかしいことに「ホスト」と言われて「ポスト?」と聞き返すくらい当館が不慣れなもので練習に付き合っていただいた次第です…) 今日は各所に電話電話で調整のうえ、最終的に川端講座をその翌月10月9日(土)の紅葉講座の日程にスライドさせることにいたしました。押し出された紅葉講座は年明けに仕切り直しての開催です。11月23日(火・祝)の最終回に触らなかったのは、この日が100年前の花袋秋聲誕生50年祝賀会の開催日であるため。ここはどうしても花袋の回でなくては…という館の勝手なこだわりから、失礼ながら紅葉先生にご移動いただくことになりました。お申し込みくださった皆様にはご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。決して先生方のせいではないのに、先生方から「みなさまに申し訳ありません、とお伝えください」と言付かりましたのでこの場を借りてお伝え申し上げます。会場をお貸しくださっている金沢ふるさと偉人館さんにも何度も何度も申し訳のないことです。  そしてこれもまた悲しいことに、石川近代文学館さんで講座と同日9月18日からご開催予定であった「生誕150年記念 徳田秋聲」展も10月1日(金)からに延期ですね…! ポスター・チラシにズバーンとあしらわれた秋聲肖像に度肝を抜かれ、東京の名誉館長(秋聲令孫)と大胆なポスターですねー! 大秋聲展って感じですねー! とキャッキャしていた矢先のことです(クリックでPDF開きます→)。こちらは当館からの依頼でなく、石川近代文学館さんが独自にご企画くださったもの。だけれども我が儘を言って「生誕150年記念協力展示」のラインナップに加わっていただきました。 そしてこれもまた悲しいことに、石川近代文学館さんで講座と同日9月18日からご開催予定であった「生誕150年記念 徳田秋聲」展も10月1日(金)からに延期ですね…! ポスター・チラシにズバーンとあしらわれた秋聲肖像に度肝を抜かれ、東京の名誉館長(秋聲令孫)と大胆なポスターですねー! 大秋聲展って感じですねー! とキャッキャしていた矢先のことです(クリックでPDF開きます→)。こちらは当館からの依頼でなく、石川近代文学館さんが独自にご企画くださったもの。だけれども我が儘を言って「生誕150年記念協力展示」のラインナップに加わっていただきました。 |
企画展「風呂敷の魅力」記録映像公開! |
| 2021.9.5 |
残念ながら臨時休館中にその会期を終えてしまった金沢くらしの博物館さんの秋聲生誕150年協力展示「風呂敷の魅力」。なんとも無念な気持ちで館内の協力展示表示を降ろしておりましたら、くらしさまから本企画展を映像にしてYouTubeで公開する、というなんとも画期的なお知らせをいただきました。たくさんの方に風呂敷の提供にご協力いただいたから…と仰るその理由天使か…! と深い感動に打ち震えながら(くらしさまはわりといつも天使です)、当館にいたっては提供に協力したというより大風呂敷で後ろから急にガッと天使を捕獲しにかかった形であったなァと在りし日のことを思ったりいたしました。展示みたかったのに! という方、もう1回見たいワ! という方、ぜひこちらからお楽しみください。 今回展示していただいた秋聲『縮図』風呂敷は、厳密にはロカ・ワークショップさんでご制作いただき、当館で受託販売させていただいているお品です(詳しくはこちらから)。確実に『縮図』でありながらかなりモダンでハイカラなデザインとなっており、モダンでハイカラな秋聲が持って歩いたらさぞ決まって見えたろう…と想像される逸品です。いつぞや名誉館長(秋聲令孫)がおみやげを包むのに使ってくださっているのが嬉しくて、「やだ、適当に包んじゃってるのに~!」と仰るそばから記念撮影をば。 今回展示していただいた秋聲『縮図』風呂敷は、厳密にはロカ・ワークショップさんでご制作いただき、当館で受託販売させていただいているお品です(詳しくはこちらから)。確実に『縮図』でありながらかなりモダンでハイカラなデザインとなっており、モダンでハイカラな秋聲が持って歩いたらさぞ決まって見えたろう…と想像される逸品です。いつぞや名誉館長(秋聲令孫)がおみやげを包むのに使ってくださっているのが嬉しくて、「やだ、適当に包んじゃってるのに~!」と仰るそばから記念撮影をば。くらしさまの映像にもありましたとおり、現代においても、西瓜を包んだりペットボトルを包んだりとかなり柔軟にいろいろなものを運べる便利アイテムとして再注目されている風呂敷ですが、秋聲がものを運ぶときに使っていたものといえば石川近代文学館さんに寄託されている信玄袋のほか、この春「徳田家所蔵品展」で公開させていただいた革の鞄、そしてこちらも徳田家からお預かりさせていただいております籐のトランクが思い浮かびます。この籐製トランクは徳田家で中を改めた際、昭和8年9月8日付の新聞の挟み込みが発見され、あらッ「町の踊り場」(昭和7年8月の帰省を描く)と「旅日記」(昭和9年11月の帰省を描く)の間のころではないですかァ~! とたいそうテンションが上がったものでした。昭和9年5月には「秋聲会」メンバーと熱海旅行にも出かけていますね。これを携え出かけたのでしょうか。 そのほか実はここだけのお話、徳田家で秋聲の“折鞄”も見せていただいたことがありました。これがはま夫人の死を描く短篇「折鞄」のソレかどうか…? いつか「折鞄」展開催のそのときに…。 |
10月23・24日 |
| 2021.9.3 |
| 10月1日・2日の新内流しと同月23日(土)には作家・北村薫先生のスペシャルトークイベントがございます。そもそも北村先生と当館とのご縁は2015年1月頃より始まりました(2015年1月24日付記事参照)。結んでくれたのは、北村先生のご著書『太宰治の辞書』(新潮社刊)。太宰その人と秋聲との直接の接点こそパッと思いつかないものの、太宰は秋聲を尊敬していたとお聞きしますので、こんなところでも(ありがとう太宰治…)と深い感謝を捧げたくなるのでした。 本書のその後も秋聲にご言及くださること多く、ホッホ~これはこれは…と虎視眈々とお招きする機を狙っておりましたところの今年生誕150年。この機を逃してなるものかっ…! というわけで、このようなご時世ではございますが、金沢21世紀美術館内シアター21にて、現状最大収容人数の半分以下となる定員50名で開催予定です。なおたいへん申し訳ないのですがオンラインでの配信の予定はございません。開催時間は16時~17時半、また僭越ながら当館学芸員が聞き手として登壇いたしますので、上記ご縁のもろもろは当日のトークにて詳しくご紹介申し上げたく存じます。それからお申し込み要項にも記載いたしましたとおり、もし「この機にぜひ北村先生にお聞きしたい!」ということがございましたら、お申し込み時(メールのみ)にあわせてお書き添えください。お時間に余裕がございましたら、代わってご質問申し上げます。  この翌日の24日(日)が「文豪とアルケミスト×OEK金澤演奏會」ですね! はからずも秋聲関連のイベントが連続することになってしまい、世の秋聲会のみなみなさまにおかれましては選択に迷わせてしまって申し訳ございません…。先日、主催者さまよりご丁寧にこちらの演奏會のチラシ・ポスターをお持ちいただきました(クリックでPDF開きます→)。おぉ…夢ではなかった…と改めて感慨深く眺めまわし、書いてもいない「秋聲生誕150年記念」の文字をそこに幻視し、そしてにこやかな犀星さんの一方、こんな不機嫌そうな顔をしていながら、でも作品を朗読してくれるんでしょ? そうでしょ? とニコニコわれらが秋声くんの当日の勇姿をも想像いたしました(ちょっともう聞こえました)。あわせて曲目のラインナップも眺めておりましたらいくつか今回初演となる楽曲も含まれているのですね~これは嬉しいこと! チラシおよびポスターは13日の再開館以降、館内でご覧くださいませ。とりたてて何のお役にも立っていないのですが、ありがたいことに「協力」クレジットに当館名も入れていただいております。 この翌日の24日(日)が「文豪とアルケミスト×OEK金澤演奏會」ですね! はからずも秋聲関連のイベントが連続することになってしまい、世の秋聲会のみなみなさまにおかれましては選択に迷わせてしまって申し訳ございません…。先日、主催者さまよりご丁寧にこちらの演奏會のチラシ・ポスターをお持ちいただきました(クリックでPDF開きます→)。おぉ…夢ではなかった…と改めて感慨深く眺めまわし、書いてもいない「秋聲生誕150年記念」の文字をそこに幻視し、そしてにこやかな犀星さんの一方、こんな不機嫌そうな顔をしていながら、でも作品を朗読してくれるんでしょ? そうでしょ? とニコニコわれらが秋声くんの当日の勇姿をも想像いたしました(ちょっともう聞こえました)。あわせて曲目のラインナップも眺めておりましたらいくつか今回初演となる楽曲も含まれているのですね~これは嬉しいこと! チラシおよびポスターは13日の再開館以降、館内でご覧くださいませ。とりたてて何のお役にも立っていないのですが、ありがたいことに「協力」クレジットに当館名も入れていただいております。演奏會のチケットはすでに販売中。詳しくは公式HPよりご確認ください。 |
新内流し「老いの底」 |
| 2021.9.1 |
| 9月1日、本日は現在秋聲生誕150年記念展示にご協力いただいている東京の竹久夢二美術館さん、金沢湯涌夢二館さん(こちらは当館同様9月12日まで臨時休館中)で顕彰される画家・竹久夢二のご命日だそうですね。当館でも13日の再開館以降、9月の書斎は夢二さん仕様にしてみるつもりでおります。とはいえ、繰り返しになりますがさすがに画幅の所蔵はございませんので、お机まわりなどをほんの気持ちばかり…。 また、それと同時に9月1日といえば関東大震災の日。大正12年のこの日、震災発生時に秋聲がたまたま単身金沢に帰省していたとは有名な話で、その体験をもとに「不安のなかに」(↓『新世帯』所収)「余震の一夜」(いずれも大正13年1月発表)などの短篇が書かれているわけですが、現在北陸中日新聞さんで毎週土日に連載中の「フアイヤ・ガン」もこの年11月の発表、震災直後の混乱ののこる東京が舞台となっています。それこれ短篇小説の系譜をご紹介する泉野図書館さんにおける上田館長による講演につきましても本日、非常にボリューミーなレジュメが館長から送られてまいりました。  さらに現代におきまして一ヶ月後の今年10月1日(金)・2日(土)には毎年恒例「新内流し」の開催が決まっております。こちらも今年のテーマは秋聲の短篇「足袋の底」(←『新世帯』所収)から新作「老いの底」。題からウッと心にくる空気を醸しつつ、先だって紋弥さんより今年の床本(台本のようなもの)をお送りいただき、冒頭からニヤリとさせる新しい試みの作品となっておりました。いわゆる“読書の秋“ですから、いよいよここからエンジンのかかってくる文学館界隈でございます。
さらに現代におきまして一ヶ月後の今年10月1日(金)・2日(土)には毎年恒例「新内流し」の開催が決まっております。こちらも今年のテーマは秋聲の短篇「足袋の底」(←『新世帯』所収)から新作「老いの底」。題からウッと心にくる空気を醸しつつ、先だって紋弥さんより今年の床本(台本のようなもの)をお送りいただき、冒頭からニヤリとさせる新しい試みの作品となっておりました。いわゆる“読書の秋“ですから、いよいよここからエンジンのかかってくる文学館界隈でございます。今年の新内は1日目夜を秋聲ゆかりの円長寺さんで、2日目夕方を当館内で実施予定で、秋聲作品にもちょこちょこ出てくる円長寺さんといいましたら何せ「ひがし茶屋街」と隣接する立地につき、生誕150年特別編といたしまして好天なら茶屋街の通りにおける“流し”も計画中。たまたま居合わせた方にはとても嬉しいサプライズとなりそうです(なお“流し”中の立ち見はご自由にしていただけますが、このようなご時世ですので円長寺さんご本堂における本編につきましては当日飛び入りでのご参加受付はいたしません。9月18日より受付開始いたしますので、必ず事前にお申し込みください)。2日目夜には犀星記念館さんでも同演目で開催決定! 犀川沿いに聴く秋聲作品もまた一興かと存じます。 |
一葉短冊についてお詫びとご報告② |
| 2021.8.27 |
| 〝秋聲は一葉のものを持っているはず〟と思う背景には、ご長男の一穂さんによる、①「文芸倶楽部」明治29年7月増刊号発表の秋聲の短篇「厄払ひ」(昨年11月5日記事参照)を読んだという一葉から(それに感服して?)〈歌を二三送られた〉と秋聲自身が「俳句日誌」なるもの(現存せず)に記し、②かつ〈秋聲の遺品の中に一葉の歌の短冊二枚と和歌三首を書いた一枚の和紙がある〉との二つの証言がちらついています(臨川書店『秋聲全集』解説および角川書店『徳田秋聲集』日本近代文学大系21・解説)。 また渋川驍が著書『ガラス絵』に記録する一穂の発言に、秋聲がかつて入手し、この発言当時(秋聲の十七回忌/昭和34年)にもたしかに徳田家に在るという資料の名がいくつか登場し、そこに現在におけるそれらの有無を書き添えれば下記のとおり。 ・尾崎紅葉晩年の俳句短冊「秋の蠅寝ながらふまへて遊ぶ也」→今回確認/正しくは 「寝がほふまへて」) ・尾崎紅葉晩年の俳句短冊「床ずれや長夜のねむり砥のごとし」→今回確認(同上/ 正しくは「長夜のうつゝ」) ・樋口一葉の歌稿『独吟歌仙行』→未確認 ・樋口一葉の原稿『にごりえ』(7章の終わりから8章のはじめ)→未確認 ・夏目漱石の秋聲宛献呈署名入『道草』→確認済・既公開(その他短冊1枚も確認済) ――脳内で原稿を短冊にすり替え、紅葉に引っ張られて各種の記憶を都合よく繋ぎ合わせてしまった感…ここから綿密な確認を怠ったこちらのミスであり決して言い訳にもならないのですが、資料にまつわる情報としてここにご紹介申し上げます。 |
一葉短冊についてお詫びとご報告① |
| 2021.8.27 |
 臨時休館により9月13日(月)開幕予定とずれこみました新企画展「俳句と遺墨vol.2~初公開/文士・画家20人の筆跡~」。今回初公開となる徳田家蔵・秋聲をはじめ計20人による50枚の短冊の中には樋口一葉の名もございます。これは貴重! となって興奮にまかせチラシ裏面画像の6枚にも採用してしまったのですが、先日このチラシをご覧になったという、いつもお世話になっているとある方から「これ…同じのがうちにもあります…」とそっとお電話をいただきました。そしてご親切にもお送りくださった画像を見れば、たしかにおんなじ――慌てて実物をよくよく確認すると、まさかの複製品…! 一瞬で全身の血の気が引きました。とんでもないことをしでかしてしまった、と思うと同時に何故見抜けなかったかと走馬灯のようにあの日この日のことを思い返しました。 臨時休館により9月13日(月)開幕予定とずれこみました新企画展「俳句と遺墨vol.2~初公開/文士・画家20人の筆跡~」。今回初公開となる徳田家蔵・秋聲をはじめ計20人による50枚の短冊の中には樋口一葉の名もございます。これは貴重! となって興奮にまかせチラシ裏面画像の6枚にも採用してしまったのですが、先日このチラシをご覧になったという、いつもお世話になっているとある方から「これ…同じのがうちにもあります…」とそっとお電話をいただきました。そしてご親切にもお送りくださった画像を見れば、たしかにおんなじ――慌てて実物をよくよく確認すると、まさかの複製品…! 一瞬で全身の血の気が引きました。とんでもないことをしでかしてしまった、と思うと同時に何故見抜けなかったかと走馬灯のようにあの日この日のことを思い返しました。単純に学芸員としての能力不足にくわえて、これら短冊すべてが徳田家由来のものであるということ、また秋聲自身の裏書きのある紅葉のものなどと一緒に見てしまったこと、何より〝秋聲は一葉のものを持っているはず〟との強い先入観が、本物と思い込み調査をおろそかにしてしまった原因もろもろ…しかし激しくショックを受ける間にもすぐさま調査に取りかかるのが真の研究者というもので、呆ける学芸員の傍らで素早く『樋口一葉全集』(筑摩書房)を繰った館長によれば、見つかった和歌二首のうち「敷嶋のうたのあらす田すきかへしむかしの春はたれかみすべき」の解題には「山梨県東山梨郡大藤村に記念碑が建てられた際複製されたため、模造品も多く現存している」とあり、「玉ぼこの道づれにとはいはざりししぐれに今日もあひてける哉」には「現在発見されているものは、すべて複製品で、まだ真筆のものは現れていない。おそらく、これらも記念に配布されたものであろう」との記載がありました。ちゃんと書いてあったねぇ…と改めて落ち込みながらも(なお館長は画像でしか見ておりませんので学芸員一人の罪です)、チラシをご覧になってこれは…と思われわざわざお電話くださったその方のご見識とご厚情に改めて深く感謝をいたしました。本来ならば(複製)と記してチラシに掲載すべきところ、恥を忍び、またこの場を借りてご報告するとともに深くお詫びを申し上げます。当該の短冊につきましては、秋聲旧蔵品には違いありませんので、複製品と明記して展示予定です。 (つづく) |
於 泉野図書館・静明寺 |
| 2021.8.25 |
 昨日、泉野図書館さんにパネル展示の設営のお手伝いにお邪魔いたしまして、本日より生誕150年記念展示「秋聲短篇小説の魅力」スタートです! 中日新聞さんでの新連載「フアイヤ・ガン」にも触れておりますしこれが入ったオリジナル文庫『短篇集Ⅱ』だけ長机にピョコリと立ててまいりました。なお置いてあるものは当館蔵の閲覧用で、借りられる際には図書館さんの開架フロアの貸出用からお願いいたします。9月4日(土)開催予定の当館・上田館長による同テーマの講演もまだ少し空きがあるようですので、ご興味おありの方は泉野図書館さんまでお申し込みください。展示は講演の翌週6日(月)まで。泉野図書館さんは毎週火曜がご休館なので、利用者さんのお邪魔にならぬようそこを狙って設営・撤去をおこなうわけですが(カナヅチでけっこうガンガンします)、対外的に休館でも中には資料点検や設備点検などなさる職員さんがいらっしゃるのだなァと昨日思ったりいたしました。当館も今年新たにできたやはり火曜の定休日を使ってメンテナンスをしたりいたしますので、夏休み中の学校の先生、みたいな感覚でしょうか。 昨日、泉野図書館さんにパネル展示の設営のお手伝いにお邪魔いたしまして、本日より生誕150年記念展示「秋聲短篇小説の魅力」スタートです! 中日新聞さんでの新連載「フアイヤ・ガン」にも触れておりますしこれが入ったオリジナル文庫『短篇集Ⅱ』だけ長机にピョコリと立ててまいりました。なお置いてあるものは当館蔵の閲覧用で、借りられる際には図書館さんの開架フロアの貸出用からお願いいたします。9月4日(土)開催予定の当館・上田館長による同テーマの講演もまだ少し空きがあるようですので、ご興味おありの方は泉野図書館さんまでお申し込みください。展示は講演の翌週6日(月)まで。泉野図書館さんは毎週火曜がご休館なので、利用者さんのお邪魔にならぬようそこを狙って設営・撤去をおこなうわけですが(カナヅチでけっこうガンガンします)、対外的に休館でも中には資料点検や設備点検などなさる職員さんがいらっしゃるのだなァと昨日思ったりいたしました。当館も今年新たにできたやはり火曜の定休日を使ってメンテナンスをしたりいたしますので、夏休み中の学校の先生、みたいな感覚でしょうか。また、9月11日(土)の金沢ナイトミュージアム「徳田秋聲『土耳其(トルコ)王の所望』」朗読会は、現状予定通り開催の見込みです。9月12日(日)までの臨時休館中は原則各館イベントはすべて中止なのですが、こちらは会場が当館でなく徳田家菩提寺・静明寺さんということで、当館より広いご本堂をお借りすることから別枠での開催ということになっております(主催も当館ではないのです)。なお当日のテーマ「土耳其王の所望」は秋聲による翻訳作品で当館オリジナル文庫『秋聲少年少女小説集』に収録。同じくオリジナル文庫から『秋聲翻案翻訳小説集』収録の全7作中3作がホーソン作品ということで、秋聲とゆかり深いアメリカの作家ナサニエル・ホーソンの原作…と言われておりますが、おおもとはギリシア神話のようで実際のところ似たようなお話はゴロゴロしているのかもしれません。秋聲が実際にどの本を用いたものか、恥ずかしながら館としてはいまだ調査に着手できていない状況です。 それにしてもこれはまた珍しいところから選ばれたもの。昨年の当館主催朗読劇「薔薇の円舞曲」にもご出演くださった林恒宏さんの語りに、太田豊さんの笛・おりん、大平清さんのサズの競演。サズ!? それすなわちトルコの弦楽器! 明日26日(木)よりナイトミュージアムHP等からお申し込み受付開始です。 |
「フアイヤ・ガン」連載スタート! |
| 2021.8.22 |
 昨日21日(土)より「北陸中日新聞」さんにて秋聲の名作短篇「フアイヤ・ガン」の連載が始まりました! 同枠ではこれまでに某K花さんの「龍潭譚」、犀星さんの「加賀金沢」と連載されてきたところのしんがり、秋聲のターンでーす! 二文豪で終わらずほんとうによかった! 連載スタート…なんと甘美な響きだことか…毎週土日掲載の全9回と伺っております。赤池佳江子さんの絶妙な挿絵とともに何卒最後までお付き合いください。イヤむしろ最後まで読まないことにはオチがつかない…あっハイ、秋聲には珍しくきれいなオチのある作品となっております。そして、アラ秋聲っておもしろいね…とうっかり片足のつま先を秋聲に捕まえられてしまった方には、本作も収録された当館オリジナル文庫・短編小説傑作集Ⅱ『車掌夫婦の死・戦時風景』をおすすめいたしますし、Ⅱからじゃきもちがわるい! という方には傑作集Ⅰ『風呂桶・和解・チビの魂』というのがございます。あるいは新聞の連載予告に引用されました小林修先生による「フアイヤ・ガン」の背景についてのご解説にご興味がわかれましたなら紅野謙介・大木志門編『21世紀日本文学ガイドブック⑥ 徳田秋聲』をお買い求めください。通常、当館内ショップでも取り扱っておりますが、いかんせん来月12日まで臨時休館中ですので、とりいそぎ書店さんか図書館さんにて。文学館に似合わずシンプルな感想で恐縮ながら、あの、これはとても面白いです(真顔)。最先端の秋聲研究がここに詰まっておりますし、何より当館が全幅の信頼を寄せております小林修先生ですから最高級品質をお約束いたします。 昨日21日(土)より「北陸中日新聞」さんにて秋聲の名作短篇「フアイヤ・ガン」の連載が始まりました! 同枠ではこれまでに某K花さんの「龍潭譚」、犀星さんの「加賀金沢」と連載されてきたところのしんがり、秋聲のターンでーす! 二文豪で終わらずほんとうによかった! 連載スタート…なんと甘美な響きだことか…毎週土日掲載の全9回と伺っております。赤池佳江子さんの絶妙な挿絵とともに何卒最後までお付き合いください。イヤむしろ最後まで読まないことにはオチがつかない…あっハイ、秋聲には珍しくきれいなオチのある作品となっております。そして、アラ秋聲っておもしろいね…とうっかり片足のつま先を秋聲に捕まえられてしまった方には、本作も収録された当館オリジナル文庫・短編小説傑作集Ⅱ『車掌夫婦の死・戦時風景』をおすすめいたしますし、Ⅱからじゃきもちがわるい! という方には傑作集Ⅰ『風呂桶・和解・チビの魂』というのがございます。あるいは新聞の連載予告に引用されました小林修先生による「フアイヤ・ガン」の背景についてのご解説にご興味がわかれましたなら紅野謙介・大木志門編『21世紀日本文学ガイドブック⑥ 徳田秋聲』をお買い求めください。通常、当館内ショップでも取り扱っておりますが、いかんせん来月12日まで臨時休館中ですので、とりいそぎ書店さんか図書館さんにて。文学館に似合わずシンプルな感想で恐縮ながら、あの、これはとても面白いです(真顔)。最先端の秋聲研究がここに詰まっておりますし、何より当館が全幅の信頼を寄せております小林修先生ですから最高級品質をお約束いたします。館ではなかなか思うように活動できないなか、こうして他の媒体でもって秋聲生誕150年を盛り上げてくださることが本当にありがたく、また、あわせてご掲載頂きました秋聲と桐生悠々にまつわる記事のほうでは泉野図書館さんにおける館長講演の告知もお書き添えいただき、「フアイヤ・ガン」から始まる秋聲短篇小説ムーヴメントをこの夏巻き起こすんだい!! とかなんとか息巻きながらいま手元にあるオリジナル文庫の原稿は長篇小説『足迹』のソレ…既刊分の在庫がもうすぐ底をつく、ということに気がつきまして、今年は新刊でなくこちらの増刷をば…10年ぶりにカバーが変わりますので、文庫本コンプリートを目指されている方はどうぞお早めに今あるバージョンをご注文ください。 |
| 「俳句の日」 |
| 2021.8.20 |
| 本当は昨日8月19日、今日は「俳句の日」なんですってね~! 8(は)19(いく)の語呂合わせですって~! と呑気に書くつもりでおりました。が、生憎の臨時休館延長発表で急遽内容差し替えに。改めまして1日遅れの「俳句の日」、当館の次回企画展「俳句と遺墨vol.2」の宣伝にはうってつけの日でございました。休館延長にともない本企画展も9月13日(月)からとさらに開幕が遅れますので、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。 今回初公開する予定の徳田家蔵短冊50枚のうち秋聲の自筆は5点、すべて俳句で、中に「初雷の雨雲ちかき軒端哉」というのがございます。これに関して、似たものに「雨雲の軒端に近く雷す」という句があり、こちらは「文芸春秋」誌に記録されるところによれば昭和8年7月24日、田端自笑軒における芥川龍之介の七回忌に秋聲が出席して詠んだもの。芥川の忌日すなわち「河童忌」からのどうもいつもお世話になっております田端文士村記念館さんのご案内です!  今回の俳句展でもいろいろとお力添えをいただいておりながら、ご紹介が遅くなり申し訳ありません。現在同館では特別企画展「河童忌記念帖2021in田端」(←画像クリックでPDF開きます)が開かれており、上記のようなゆかりでおそらく秋聲もチョロリと登場させていただいているかと存じますが、何より今回の見どころは〝現代作家が選ぶ芥川龍之介のことば〟というご企画。角田光代、北村薫、山崎ナオコーラの三氏自筆によりそれぞれの心に刺さる芥川の〝ことば〟が紹介されているのです。そして当館をはじめ、すぐすぐ観覧にゆかれない方のため、ありがたいことに先日ツイッターでその原稿の画像をアップしてくださったうえ、今なら同館HPよりそれに寄せた三氏のお言葉も動画で見ることのできるというこの手厚さ…! アァありがたやありがたや…三氏それぞれのお言葉が興味深いのはもちろんのこと、とくに当館といたしましては来たる10月23日(土)に北村薫先生をお招きしての生誕150年記念スペシャルトークイベントの開催が決定しておりますので、これも旬の話題のひとつとして吸収させていただきました。 今回の俳句展でもいろいろとお力添えをいただいておりながら、ご紹介が遅くなり申し訳ありません。現在同館では特別企画展「河童忌記念帖2021in田端」(←画像クリックでPDF開きます)が開かれており、上記のようなゆかりでおそらく秋聲もチョロリと登場させていただいているかと存じますが、何より今回の見どころは〝現代作家が選ぶ芥川龍之介のことば〟というご企画。角田光代、北村薫、山崎ナオコーラの三氏自筆によりそれぞれの心に刺さる芥川の〝ことば〟が紹介されているのです。そして当館をはじめ、すぐすぐ観覧にゆかれない方のため、ありがたいことに先日ツイッターでその原稿の画像をアップしてくださったうえ、今なら同館HPよりそれに寄せた三氏のお言葉も動画で見ることのできるというこの手厚さ…! アァありがたやありがたや…三氏それぞれのお言葉が興味深いのはもちろんのこと、とくに当館といたしましては来たる10月23日(土)に北村薫先生をお招きしての生誕150年記念スペシャルトークイベントの開催が決定しておりますので、これも旬の話題のひとつとして吸収させていただきました。結局自分のところの宣伝ですみません。そう、いらっしゃるのです…! ほんとうです!!(追って、お申し込み要領をもう少し詳しく追記します) |
臨時休館延長のお知らせ |
| 2021.8.19 |
 またも浮かれている間に臨時休館が9月12日(日)まで延びてしまいました…。これに伴い、ちょうど同日までの会期延長を決めてくださっていた金沢ふるさと偉人館さんの秋聲展も終・了…! まァなんときれいな重なり方でしょうか。しかしこればかりは仕方がありません。延長をご検討くださったお気持ちに、改めてお礼を申し上げます。さきほど、最近ハイテク形式に生まれ変わった同館の「偉人館雑報」本日分を読ませていただき、ちょっと泣きました。そう…秋聲生誕150年はまだ終わっていませんね。むしろこれからが秋、秋聲の季節ですね。ご協力・ご支援くださっているみなさま方に恥じぬよう、われわれもできることを模索してまいります。 またも浮かれている間に臨時休館が9月12日(日)まで延びてしまいました…。これに伴い、ちょうど同日までの会期延長を決めてくださっていた金沢ふるさと偉人館さんの秋聲展も終・了…! まァなんときれいな重なり方でしょうか。しかしこればかりは仕方がありません。延長をご検討くださったお気持ちに、改めてお礼を申し上げます。さきほど、最近ハイテク形式に生まれ変わった同館の「偉人館雑報」本日分を読ませていただき、ちょっと泣きました。そう…秋聲生誕150年はまだ終わっていませんね。むしろこれからが秋、秋聲の季節ですね。ご協力・ご支援くださっているみなさま方に恥じぬよう、われわれもできることを模索してまいります。 と、とりいそぎ手の届く範囲で模索してみました結果、6月に通販分として数量限定販売しておりました生誕150年記念トートバッグの通販をまたも各色30枚ずつという形でお受け付けしてみようと思います。当時急いでご購入くださったみなさまには申し訳ございません。いやらしく小出しにいたしまして恐縮です。館を開けられない分、実地販売予定分をまたすこし通販に回してみるというさぐりさぐり…なにせほかでもない今年にこのバッグをご使用いただきたかったのです。もちろん生地がしっかりしておりますので来年以降もお使いいただけるお品ではありますが、今年、これを、秋聲を愛するみなさまに持ってウキウキお出かけしていただきたかった…そんな気持ちのこもったバッグです。何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。ご購入ご希望の方はグッズページをご確認ください。 なお、先般サンタ三兄弟をご注文のみなさまには、明日20日に一斉発送いたします。今は三兄弟がそれぞれの行き先を小声で確認し合いながら、わくわく出発を待っている状態。お引き取りありがとうございました。到着のおりにはぜひ可愛がってやってください(お酢は厳禁!)。サンタ三兄弟は引き続き通販お受け付け中です。 それから泉野図書館さんにおける9月4日(土)の館長講演につきましては、現状予定通りご開催とのことですが、今後予定が変わってくるかもしれません。同館にてお申し込み受付をしてくださっておりますので、そちらにてご確認をお願いいたします。 |
「文豪とアルケミスト×OEK金澤演奏會」 |
| 2021.8.18 |
おーういみんなァーーー! 秋声くんが金沢にやァってくぅるよォーーー! というわけで、昨日MROラジオ「あさダッシュ!」さんに出演させていただき、泉野図書館さんのご企画から協力展示あれこれについてお話しして、アッでも竹久夢二美術館さんとか吉備路文学館さんとか真砂中央図書館さんとか玉川図書館さんとか外の施設さんのことばっかりご紹介して、同じ財団仲間の偉人館さんとかくらしの博物館さんとか夢二館さんとかをつい身内感覚でおろそかにしてしまったな、わるかったな…と発言の内容を反芻しながらモニョモニョしている間にスンッと情報解禁となりました(公財)石川県音楽文化振興事業団ご主催「文豪とアルケミスト×OEK金澤演奏會」! ご存じ三文豪もキャラクターとなって登場するゲーム「文豪とアルケミスト」におけるサウンドトラックオーケストラコンサートにくわえ、トークゲストとしてそれぞれ秋声役、犀星役の声優・渡辺拓海さんと逢坂良太さんがご出演になるとのこと…なんとなんと…秋聲生誕150年記念事業ってわけですか…ちがいますかそうですか…生誕150年を記念して、秋声くんと犀星さんの会話を聞かせていただけるってわけですかちがいますかそうですか…ハハァ生誕150年のご褒美ってわけ……えっちがいますか? なれどそう受け取ることはそれほどまでに重い罪??? だって概要欄に「室生犀星、徳田秋声の文学作品朗読」(↓ココ)って書いてございますけれどもーーーー……!?  こちとら雨上がりの地面の上にゴロンゴロン身もだえましてもう体中が泥だらけです。秋声くんの、犀星さんのあのお声で両作家の作品が現代に蘇る…どうか泥のなかから耳をそばだてることをお許しください。会場となる石川県立音楽堂(金沢駅隣です)の横の植え込みのそのあたりから、もしくはホールの扉の上にわずかに積もった埃とともに…ご朗読が始まるやいなやギャッとなって全身から激しく発光したりして決して演出のお邪魔はいたしませんから……おとなしくしていますからァーーーー こちとら雨上がりの地面の上にゴロンゴロン身もだえましてもう体中が泥だらけです。秋声くんの、犀星さんのあのお声で両作家の作品が現代に蘇る…どうか泥のなかから耳をそばだてることをお許しください。会場となる石川県立音楽堂(金沢駅隣です)の横の植え込みのそのあたりから、もしくはホールの扉の上にわずかに積もった埃とともに…ご朗読が始まるやいなやギャッとなって全身から激しく発光したりして決して演出のお邪魔はいたしませんから……おとなしくしていますからァーーーー10月24日(日)14時~16時だそうです。そのころにどういう情勢であるやらわかりませんのであまり無邪気にご案内もできないことが悔やまれますが、ご出演のみなさまが無事に金沢にいらっしゃることのできるよう、そしてご観覧をご希望のみなさま全員がどうにか安心してその日を迎えることのできるよう心から願っております。 ちょうど二ヶ月前の今月24日(火)10時~チケット販売のご予定だそう。詳しくは公式サイトよりご確認ください。 |
生誕150年記念協力展示⑨ |
| 2021.8.13 |
 このたびは泉野図書館さんにおける生誕150年記念パネル展および当館館長による講演のご案内です! 市内文化施設が8月末まで一斉に臨時休館を余儀なくされるなか、図書館さんががんばってくださっています。ご制作いただきましたチラシ(←画像クリックでPDFが開きます)のとおり、8月25日(水)~9月6日(月)、2階のアートロビーをお借りして「秋聲短篇小説の魅力」と題したパネル展示および、会期中の9月4日(土)14時~15時半、当館上田館長による同題の講演会をご開催いただくこととなりました。外にでてゆく機会を設けていただきほんとうにありがたいことです。 このたびは泉野図書館さんにおける生誕150年記念パネル展および当館館長による講演のご案内です! 市内文化施設が8月末まで一斉に臨時休館を余儀なくされるなか、図書館さんががんばってくださっています。ご制作いただきましたチラシ(←画像クリックでPDFが開きます)のとおり、8月25日(水)~9月6日(月)、2階のアートロビーをお借りして「秋聲短篇小説の魅力」と題したパネル展示および、会期中の9月4日(土)14時~15時半、当館上田館長による同題の講演会をご開催いただくこととなりました。外にでてゆく機会を設けていただきほんとうにありがたいことです。講演会のお申し込みは8月17日(火)10時より、泉野図書館さんのほうで受け付けてくださいますので、お電話・FAX等でよろしくお願いいたします。火曜以外の開館日であれば窓口でもお受け付けくださるとのこと。コロナ禍により会場となるオアシスホールの最大収容人数よりずいぶんと絞った定員30名様と、それだけとても残念なことではありながら、ご都合のよろしい方はぜひご参加ください。 『黴』や『仮装人物』『縮図』など、代表作というとつい長篇小説を挙げられがちな秋聲ですが、なかなかどうして短篇小説だってとてもいい…そんなところをパネルから講演からぐいぐいにプレゼンさせていただく所存です。またそれはそこ、図書館さんの強みでして、ハァ~~読んでみたいい~~となったらすぐに借りて帰ることができますよ! 当館で刊行しているオリジナル文庫もすべて市内図書館さんに納本させていただいておりますし、それ以外にもいちばん古いものだと昭和22年刊行の『萌出るもの』(風雪社)のご所蔵がおありでした。しかも貸出可! 緑のチェックのかわいいやつです。しかし内容は例によってかわいくありません。物語の結末における狂った晩餐会みたいな地獄の空気感を時々思い出しては苦しくなることのある秋聲記念館です。この機にぜひお手にとってみてください(それほど長くはありませんが、短篇小説の魅力と言っておいて本作は短篇ではありません。すみません) それから館外への露出つながりでこの受付開始日時の真裏、8月17日(火)10時~MROラジオ「あさダッシュ!」さんに学芸員が出演させていただきます。石川県にまん延防止等重点措置が適用されているので電話出演になるかもしれませんが、上記企画等々についてお話しさせていただく予定です。 |
トリオデビュー |
| 2021.8.4 |
| この酷暑に南半球気分でウキウキとサンタ豆皿を発売したのが7月21日のこと。よォ~しこれから夏休みだぞぉ~と、個性の強い薄笑いの全サンタクロースに号令をかけ、勇んで整列させていたところに一ヶ月の臨時休館です。サ、サンタたちや…あんなにいっしょうけんめい前へならえのれんしゅうをしたのにごめんよ……と日々背中に突き刺さる無数の視線にいよいよ堪えきれなくなり、このたびお試しでそっと通販をやってみることといたしました。 とはいえ、一個で二個で三個で…とご注文をいただくと非常に有り難いことではありながらこうしたことに不慣れな記念館一味が混乱してしまうのが目に見えておりますし、一個だけだと送料のほうがかえってお高くなりかねませんし、何せ割れ物、扱いがデリケートなものですから職員一同知恵をしぼって問答無用の3個セット、すなわち「サンタ三兄弟」としてお出かけさせてみることに。また、サンタひとりひとりに命を吹き込む作業にすこしお時間を要することから、数量もごく控えめに、まずは限定20セットのご用意とさせていただきました。この第一弾で様子を見ながら、今後第二弾・三弾の受付を検討してゆきたく存じます。真夏のサンタ、三人まとめてぜひウチへ!! というお方、詳しくはグッズページよりご確認ください。  欲しいけど正直一家に三人はちょっと多い…というお方におかれましては、ぜひ右どなり左どなりのお宅へとお配りください。ただ両どなりのお宅もみんなみんなそうしてゆくと、結局そのうち三兄弟が大集合してしまうという魔の3しばり。三文豪、三位一体、三本締め。すわりがよいのでございます。ちなみにお写真的に一応いちばん上が長男、左下が次男、右下が三男という内部設定がありますが、原則サンタ三兄弟は三つ子につき、親かよほど親しい人でなければ表からみても裏からみてもちょっと区別がつきませんのでお含みおきを願います(※お色違いとかお顔違いとかそういうことはございません。同デザインの3個セットです)。 欲しいけど正直一家に三人はちょっと多い…というお方におかれましては、ぜひ右どなり左どなりのお宅へとお配りください。ただ両どなりのお宅もみんなみんなそうしてゆくと、結局そのうち三兄弟が大集合してしまうという魔の3しばり。三文豪、三位一体、三本締め。すわりがよいのでございます。ちなみにお写真的に一応いちばん上が長男、左下が次男、右下が三男という内部設定がありますが、原則サンタ三兄弟は三つ子につき、親かよほど親しい人でなければ表からみても裏からみてもちょっと区別がつきませんのでお含みおきを願います(※お色違いとかお顔違いとかそういうことはございません。同デザインの3個セットです)。 またトートバッグやクリアファイルと異なりこちらは数量限定品でなく、通常開館時でしたら記念館内ミュージアムショップで常時おひとつからお買い求めいただけます。そしてなにを入れてもよいのですが、三兄弟揃ってお酢はちょっと苦手のようで、与えると具合がわるくなる可能性がありますので、できれば勘弁してやってください。 |
| 偉人館さん会期延長! |
| 2021.8.3 |
臨時休館による処々の会期短縮の無念をこちらにて切々と述べておりましたらば、嬉しいお知らせが届きました。金沢ふるさと偉人館さんの協力展示、9月12日(日)まで会期延長! ありがとうございます~! 休館がこれ以上延びないことを祈ります~! 1日付の偉人館さんブログ「偉人館雑報」におけるチラシ会期の拡大(特大)表示に笑いました。あふれでる二度見感…!「「会期終わっとるやないかーーい!!」」おかげさまで一緒になって叫びました。当館の「俳句と遺墨」展でお出しする予定の秋聲短冊5枚とは異なる内容の俳句短冊もご出品いただいておりますので、両館あわせてご観覧いただけましたら幸いです。また、当館の展示では触れられませんでしたが「俳句って難しそうじゃない?」と尋ねる学生時代の秋聲(末雄青年)に「そうねー難しいけど楽しいもんだわー」などと秋聲のその先をゆき折々に俳句の妙を説いていたというのが若き日の友・桐生悠々。彼の忘れがたい一句「東風(こち)ふくや厩(うまや)を叩く枯柳」とは秋聲の自伝小説『光を追うて』に記されるところです。 1日付の偉人館さんブログ「偉人館雑報」におけるチラシ会期の拡大(特大)表示に笑いました。あふれでる二度見感…!「「会期終わっとるやないかーーい!!」」おかげさまで一緒になって叫びました。当館の「俳句と遺墨」展でお出しする予定の秋聲短冊5枚とは異なる内容の俳句短冊もご出品いただいておりますので、両館あわせてご観覧いただけましたら幸いです。また、当館の展示では触れられませんでしたが「俳句って難しそうじゃない?」と尋ねる学生時代の秋聲(末雄青年)に「そうねー難しいけど楽しいもんだわー」などと秋聲のその先をゆき折々に俳句の妙を説いていたというのが若き日の友・桐生悠々。彼の忘れがたい一句「東風(こち)ふくや厩(うまや)を叩く枯柳」とは秋聲の自伝小説『光を追うて』に記されるところです。そして秋聲のせいで少し始まりが遅れてしまった?(あるいはそのままかもしれません。どちらにせよすみません)偉人館さんの次回企画展「1964年東京オリンピック成功を支えた大島鎌吉展」は9月25日(土)から。金沢出身のロサンゼルス五輪の陸上三段跳び銅メダリストで、今春偉人館さんの常設展にも加わり、そのコーナー近くの床に三段跳びの記録を示す印があったように記憶します。それがちょいと体感では考えられない距離感で、(えっ人ってこんな飛ぶ…!?)と驚嘆したものですが、生憎そのときはひとりだったので誰とも共有できず、そんなざわざわを胸に押し込めながら悶々として帰館したのでした。企画展ご開幕のおりには、その距離と胸のざわざわを再度確かめにお邪魔します。 9月×偉人館といたしましては、18日に石川則夫先生(國學院大學教授)による川端講座(連続講座②)で再び会場をお借りします。そして、5月開催がコロナで延期としておりました木谷喜美枝先生(和洋女子大学名誉教授)による紅葉講座(連続講座③)の振り替え日がやはり同館にて10月9日(土)に決まりました。前回お申し込みくださったみなさまを優先的に、受付の日程につきましては追ってご案内を申し上げます。 |
祝・犀星生誕日 |
| 2021.8.1 |
犀星(館)さん、本日8月1日のお誕生日&開館記念日おめでとうございます! 本来であれば、水洞館長さま(先日の秋聲シンポジウムではお世話になりました!)による記念講演会がおこなわれる予定であったものが臨時休館にともないこちらも中止に…いま同館HPへ赴き、痛々しい取り消し線の下から盗み見ましたタイトル「犀星と龍之介―〈盗る〉文学の可能性―」…なんと興味深いことでしょうか、事態が落ち着きましたらぜひリベンジ開催をお願いしたいところです。また、犀星→龍之介→とくればわれらが岡栄一郎! 秋聲の甥っ子(仮)にして金沢出身の劇作家。まだ本体の企画展「偉い友達
芥川龍之介」は見にうかがえていないのですが、きっと顔を出していることと存じます。当館と同じく11月7日までの会期となっておりますので、再開館のおりにはきっとお邪魔いたします。 さて、当館の新しい企画展にも犀星さんはご登場です。企画展ページにしれっと情報をあげておりますとおり、今回は東京の秋聲旧宅から新たに発見された20名の文士や画家による50枚におよぶ短冊を一挙公開するもの。その20名さまもチラシにお名前をあげさせていただきました。①今井邦子、②巌谷小波、③岡本かの子、④尾崎紅葉、⑤梶田半古、⑥小峰大羽、⑦佐藤春夫、⑧鈴木三重吉、⑨高浜虚子、⑩田村俊子、⑪田山花袋、⑫内藤鳴雪、⑬馬場孤蝶、⑭原阿佐緒、⑮樋口一葉、⑯平福百穂、⑰正岡子規、⑱三木露風、⑲若杉鳥子……あれっひとり足りない…! と一瞬ヒヤッとしましたが、最後のひとりは他でもない、⑳秋聲自身でございます。残念ながら犀星さんのものは確認されなかったのですが(川向こうの兄弟子・某K花さんのも。これがもしあれば結構なニュースです)、お二人に関しましては館蔵品の短冊を1枚ずつ出品予定です。くわえて短冊でこそないものの、徳田家蔵・犀星さんの『犀星発句集』を初公開! 秋聲と長男一穂に宛てた献呈署名入りです。やはり俳句といえば犀星さんですから、上記20名に名をつらねていないのに何故かパネルで大きくご紹介する選抜8名さまのうちには入ってきているというこのねじれ具合。ぜひ9月1日以降、当館にてご覧ください。 さて、当館の新しい企画展にも犀星さんはご登場です。企画展ページにしれっと情報をあげておりますとおり、今回は東京の秋聲旧宅から新たに発見された20名の文士や画家による50枚におよぶ短冊を一挙公開するもの。その20名さまもチラシにお名前をあげさせていただきました。①今井邦子、②巌谷小波、③岡本かの子、④尾崎紅葉、⑤梶田半古、⑥小峰大羽、⑦佐藤春夫、⑧鈴木三重吉、⑨高浜虚子、⑩田村俊子、⑪田山花袋、⑫内藤鳴雪、⑬馬場孤蝶、⑭原阿佐緒、⑮樋口一葉、⑯平福百穂、⑰正岡子規、⑱三木露風、⑲若杉鳥子……あれっひとり足りない…! と一瞬ヒヤッとしましたが、最後のひとりは他でもない、⑳秋聲自身でございます。残念ながら犀星さんのものは確認されなかったのですが(川向こうの兄弟子・某K花さんのも。これがもしあれば結構なニュースです)、お二人に関しましては館蔵品の短冊を1枚ずつ出品予定です。くわえて短冊でこそないものの、徳田家蔵・犀星さんの『犀星発句集』を初公開! 秋聲と長男一穂に宛てた献呈署名入りです。やはり俳句といえば犀星さんですから、上記20名に名をつらねていないのに何故かパネルで大きくご紹介する選抜8名さまのうちには入ってきているというこのねじれ具合。ぜひ9月1日以降、当館にてご覧ください。それから龍之介さんにもお名前だけ登場していただきました。なぜなら若くして命を絶った龍之介を悼んで秋聲がいくつか俳句を残しているため。こちらも追ってご紹介いたします。 |
休館のうえ休館 |
| 2021.7.31 |
生誕150年記念企画展「秋聲の家―徳田家所蔵品展」が25日をもって無事に終了いたしまして、26日より展示替え休館をいただいておりました当館です。と、そうしてしばし外界から遠ざかっていた間に今月31日~来月22日までの市内施設一斉臨時休館が決まり、それにアワアワしている間に本日休館のお尻がさらに伸び、8月31日(火)までお休みすることになりました。石川県の新型コロナウイルス「まん延防止等重点措置」適用に伴う期間変更です。来館をご検討くださっていたみなさまにはご不便・ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。ちょっとワープしている間に、えっワープホールを閉じられたァ! みたいな寄る辺のなさを感じております。展示替え休館に入ったまま帰ってこられなくなった秋聲記念館… さらにおとといでしたか、地元の北國新聞さんに次回企画展「俳句と遺墨vol.2」の情報をとても大きく載せていただき、8月4日より開幕! とご宣伝いただいたその日の夕方に休館決定…! ただ不幸中の幸いと言えるのは、展示替えの段階として前回展の撤去が終わり、新しいパネルが設置されたところでのお達しでしたのでまだケースに資料を入れる前。これが入れた後ならば遣る瀬なさも一入でした。かくなれば、資料をいたずらに傷めぬよう陳列作業は8月終わりの再開館近くまで寝かせることにいたします。また撤去の際にちょいと腰を負傷し、この数日よろよろ移動を余儀なくされておりますので、そういった意味でもア~いま一日に短冊1枚しか運べないですねぇ~とのテンションでのたのた活動しております。短冊は約50枚展示予定。一ヶ月でも少し足りないのでした。それこれ含め、秋聲記念館てば、正解はCMのあと!! みたいないやらしいもったいぶり方をしているな…とお思いいただけましたら幸いです。 さらにおとといでしたか、地元の北國新聞さんに次回企画展「俳句と遺墨vol.2」の情報をとても大きく載せていただき、8月4日より開幕! とご宣伝いただいたその日の夕方に休館決定…! ただ不幸中の幸いと言えるのは、展示替えの段階として前回展の撤去が終わり、新しいパネルが設置されたところでのお達しでしたのでまだケースに資料を入れる前。これが入れた後ならば遣る瀬なさも一入でした。かくなれば、資料をいたずらに傷めぬよう陳列作業は8月終わりの再開館近くまで寝かせることにいたします。また撤去の際にちょいと腰を負傷し、この数日よろよろ移動を余儀なくされておりますので、そういった意味でもア~いま一日に短冊1枚しか運べないですねぇ~とのテンションでのたのた活動しております。短冊は約50枚展示予定。一ヶ月でも少し足りないのでした。それこれ含め、秋聲記念館てば、正解はCMのあと!! みたいないやらしいもったいぶり方をしているな…とお思いいただけましたら幸いです。またこれにより、ともに8月29日(日)までの会期でありました金沢ふるさと偉人館さんおよび金沢くらしの博物館さんの秋聲生誕150年協力展示も終…了…これは痛い…とても悲しい…。思わぬことでせっかくの展示が一ヶ月も短縮されてしまい無念ではありますが、両館のご協力にこの場を借りて厚くお礼を申し上げます。なお同じ市内の玉川図書館さん、東京の真砂中央図書館さんの協力展示は本日までとなっておりますのでご無理のない範囲でご観覧くださいませ。その他、東京の竹久夢二美術館さんは事前予約制で開館中、金沢の湯涌夢二館さんは9月まで会期はあるものの当館同様、8月末まで臨時休館予定です。 |
連続講座、開講! |
| 2021.7.23 |
 去る18日、連続講座第1回が無事終了いたしました。かなりの猛暑のなか、またこのようなご時世にご参加くださったみなさま、ありがとうございました。本来5月に開催するはずであった初回が延期となり、このたびようやく開講にいたった形です。紅葉先生をすっとぱしての秋聲の兄弟子・某K花さんが今回の主役。川向こうから安心と信頼の泉鏡花記念館・秋山館長さまをお招きいたしまして、まだ仲がよかったころのK花さんと秋聲の交流を中心にお話しいただきました。ええ、あったんですよね、そんなころが…(遠い目)。 去る18日、連続講座第1回が無事終了いたしました。かなりの猛暑のなか、またこのようなご時世にご参加くださったみなさま、ありがとうございました。本来5月に開催するはずであった初回が延期となり、このたびようやく開講にいたった形です。紅葉先生をすっとぱしての秋聲の兄弟子・某K花さんが今回の主役。川向こうから安心と信頼の泉鏡花記念館・秋山館長さまをお招きいたしまして、まだ仲がよかったころのK花さんと秋聲の交流を中心にお話しいただきました。ええ、あったんですよね、そんなころが…(遠い目)。お招きいたしまして、と書きながら、物理的にお招きした場は当館でなく当館より広い講座室をもつ金沢ふるさと偉人館さん。にもかかわらず、開会の挨拶時に「みなさまこんにちは~当館学芸員の…」と思わず口からぽろりと出てしまい、一瞬で偉人館さんを我がもののようにしてしまいましたこと、心よりお詫びを申し上げます。いくら秋聲展を開催してくださっているからってさすがに図々しかったです。ぜんぜん当館ではなかったですし、偉人館さんの講座室ですし、偉人館さんの机に椅子に、プロジェクターにマイクです。ぜんぶお借りしちゃってすみません…!(あといつもブログ「偉人館雑報」でのご紹介ありがとうございます!) 偉人館さんも触れてくださっているとおり、今回講座のサブタイトルとなりましたのは「―俳句で競う―」。互いに紅葉門下生であったころに参加した句会におけるふたりの作品や、彼らがどういった句を好んだかなど、これまでにないとても新しいテーマです。一句一句比較してゆくと、秋聲の意外とロマンティストな一面が見えてきたり、そこに奥深い物語性が垣間見えたり…と、とても一言では括ることのできない多面性を認識する貴重な機会ともなりました。また某K花さんが紅葉先生に添削を受けている句稿などのレアな資料もご紹介いただき、同じ師匠について、「徳田」と「泉」と呼び合い互いの家を行き来したり一緒に食事にでかけたり、そんな彼らのわかき日が生き生きと想像されて、なんだか甘酸っぱい気持ちにもなりました。また、それらをお話しされる秋山館長さん独特のゆったりとしていながらクッキリ会場の後ろまで通るお声の素晴らしいこと! マイクカバーのうえマスク越しでも影響皆無でございました。秋山館長さま、このたびのご協力まことにありがとうございました。今度の日曜は当館学芸員が秋山館長さまコーディネートによるシンポジウムにお邪魔いたします。 講座の最後に大きな雷が鳴りまして、いつもなにか大事なイベント時に天候が大荒れになる某K花館さんを思い、つい「アッ鏡花さんが…」と口走ってしまったのですが、K花さんは雷がお嫌いでしたね。濡れ衣でしたね、すみません。 |
ソロデビュー |
| 2021.7.21 |
 秋聲生誕150年を記念いたしまして、このたび新しいグッズが仲間入りいたしました。秋聲サンタクロース豆皿でございます! 贅沢にも九谷焼の技法を用いて、すこし立体的に盛り上がったきらきらしいサンタが底にどん! その再現率たるや!(元のネタはこちらの秋聲旧蔵品です) 目尻の皺にいたるまで実に見事なお仕事ぶりです。作家さんとはすばらしいですね。モチーフとの相性でもって選び抜かれた形とサイズ――ちょっとした豆菓子や薬味やアクセサリーなどを入れるのにもってこいの可愛らしいサイズ感(H5.7×W6.2×D2.0cm)とともに、それらを持ち上げたあとには薄笑いのサンタがどん! クリスマスシーズンとはほど遠い連日の酷暑のなか、サンタグッズを意気揚々と発売する記念館ですみません。 秋聲生誕150年を記念いたしまして、このたび新しいグッズが仲間入りいたしました。秋聲サンタクロース豆皿でございます! 贅沢にも九谷焼の技法を用いて、すこし立体的に盛り上がったきらきらしいサンタが底にどん! その再現率たるや!(元のネタはこちらの秋聲旧蔵品です) 目尻の皺にいたるまで実に見事なお仕事ぶりです。作家さんとはすばらしいですね。モチーフとの相性でもって選び抜かれた形とサイズ――ちょっとした豆菓子や薬味やアクセサリーなどを入れるのにもってこいの可愛らしいサイズ感(H5.7×W6.2×D2.0cm)とともに、それらを持ち上げたあとには薄笑いのサンタがどん! クリスマスシーズンとはほど遠い連日の酷暑のなか、サンタグッズを意気揚々と発売する記念館ですみません。こちらのお品は昨年、金沢21世紀工芸祭さんのご企画でゲーム「文豪とアルケミスト」と三文豪とのコラボ茶器制作の際にお世話になりました三栄工業株式会社さんによる新作です。あのときも、秋聲モチーフの茶器をご制作になるにあたり、わざわざ記念館にご相談に足を運んでくださったお席で「たとえばサンタでは…?」という悪魔の囁きが洩れたには洩れたのですが、犀星さん=杏と金魚、某K花さん=兎、秋聲=サンタ――いやいやちょっとバランス的にどうでしょう、せっかくの美しいデザインのなか浮いてしまうのではないでしょうか…と当館のほうがかえってぐずり(ツイッターのアイコンにまでしておいて)、さらなる協議の結果、代表作『あらくれ』の表紙にあしらわれた野苺をモチーフとしてご採用いただいたのでした。 あれから一年…サンタの目の奥に燃えていた情熱の炎はいまだ消えてはおりませんでした。生誕150年という記念すべき年に満を持して、彼のためだけに準備された白く清廉なステージのうえでまさかのソロデビュー…! というわけで、三栄工業さんの執念(ほんとうにありがたいことです)の結晶・サンタ豆皿、これより当館の目玉商品として末永くよろしくお願いいたします。今のところ通販の予定はございませんが(今後様子を見ながら検討します)、トートバッグやらと異なりとくに限定品というわけではありませんので、いつお越しになってもお買い求めいただけるよう常に複数人常駐させてゆくつもりでおります。それこそ三栄工業さんが、ハァッ!! もうこのサンタみるのイヤです…!!! と仰らない限りは永遠に…永遠につづくサンタの行列… ※ツイッターのほうで価格を間違えまして申し訳ございませんでした。 正しくは500円(税込)です。お詫びして訂正いたします。 |
吉備路文学館へ愛を込めて |
| 2021.7.12 |
| 昨日11日をもちまして、遠く岡山県は吉備路文学館さんにおける秋聲生誕150年記念協力展示の会期が終了いたしました。途中、コロナ禍による臨時休館などもあり、お忙しいところ横からたいへんなお手間をおかけしてしまった…と申し訳なくも思いつつ、ぜひご協力させてください! グッズもよければ置かせてください! と早々に温かいお返事をくださった吉備路さまのご厚情に改めまして深く深くお礼を申し上げます。白鳥、秋江、秋聲の友情が100年経っても続いているかのよう…かつ、休館になってしまってすみません、グッズの販売遅れてしまってすみません、とその都度お詫びくださったご担当者さまにかえってこちらが恐縮しきりでございました。 ほんとうにありがとうございました。今後当館に何かできることあらばぜひともにお声がけください。吉備路文学館さんの行く道に幸多からんことを!!!!!  お返しにもなりませんが、当館の白鳥・秋江仕様の書斎は今月いっぱいご覧いただけるほか、いつかのブログで今回展に白鳥さんはちろっと出てくるけれども秋江さんは展示解説などで~~と申し上げていたくせ結局一度もお出しできなかったエピソードをこちらにて。今回展では、はま夫人を喪った秋聲一家が自宅の増改築を思い立ったくだりをご紹介しており、その過程において秋江の姿が目撃されているのです。 お返しにもなりませんが、当館の白鳥・秋江仕様の書斎は今月いっぱいご覧いただけるほか、いつかのブログで今回展に白鳥さんはちろっと出てくるけれども秋江さんは展示解説などで~~と申し上げていたくせ結局一度もお出しできなかったエピソードをこちらにて。今回展では、はま夫人を喪った秋聲一家が自宅の増改築を思い立ったくだりをご紹介しており、その過程において秋江の姿が目撃されているのです。犀星館さんの方でよくお見かけする文芸評論家の窪川鶴次郎によれば、「大正十五年の秋のことであつた。ちやうど今のお宅が改築中で、洋服を着た近松秋江氏と共に、先生は庭に立つてをられた。近松氏はステツキであちこちと指して、家の話をされてゐた」(「懐かしい思ひ出の断片」/「新潮」昭和19年1月号)…とのこと。おうちの改修にあたり近松氏にあれやこれやとご相談をしていたのでしょうか。近松氏のではありませんが、秋聲の方のステッキを今回あわせて展示中。この年末に徳田家で開催された忘年会と完成披露会を兼ねた「二日会」の出席者には近松氏のお名前も確認され、ここで再び仕上がりについてのあれやこれやをふたりで話し合ったに違いありません。なお、当夜の会のメインメニューはおでんの由。 |
生誕150年記念公開シンポジウム |
| 2021.7.8 |
| こ、これが150年の力…! このたび当館でなく、他の主催者さまによる「生誕150年記念」を冠した催しがおありとのことで「イベント」ページに概要をあげさせていただきました。時は7月25日(日)14時半~16時、ところは香林坊プラザ10階ホール、テーマは公開シンポジウム「生誕150年記念 徳田秋聲を読む」でございます! ワーーー秋聲をメインテーマにしたシンポジウムだなんてウン年前の当館主催シンポジウム以来はじめてーーーー! 北陸新幹線開業前の記憶ーーー! ご企画ありがとうございます。また当日はお招きにあずかり、僭越ながら当館学芸員がパネリストとして出演させていただくこととなりました。 その他のご登壇者を確認いたしましたら同じくパネリストとして天野憲二氏(「雪嶺文学」主宰、石川県文芸協会常任理事)、水洞幸夫氏(室生犀星記念館長、金沢学院大学副学長・文学部長)、コーディネーターに秋山稔氏(泉鏡花記念館長、石川県文芸協会理事長)…って二文豪館の館長さんがそろい踏みーーー! なんと場違いなことでしょう。出演者が秋聲だけヒラ、という、前にもいちどこんなことがありましたね…。みなさまの胸をお借りするつもりで秋聲を読み、そして語らせていただきたく存じます。当館はともかく、上記豪華出演者のみなさまの「徳田秋聲を読む」体験をお聞かせいただけるなど夢のようです。参加お申し込みはご主催の石川県文芸協会事務局さんまでお電話(076-260-3581)にてお願いいたします。 上記イベント、コーディネーター役の秋山館長さんを講師としてお招きする当館主催第1回講座のちょうど一週間後でございます。7月18日(日)、当館の連続講座「兄弟子・泉鏡花と秋聲―俳句で競う」は現在お申し込み受付中。会場として金沢ふるさと偉人館さん3階の広い講座室をお借りしておりますのでまだお席に余裕がございます。ぜひ当館のほうまでお電話ください(偉人館さんへのお問合せはご遠慮願います)。  第2回講座は9月、川端康成をテーマに予定しておりますが、かつて康成展を開催したときのタイトルもまた「康成、秋聲を読む。」でした。作家になった後はもちろんのこと、まだ面識のない学生時代から秋聲作品を授業中にもこっそり読んでいた川端康成、とその歴史からご紹介したくてつけたタイトルで、現在秋聲本人に出会うことはもちろん不可能なわけですが、「秋聲を読む」ことが秋聲と出会うこと……そう思えばその自由は今なおわれらの手に!(絶版も多くて本屋さんで出会うにはレアな人だけれども!) 第2回講座は9月、川端康成をテーマに予定しておりますが、かつて康成展を開催したときのタイトルもまた「康成、秋聲を読む。」でした。作家になった後はもちろんのこと、まだ面識のない学生時代から秋聲作品を授業中にもこっそり読んでいた川端康成、とその歴史からご紹介したくてつけたタイトルで、現在秋聲本人に出会うことはもちろん不可能なわけですが、「秋聲を読む」ことが秋聲と出会うこと……そう思えばその自由は今なおわれらの手に!(絶版も多くて本屋さんで出会うにはレアな人だけれども!) |
生誕150年記念協力展示⑧ |
| 2021.7.4 |
 ゆ…夢二界隈って優しいひとの集まりなんですか…!? えっ…夢二と名のつく館には、優しくないと入れないんです…?? 本日はそんな問いとともにお送りいたします。というのもこのたび金沢湯涌夢二館さんが生誕150年記念協力展示(プレ)を常設展に紛れ込ませてくださったそうな…! ゆ…夢二界隈って優しいひとの集まりなんですか…!? えっ…夢二と名のつく館には、優しくないと入れないんです…?? 本日はそんな問いとともにお送りいたします。というのもこのたび金沢湯涌夢二館さんが生誕150年記念協力展示(プレ)を常設展に紛れ込ませてくださったそうな…! ええ、整理いたしましょう。昨日3日(日)にご開幕の新企画展「夢二×文学」ご主催は東京は文京区の竹久夢二美術館さん(協力展示実施中)、同じく昨日3日(日)にご開幕の「『増訂版 金沢湯涌夢二館収蔵品総合図録 竹久夢二』刊行記念名品展(後期)」ご主催は金沢湯涌夢二館さん(常設展のほうでプレ協力展示実施中)でございます。 きのうあんなに気まずくしてしまったのに、たいそう爽やかに「一画もうけましたよ~ほんとうに小さいですけども~」とご一報をくださいました。聞けば少し前から、常設展示中の秋聲・順子カップルによる「私たちの生活」掲載誌(複製)が日々ちょっとずつ前方へ移動しつつあったとのこと(ホラー)…そのメンテナンスも兼ね展示替え休館中に生誕150年紹介パネルを設置、夢二装幀書籍とともにコーナーを調えてくださったそう。これぞ秋聲ご本人による真の圧…! さらには今秋、もう一回りだけ大きな規模で協力展示に再度ご参画くださるとのことで、アレッあちら「金沢湯涌優しい夢二館」が正式名称でしたっけ…? 夢二と名のつく館には「なにごとも二周すべし」という格言がおあり…?? とにもかくにもありがとうございます。感謝しかございません。当館所蔵のと異なる順子さんの可愛い方の『流るるまゝに』(秋聲・菊池寛ほか序・夢二装幀)、どうか、同館でご覧くださいませ。 さて、もういくつ寝ると七夕ですが、七夕といえば夢二さんがお描きになった「婦人グラフ」表紙の女性と七夕図を見て、秋聲が「順子を描いてる!」と言い出しあれこれ文句を言ったというエピソードが思い出されます。それに対して順子さんが「もー悪口言いなさんな~(有島)生馬さんが夢二さんの絵は日本風俗に多大な貢献したって言ってますよー」(意訳)とフォローしたそう… どうしても…どうしたって夢二館さんへのご恩返しが出来ない秋聲館で…ほんとにどうも… |
| 返礼展示(気持ちばかり) |
| 2021.7.3 |
| 7月に入りまして、これまで年末年始と展示替期間しかお休みのなかったわれわれ小粒館たちに「定休日」なるものが誕生いたしました! 当館はじめ川向こうの某K花館、金沢文芸館、金沢蓄音器館、安江金箔工芸館ら東山界隈+三文豪しばりで川違いの犀星記念館さんまでが火曜休館組でございます。月曜休館組もおりますので、どうかご観覧をご計画のおりにはお手数ですが各館の休館スケジュールをあらかじめご確認いただけましたら幸いです。 そして7月に入りましたので、書斎の掛け軸もかけかえました。今月は秋聲と仲良し・正宗白鳥自筆です。ついでに机のうえの書籍類もまるっと入れ替え。一山は白鳥著作、もう一山は近松秋江著作です。といいますのも、現在協力展示を開催してくださっている各館のみなさまへのご恩返しを返礼展示のかたちで…と思い暮らして幾星霜…。なかなか手が回らずキャプションひとつ作る余裕なく、アァもう吉備路文学館さんのミニ展示「徳田秋聲生誕150年記念展 近松秋江と正宗白鳥」のお尻が見えてきている…! と追い詰められたうえの書斎にボーン!です。す、すみません…むきだしで…。ご来館の際にはぜひ書斎も覗きにいってみてください。白鳥・秋江を対象に人物評かなにか書いて、と出版社に依頼されたテイでお送りしております。中央公論社刊『近松秋江傑作選集』などは監修者として秋聲・白鳥・上司小剣・宇野浩二の名があがっていますので、この一冊の中がなかなか密ですね! 吉備路文学館さんの協力展示は今月11日(日)まで。あわせてよろしくお願いいたします。  と、一方で本日より竹久夢二美術館さんの新しい企画展が始まりました! 以前にもご案内いたしましたとおり、有島生馬と生誕150年仲間の花袋さんに挟まってまたもその存在を主張している秋聲作品(夢二装幀)でございます。混ぜてもらえてよかったですね~~~! 書斎も来月には夢二さん仕様に変えてゆくつもりです。といってもさすがに夢二画幅は所蔵していないので、お机のうえなどをほんの気持ちばかり…。そういえば、現在の企画展パネルで野溝七生子の『山梔(くちなし)』出版記念会のご紹介をしており、秋聲と山田順子、北原白秋、翁久允らが写る写真があるのですが、久允によれば、その会に当時世間を騒がせていた秋聲・順子カップルが入ってきたとき一座がシーンとしてしまったとか…そして同会場の片隅には順子と破局後の夢二さんもいらしたとか…。 と、一方で本日より竹久夢二美術館さんの新しい企画展が始まりました! 以前にもご案内いたしましたとおり、有島生馬と生誕150年仲間の花袋さんに挟まってまたもその存在を主張している秋聲作品(夢二装幀)でございます。混ぜてもらえてよかったですね~~~! 書斎も来月には夢二さん仕様に変えてゆくつもりです。といってもさすがに夢二画幅は所蔵していないので、お机のうえなどをほんの気持ちばかり…。そういえば、現在の企画展パネルで野溝七生子の『山梔(くちなし)』出版記念会のご紹介をしており、秋聲と山田順子、北原白秋、翁久允らが写る写真があるのですが、久允によれば、その会に当時世間を騒がせていた秋聲・順子カップルが入ってきたとき一座がシーンとしてしまったとか…そして同会場の片隅には順子と破局後の夢二さんもいらしたとか…。返礼のつもりがただただ気まずい感じになりました。すみません。 |
生誕150年記念協力展示⑥⑦ |
| 2021.6.30 |
おかげさまで27日をもちまして竹久夢二美術館さんにおける協力展示第一弾が会期を終了し、現在同館は次の企画展準備のため休館中。改めましてこのたびは先陣切ってご協力をいただき、まことにありがとうございました! その他の施設さまにお願いするときにも「あ~竹久夢二美術館さんがすでに参加を表明してくださってるんですけどォ~」とイヤラシイ圧にそのお名前を使わせていただきましたこと数知れず…。(えっあの竹久夢二美術館さんが…!?) と迷える他館さんの背中をぐいと押してくださったに違いありません。そして時はめぐってはやくも第二弾…そんなわけで18日記事のとおり、協力展示⑥はふたたび竹久夢二美術館さんでーす! と、その前にちょいと待たれい! 3日の前に1日があるぞ!! とのことで、図書館さん勢力から第二陣・金沢市立玉川図書館さんがこのたび名乗りをあげてくださいました! 7月1日(木)~7月31日(土)まで、なにか調べ物をするっちゃあお世話になっている同館にて秋聲関連図書コーナーを設置していただけることになり、こちらが協力展示⑥、竹久夢二美術館さん第 二弾が協力展示⑦となります。フフフフ、順調に増えてきましたね…みんなにお祝いしていただいて嬉しいですね、秋聲先生…(だけどどうせ「ニッコリともせず『どうも有難う御座いました』とそれだけ言って一礼なさる」のでしょうね…/Ⓒ今井邦子/次々回企画展で詳しくご紹介予定です)。館内に白鳥路のとお揃いの三文豪像もある同館をご利用の際には、明日以降、ぜひ秋聲コーナーにもお立ち寄りくださいませ。玉川図書館さんお忙しいなかご協力ありがとうございます! 二弾が協力展示⑦となります。フフフフ、順調に増えてきましたね…みんなにお祝いしていただいて嬉しいですね、秋聲先生…(だけどどうせ「ニッコリともせず『どうも有難う御座いました』とそれだけ言って一礼なさる」のでしょうね…/Ⓒ今井邦子/次々回企画展で詳しくご紹介予定です)。館内に白鳥路のとお揃いの三文豪像もある同館をご利用の際には、明日以降、ぜひ秋聲コーナーにもお立ち寄りくださいませ。玉川図書館さんお忙しいなかご協力ありがとうございます!さらに続きまして同じ市立の図書館仲間の泉野図書館さんでも、この夏生誕150年を記念した秋聲企画がございます。8月末頃~9月初旬にかけて、両館連携事業といたしましてその館内スペースをお借りしたミニ展示(当館プレゼンツ)と、会期中の上田館長による記念講演です。その準備のため、昨日図書館さんの休館日を利用して、会場の下見にお邪魔させていただきました。開館16周年を迎えた自分とこの展示室さえ、毎回、アレッ壁足りないんじゃ…!? となっているありさまですので、ひとさまの会場をお借りするだなんてなかなかのハードルの高さ。展示スペースをしっかり把握してパネル制作に臨みたく存じます。詳細につきましては追ってご案内のほど! |
シビックシアター☆トークショー |
| 2021.6.28 |
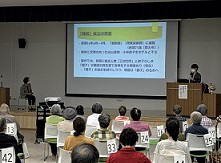 去る24日、東京都文京区におけるシビックシアター☆トークショー映画『縮図』上映会が無事終了いたしました。全3回の講座とあわせて、これにて秋聲第二の故郷・文京区における生誕150年イベントはひとまず終了でございます。お世話くださったみなさま、ご参加くださったみなさまに、心よりお礼を申し上げます。この日は、映画上映とともに学芸員のトークショー(しょ、ショーというほどのものでは…粛々とした作品解説です)も、ということで朝一番で乗り込みまして、しかしながら映画『縮図』は堂々の131分! 2時間超ある映画をご覧になったあと、一学芸員の話なんぞどなたが聴いてくださるかしら…!? と怯えに怯えた結果、ほかならぬ文京区ご在住・徳田名誉館長(秋聲令孫)に泣いてお縋りいたしまして、なんと一緒にご登壇いただくことに成功いたしました! 『縮図』の背景とともに、名誉館長の思い出をも一緒に語っていただき、ご参加のみなさまへの素敵なサプライズになったのではないでしょうか。おかげさまでほとんどの方が席を立たずに最後までご静聴くださっておりました。文京区のみなさま、温かい眼差しをありがとうございました。また、そこは優しさのかたまりである名誉館長のこと、この日のため、徳田家に遺された『縮図』主演女優・乙羽信子さんのサイン本ほか、乙羽さん・新藤兼人監督らが徳田家を訪れた際のお写真等もご持参くださり、会場のみなさまにご紹介することができました。百聞は一件に如かず、これは嬉しい! 名誉館長をはじめ、ご応募くださったみなさま(応募者多数で抽選になったと聞きました)、主催者さま、たくさんのサポーターのみなさま、そしていつも温かいお言葉で応援してくださる近代映画協会さま(『縮図』制作元)、その他関係者のみなみなさまのご協力と支えに深く感謝を申し上げます。一緒に生誕150年を盛り上げてくださって本当にありがとうございました。また、文京区における協力展示はまだまだ続きます。当日なんとか滑り込みを果たしご挨拶がかないました真砂中央図書館さん、竹久夢二美術館さんにおける秋聲コーナーには今後ともどうかご注目ください。文京区に秋聲あり! おかげさまで帰りの新幹線で何度となく叫びだしそうになりました興奮の一日でした。 去る24日、東京都文京区におけるシビックシアター☆トークショー映画『縮図』上映会が無事終了いたしました。全3回の講座とあわせて、これにて秋聲第二の故郷・文京区における生誕150年イベントはひとまず終了でございます。お世話くださったみなさま、ご参加くださったみなさまに、心よりお礼を申し上げます。この日は、映画上映とともに学芸員のトークショー(しょ、ショーというほどのものでは…粛々とした作品解説です)も、ということで朝一番で乗り込みまして、しかしながら映画『縮図』は堂々の131分! 2時間超ある映画をご覧になったあと、一学芸員の話なんぞどなたが聴いてくださるかしら…!? と怯えに怯えた結果、ほかならぬ文京区ご在住・徳田名誉館長(秋聲令孫)に泣いてお縋りいたしまして、なんと一緒にご登壇いただくことに成功いたしました! 『縮図』の背景とともに、名誉館長の思い出をも一緒に語っていただき、ご参加のみなさまへの素敵なサプライズになったのではないでしょうか。おかげさまでほとんどの方が席を立たずに最後までご静聴くださっておりました。文京区のみなさま、温かい眼差しをありがとうございました。また、そこは優しさのかたまりである名誉館長のこと、この日のため、徳田家に遺された『縮図』主演女優・乙羽信子さんのサイン本ほか、乙羽さん・新藤兼人監督らが徳田家を訪れた際のお写真等もご持参くださり、会場のみなさまにご紹介することができました。百聞は一件に如かず、これは嬉しい! 名誉館長をはじめ、ご応募くださったみなさま(応募者多数で抽選になったと聞きました)、主催者さま、たくさんのサポーターのみなさま、そしていつも温かいお言葉で応援してくださる近代映画協会さま(『縮図』制作元)、その他関係者のみなみなさまのご協力と支えに深く感謝を申し上げます。一緒に生誕150年を盛り上げてくださって本当にありがとうございました。また、文京区における協力展示はまだまだ続きます。当日なんとか滑り込みを果たしご挨拶がかないました真砂中央図書館さん、竹久夢二美術館さんにおける秋聲コーナーには今後ともどうかご注目ください。文京区に秋聲あり! おかげさまで帰りの新幹線で何度となく叫びだしそうになりました興奮の一日でした。と、この興奮の冷めぬうちにガツーンと燃ゆる鉄を叩いてくるのが一緒に講座にでてくださった声優うえだ星子さんですね! 第2回講座のなかでご朗読いただきました秋聲作品「生活のなかへ」をこのたびYouTubeチャンネル「ほしこの押入れ」にアップしてくださいました! うえださんが〝今だからこそ〟と始められたこの朗読配信というご活動。そこに〝今にこそ〟聴いていただきたい作品が出会いました。 |
吉備路さまカムバック |
| 2021.6.22 |
昨日まで臨時休館されていた協力展示開催中の吉備路文学館さんが本日より無事再開の由! おかえりなさいませ~! 吉備路さまには現在、当館オリジナルグッズを一部(クリアファイル、一筆箋)販売用に置いていただいている関係で、実は生誕150年記念デザインロゴ入りのクリアファイルもごく少数ながらお預けしているのです。両館ともに臨時休館等々で先行き不透明であったことからご案内が遅れまして恐縮です。当館での通販分は終了してしまいましたので(館内では販売中です)、同館お近くにお住まいの方はぜひ吉備路さんの方でお買い求めいただけましたら幸いです。 なお、クリアファイルの裏面は黒ベースに樹木図の拡大版。こうすると何が一番に見えてくるといって「媾曳」ですね。あっハイ「あいびき(特大)」です。あっハイ、妻帯者・川添が逢い引きをするお話です。一度目につくともうそれしか見えない病にかかってしまうものですが、この作品チョイスとサイズそれぞれにまったく意図はございません。「縮図」は代表作だから大きく~「二老婆」ははずせないから~とやりだすと、すべてが意味を持ち始め、たぶん一生終わらぬ作業になりますのでデザイナーさんのほうで字面のバランスを鑑みてはいても採用作品は基本ランダム。その結果の特大の媾曳です。 なお、クリアファイルの裏面は黒ベースに樹木図の拡大版。こうすると何が一番に見えてくるといって「媾曳」ですね。あっハイ「あいびき(特大)」です。あっハイ、妻帯者・川添が逢い引きをするお話です。一度目につくともうそれしか見えない病にかかってしまうものですが、この作品チョイスとサイズそれぞれにまったく意図はございません。「縮図」は代表作だから大きく~「二老婆」ははずせないから~とやりだすと、すべてが意味を持ち始め、たぶん一生終わらぬ作業になりますのでデザイナーさんのほうで字面のバランスを鑑みてはいても採用作品は基本ランダム。その結果の特大の媾曳です。それから本日は生誕150年記念連続講座の第2回…改め、繰り上げ第1回「鏡花と秋聲」回の参加申込の受付開始日。ほんとうの第1回・5月の紅葉回はコロナ禍で秋頃に延期となり、7月18日(日)にようやく講座開講の運びとなりました。紅葉先生をさしおいて…! と川面に乗ってどこからともなく聞こえるような、聞こえないような…そんな幻聴とともにまずは川向こうの兄弟子のご登場です。以前にもご案内いたしましたとおり、本講座のサブタイトルは「俳句で競う」。はからずも、次回企画展テーマ「俳句と遺墨」とリンクする形となりました。展示会期は8月4日(水)からと、開幕が講座終了後となってしまい当日あわせてはご覧いただけないのですが、みなさまが俳句の気持ちになっているその日一番にチラシをお配りできるよう、鋭意制作中です。 |
父の日 |
| 2021.6.20 |
| 「修吉に限らず七人の子供は皆なそれぞれに愛されてゐた。三人の女の子も、出来るだけの工面をして嫁になつた。けれど子供を教育すると云ふ方ではなかつた。単純な道徳観念と、動物的な愛情とがあるだけで、自分自身で激しく怒(いか)ることはあつても、人を戒めるとか諭すとか云ふやうな事はなかつた。神仏を信ずるとか、死を怖れるとか云ふやうな考もなかつた。 年の割に発育の遅かつた修吉は父親の広い懐に抱かれて軟かい頭に顎髭のチクチクする稚(おさな)い時分の事まで思出しながら、恁うして衰へて行く父親の可恐(おそろ)しい成行を、可成(なるべく)考へまいと力めた。 手がないので、修吉は時とすると、遂ひ近くの湯に連れて行きなどした。父親は杖に縋つて出来るだけ自分で歩かうとしたが、自由が利かなかつた。 『埒(らち)のあかんものに為(な)つたの』と云つて、丈の高い父親は、脊(せ)の低い少年の手に摑(つかま)つて歯痒ゆさうに、負惜みな笑方をした。目が先の方ばかり瞶(みつ)めて、足が一向に前にへ出ない。道に積つた雪が硬く凍つてゐて、深い灰色雲の隙から、をりをり薄日が差して来た。其処らの廂間や、塀のうへから見える木共は、皆な沈黙を守つて、雪の融ける春を待つてゐさうである。 『この雪がなくなると、ちと外へ出て見られるかの』と父親は恁云ふ場面でも、自分が暗い影に裹(つつ)まれてゐることを知らぬらしかつた。  二年三年と経つうちに、父は段々行歩の自由を褫(うば)はれた。舌が縺れて、記憶力や聴覚が次第に薄らいで来た。をりをり其事が、目前父の当つてゐる炬燵の周(まわり)で、低声(こごえ)で噂された。母親の頭脳には、年老つた良人(おっと)の死と云ふ事よりか、まだ前途(さき)の長い自分の身のうへや、修吉の事が考えられた。 二年三年と経つうちに、父は段々行歩の自由を褫(うば)はれた。舌が縺れて、記憶力や聴覚が次第に薄らいで来た。をりをり其事が、目前父の当つてゐる炬燵の周(まわり)で、低声(こごえ)で噂された。母親の頭脳には、年老つた良人(おっと)の死と云ふ事よりか、まだ前途(さき)の長い自分の身のうへや、修吉の事が考えられた。父親は、光沢のない、寂しい顔をして意味のない目で、如何(どう)かすると人々の顔を、ぢろりと瞶めて、見てゐる修吉を冷(ひや)りとさせた。 けれど修吉の胸には、『御父さんが死んだらば……』と小い心臓が躍るやうな事もあつた。息苦しい此の家庭を脱(のが)れる時の来るのが、待遠しくもあつた。」 (徳田秋聲「死後」より/金沢シリーズ『感傷的の事』収録) |
鯨餅をむさぼる |
| 2021.6.19 |
夏限定のお菓子、鯨餅(くじらもち)をお三時にいただきました。こちらは秋聲の随筆にもちらほら登場する金沢の老舗「森八」さん製。今時分にはじまって、8月中旬頃までの販売となります。 「加賀には古くより盛夏の暑さを乗り切るために、土用の丑の日に鯨汁を食す風習があり、その鯨の皮に見立てて道明寺粉・焼き昆布の粉を用いて仕上げた棹菓子が鯨餅」(同店HPより引用)とのことで、道明寺粉のチュブチュブ食感と疲れた体に染みいる甘み、何より見た目に涼やかなお菓子です。こちら、ただのお菓子レポートでなく、秋聲が好んだということでこのたびお味見をば。随筆「大学界隈」(昭和2年)に、次のように記しています。 「加賀には古くより盛夏の暑さを乗り切るために、土用の丑の日に鯨汁を食す風習があり、その鯨の皮に見立てて道明寺粉・焼き昆布の粉を用いて仕上げた棹菓子が鯨餅」(同店HPより引用)とのことで、道明寺粉のチュブチュブ食感と疲れた体に染みいる甘み、何より見た目に涼やかなお菓子です。こちら、ただのお菓子レポートでなく、秋聲が好んだということでこのたびお味見をば。随筆「大学界隈」(昭和2年)に、次のように記しています。「この間或(ある)料亭で、道明寺で作つた夏向きの羊羹風の菓子を出されて、それがちやうど金沢の鯨餅と同じものであるので、どこで売るのかを聞かうと思つて、つい忘れてしまつてゐるところへ、田舎へ点呼に行つた子供が帰りにその鯨餅をもつて来たので、久しぶりでその風味をむさぼることが出来た。自分は一体に牛皮のやうな餅気のものが好きなのである。藤村(ふじむら)のカステラが好きなのもそのためである。といつて自分は決して甘党と限つたわけでなく、下戸ながらも二三ばいの酒の美(うま)さも知つてゐるのである。自分は長いあひだの糖尿病だから、甘いものは食べないことにしてゐるが、鯨餅や蓮羊羹などを見ると、つい意地きたなく手が出てしまふのである。蓮羊羹もお茶人向きな郷里の菓子で、風味絶佳な珍菓だと思ふ。」 じょ、情報量多し…! 「田舎へ点呼」=金沢における簡閲点呼(いつでも徴兵に応じられるよう定期的に健康状態などをチェックする制度)、「子供」=長男一穂さん、その風味=「むさぼる」ほど(相当)、「藤村」=東京本郷の秋聲宅近所にあった羊羹で知られる超有名菓子舗・文士御用達、「藤村のカステラ」=高浜虚子の小説『柿二つ』冒頭に、正岡子規らしき〈病主人〉の母がそのカステラの箱(通称「ふぢむら氏」)に彼の句稿を収納したというくだりあり(同名の別店舗だったらすみません)、「酒の美さ」=白鳥さん! 秋聲下戸ながらお酒の美味しさわかるって!(6月17日記事参照)、「蓮羊羹」=オッケー次は蓮羊羹! また探して買ってきます。 |
つづく『断崖』 |
| 2021.6.18 |
| きのう竹久夢二美術館さんのお話をさせていただきました途端に朗報ーーー!! 現在、協力展示として秋聲コーナーを設けてくださっている同館の企画展「夢二デザイン1910-1930―千代紙から、銀座千疋屋の図案まで―」が27日(日)に会期を終了されましたのち、7月3日(土)より新しく始まる企画展「夢二×文学『絵で詩をかいてみた』―竹久夢二の抒情画・著作・装幀―」においても夢二×秋聲作品の一部を引き続き展示していただける、とか…! う、うちの陰気な秋聲が……しつっこくてすみません……ッッ!(まだ昨日のを引きずっている陰気な秋聲記念館) ほんとうはお送りいただいたチラシの「夢二×文学」というタイトルを拝見した瞬間にすこし期待してしまっていただなどということは内緒です。言うてさすがにさすがに。まさかそんな続けてだなんて。いやはや図々しいの極みだわい…とウフウフ言いながら期待に膨らむ心を諫めていたところにとても嬉しいお知らせでした。なんとまぁ…まだ一周まわりきってもいないというのに夢二美術館さんが先陣切って早くも協力展示二周目に…。次回は生誕150年パネル等々の設置はないながら、何がなくとも秋聲参戦とあらば第二弾として有り難くラインナップに加えさせていただく所存です。  さて、二周目にも続投予定と聞く秋聲の長篇小説『断崖』。気づけば外函には昨日記事でご紹介した『現代日本文学全集』と似た逆三角形が描かれておりました。かの円本には逆三角形の頂点にあたる部分に「ひすゐ(杉浦非水)」の署名あり。実は『断崖』それ自体には夢二のゆの字もないのですが、夢二作であることを示す印章が函・本体ともに入っています。同じく夢二装幀×秋聲作『路傍の花』(新潮社)本体にも描き込まれた○の中に左上から右下にかけてニョロリと曲線が走るソレ。大正9年刊行の『或売笑婦の話』に続き、翌10年、同じ日本評論社から刊行された『断崖』ですので、出版社の絡みでもって同じタッグで制作されたものでしょうか。実物はぜひ同館でご覧ください。なお日本評論社は大正7年、秋聲・夢二両者にゆかり深い本郷の地に創業しています。 さて、二周目にも続投予定と聞く秋聲の長篇小説『断崖』。気づけば外函には昨日記事でご紹介した『現代日本文学全集』と似た逆三角形が描かれておりました。かの円本には逆三角形の頂点にあたる部分に「ひすゐ(杉浦非水)」の署名あり。実は『断崖』それ自体には夢二のゆの字もないのですが、夢二作であることを示す印章が函・本体ともに入っています。同じく夢二装幀×秋聲作『路傍の花』(新潮社)本体にも描き込まれた○の中に左上から右下にかけてニョロリと曲線が走るソレ。大正9年刊行の『或売笑婦の話』に続き、翌10年、同じ日本評論社から刊行された『断崖』ですので、出版社の絡みでもって同じタッグで制作されたものでしょうか。実物はぜひ同館でご覧ください。なお日本評論社は大正7年、秋聲・夢二両者にゆかり深い本郷の地に創業しています。夢二さんの印章につきましては、金沢湯涌夢二館さんで今春増訂版を刊行された『金沢湯涌夢二館収蔵品総合図録 竹久夢二』に時代ごとの一覧の掲載がございます。これは非常に有り難い! 翻って秋聲の署名や落款について、きちんと時系列に整理してみたことがなく恐縮ながら、次回企画展「俳句と遺墨vol.2」中、ほんの少しだけその書き癖についてご紹介する予定です。 |
逆三角形の頂点に「ひすゐ」 |
| 2021.6.17 |
| 「カイチ」(前回記事参照)といえば小林かいち。大正~昭和初期に活躍したデザイナーで、名と繋がらずともその作品はきっと目にしたことがあるはず。これこれこんな、とてっとりばやくどこかで…と思えば現在開催中の秋聲展示でご協力をいただいている竹久夢二美術館さんでそのお名前があがっているではありませんか。「参考展示コーナー:夢二と同時代のデザイン」として、「杉浦非水・津田青楓・橋口五葉・恩地孝四郎・武井武雄・小林かいちのデザイン作品も展示紹介します」…フゥッ! 渡りに船とはまさにこのこと! ご観覧の際にはぜひご注目ください、といって秋聲とのつながりはにわかに出てこず、ただカイチで思い出しただけ…ってわけ…。 上記のラインナップでいえば武井武雄は童話畑で、恩地孝四郎は犀星畑で、橋口五葉・津田青楓は漱石畑でよくお見かけするように思います(すごく偏った見方です)。そ  して杉浦非水は主要な作家たちがみなお世話になっていますね。改造社の円本『現代日本文学全集』全62巻別巻1(久米正雄がその宣伝映像「現代日本文学巡礼」を撮ったソレ)の装幀で知られる御方です。1円でさくっと各作家の代表作が読める、との触れ込みで大評判となったこの円本の売上げが、そこに名を連ねた作家達の懐を潤したとは有名な話で、秋聲もこの頃自宅を増改築したりしておりますので大いに助けられたことでしょう。そんなくだりで、現在の企画展でも当該書籍を展示中です。 して杉浦非水は主要な作家たちがみなお世話になっていますね。改造社の円本『現代日本文学全集』全62巻別巻1(久米正雄がその宣伝映像「現代日本文学巡礼」を撮ったソレ)の装幀で知られる御方です。1円でさくっと各作家の代表作が読める、との触れ込みで大評判となったこの円本の売上げが、そこに名を連ねた作家達の懐を潤したとは有名な話で、秋聲もこの頃自宅を増改築したりしておりますので大いに助けられたことでしょう。そんなくだりで、現在の企画展でも当該書籍を展示中です。また、この印税でもって世界漫遊に出かけたのが秋聲と仲良しの正宗白鳥。昭和3年11月~翌10月まで一年をかけてアメリカ、フランス、イタリア、イギリス、ドイツを巡り、各地から秋聲に手紙を寄越してくれています。徳田家に残るその手紙の封の部分がけっこう派手にビリビリで、外国へ行ったことのない秋聲が待ちきれず、わくわくしながらやんちゃに開封したのかしら、などとも想像されて愉快です。円本については白鳥の随筆「円本のことなど」(「改造」昭和25年4月号)に記されているのですが、その冒頭は大正初期、当時文壇において一強であった「中央公論」に対抗すべく創刊された総合雑誌「黒潮」のお話から始まります(ちなみに文京アカデミアでご紹介した「生活のなかへ」は「黒潮」発表でした)。ある日同誌主宰者に招かれた晩餐の席で、彼が〈盛んにエロチツクな話をして私達を笑わせ〉、その理由を〈文士は猥談は好きなさうだから〉と後日語っていたというエピソード…〈それは狙ひを外れてゐないかも知れないが、聞き手が、酒の呑めぬ陰気な秋聲や私であつたのだから、徒労して功が少なかつたのであつた〉そうです。アッ…〈私達〉のなかに秋聲もいた…! |
カイチと秋聲 |
| 2021.6.15 |
| まだ定休日のないわれわれ小粒館たちは昨日14日(月)にこぞって開館をいたしました! もともと月曜休館の鈴木大拙館、金沢建築館のみなさま方も本日15日(火)には晴れて再開館いたします。 そして来る7月からは三文豪館および東山界隈の記念館たちは火曜が定休日となりますのでほんとうにややこしいですね! すみません! 来月以降も協力展示の会期中予定の金沢ふるさと偉人館さん、金沢くらしの博物館さんは月曜休館のお仲間となりますのでご観覧の際には重々お気をつけください。中で定期清掃をしたりミニ展示替えをしたりと休館ながらに職員さんがいる可能性もありますが、まずはわれわれ火曜組記念館職員たちがうっかり伺ってアッ閉まってら! となりそうな気がしております。気をつけます。 さて、ぼんやりしている間に金沢ふるさと偉人館さんのブログ「偉人館雑報」に秋聲ネタがざくざく連載されておりました。偉人館さんありがとうございます! とくに旧友桐生悠々のもとに関係者の手紙が残されていないというくだり…ハッとしてグッとくるものがございます。秋聲の手紙もぜったいにあるはず…!! といまだ諦めきれぬ思いもありながら、残されていないことが友情のひとつの形であったとは…。その他、徳田家旧主・横山家のこと、家族のこと、出身校である四高のこと、とひとさまのお庭に思わず打ち震えてしまうほど多くの秋聲ネタの数々、ぜひ覗いてみてください。 そして四高からの二中からの金沢くらしの博物館! こちらで昨日開幕いたしました企画展「風呂敷の魅力」につきまして、先日ご親切に展示風景写真をお送りいただきました。協力展示と称して秋聲の『縮図』風呂敷も紛れ込ませていただきましたこちら、お写真であげてしまってはもったいないのでどうか現地でご観覧くださいませ(このページはくらしさまの優しさ…)。と、風情ある風呂敷たちのなかに急にモダンな『縮図』風呂敷…それ自体は素敵なのですが全体のバランスのなかでアリャッなんだか雰囲気壊してますか…? とメールをお送りすると「ご心配  なく。隣に金大法学類のオリジナルキャラクター『カイチ』をちりばめたポップな風呂敷がいますから、2つ一緒で異空間となっています」と返ってきて笑いました。ご、ごめんよカイチ…ともに異空間を演出してゆこうぜ、カイチ…(右に見切れる紺色のカイチ→)。広く四高(金沢大学前身校)つながりということで何卒よろしくお願いいたします。カイチは獬豸。正義・公正を司る中国の伝説上の祥獣で、金沢大学法学類さんのオリジナルキャラクターだそう。一角獣と並ぶリアリズムの権化・秋聲、彼らの醸す不思議空間をお楽しみください。 なく。隣に金大法学類のオリジナルキャラクター『カイチ』をちりばめたポップな風呂敷がいますから、2つ一緒で異空間となっています」と返ってきて笑いました。ご、ごめんよカイチ…ともに異空間を演出してゆこうぜ、カイチ…(右に見切れる紺色のカイチ→)。広く四高(金沢大学前身校)つながりということで何卒よろしくお願いいたします。カイチは獬豸。正義・公正を司る中国の伝説上の祥獣で、金沢大学法学類さんのオリジナルキャラクターだそう。一角獣と並ぶリアリズムの権化・秋聲、彼らの醸す不思議空間をお楽しみください。 |
オンライン講座(最終回) |
| 2021.6.14 |
| 12日(土)、文京アカデミアさんの秋聲講座最終回がおこなわれました。第3回は当館初代学芸員で現東海大学教授・大木志門先生による「秋聲と一穂、父子作家の森川町の家」と、もっとも文京区にふさわしいお話でした。父秋聲と同じ作家の道を歩んだ長男一穂、従来ふたりの作品を比較し共通の体験を指摘するところまではあっても(それも多いことではありませんが)その作品執筆において一穂の存在が秋聲に与えた影響の指摘というのは今回が初めてのことではないでしょうか。秋聲が一穂に、でなく一穂が秋聲に、です。その具体例として主に秋聲の代表作『仮装人物』と『縮図』をご紹介いただき、ちょうど今月24日(木)に開催予定の同じ文京区における映画『縮図』の上映後、学芸員がトークにお邪魔することになっておりますので、ハイハイいただきー! と心のメモ帳にそっと記しましてございます。第3回を聴かれた方には、アッこないだ大木先生が言ってたやつ…! となることでしょう。いいものは広く! 当日はこっそり聴講者の中に混ぜていただきお話を拝聴いたしておりました。緊急事態宣言のもと結果的に全回オンラインでの実施になってしまったことは残念でしたが、遠く金沢にいながらにして参加ができるというのは有り難いことでもありました。大木先生、このたびは生誕150年記念企画へのご協力、まことにありがとうございました。そして最後に大木先生の編集された当館オリジナル文庫『秋聲の家―徳田一穂作品集』のご紹介もありがとうございます。本当はそれをきっちり参加人数分携え、会場にお邪魔する気満々だったのですがかないませんでしたので、ご興味をもたれた方、ぜひ通販等をご利用いただけましたら幸いです。  お話の最後には、文京区に秋聲旧宅が遺された経緯についても。「ついあることが当たり前のように思ってしまいますが」と仰ったそのお言葉に深く頷いてしまいました。100年を超える作家の家が今そこにあることはまったく当たり前でなく、一穂さんの葛藤とご苦労と、そして野口冨士男、川端康成をはじめとするさまざまな方々のご協力の賜物なのだ…ということをご紹介するのが現在の企画展「秋聲の家―徳田家所蔵品展」でもございます。 お話の最後には、文京区に秋聲旧宅が遺された経緯についても。「ついあることが当たり前のように思ってしまいますが」と仰ったそのお言葉に深く頷いてしまいました。100年を超える作家の家が今そこにあることはまったく当たり前でなく、一穂さんの葛藤とご苦労と、そして野口冨士男、川端康成をはじめとするさまざまな方々のご協力の賜物なのだ…ということをご紹介するのが現在の企画展「秋聲の家―徳田家所蔵品展」でもございます。記念館は本日14日(月)、一ヶ月に及ぶ臨時休館を経て再開館いたしました。本展で初公開の豊島与志雄・舟橋聖一・川端康成・広津和郎・林芙美子らによる家屋保存を求める嘆願書ほか、お近くの方はぜひ資料からご覧いただけましたら幸いです。 |
初オンライン講座(実質) |
| 2021.6.7 |
 去る5日(土)、文京アカデミアさんの秋聲講座第2回「生活のなかへ」が無事終了いたしました。ご聴講くださいましたみなさま、ありがとうございました。話し手としては学芸員にとって初のオンライン講座になりましたもので、開始前かなり早くに集合させていただき、トーク相手であるうえだ星子さんとパソコン越しに顔をあわせて会話を交わしてようやくほっと…。向こうさまの会場のみなさまにもご迷惑をおかけいたしました。しかも画角を確認しながら、あの机の端が気になる、だの、コンセントの穴のところが気になる、だの我が儘を申しまして、その都度ご調整いただき、最終的に目隠しのお花の鉢植えまでが登場し、おかげさまでうえださんとお花、美しい絵面となりました。心よりお礼を申し上げます。 去る5日(土)、文京アカデミアさんの秋聲講座第2回「生活のなかへ」が無事終了いたしました。ご聴講くださいましたみなさま、ありがとうございました。話し手としては学芸員にとって初のオンライン講座になりましたもので、開始前かなり早くに集合させていただき、トーク相手であるうえだ星子さんとパソコン越しに顔をあわせて会話を交わしてようやくほっと…。向こうさまの会場のみなさまにもご迷惑をおかけいたしました。しかも画角を確認しながら、あの机の端が気になる、だの、コンセントの穴のところが気になる、だの我が儘を申しまして、その都度ご調整いただき、最終的に目隠しのお花の鉢植えまでが登場し、おかげさまでうえださんとお花、美しい絵面となりました。心よりお礼を申し上げます。こればかりは対面でその朗読の迫力を感じていただきたかった…!! といまだ心残りではありながら、「これが今できる形」ととてもポジティブに捉え、何度となく言葉でも発信してくださったうえださんに救われました。テーマといたしました秋聲作品「生活のなかへ」もヒロインが疫病にかかって入院するという、ある意味で今に通じる〝非日常〟空間のお話。本番ではマスクをとって…とうち合わせしていたにもかかわらず、普通にマスク姿で登場して「こんにちは~」と話し始めてしまうウッカリ学芸員(いつも)の仕業もまた、顧みればこれまでにない失敗の仕方であって(いつかの文京アカデミアでやらかしたのは終了時刻間違いです)、いろいろな面であぁ世界はこんなにも変わってしまった…と思ったりもいたしました。しかし画面越しという大きなハンデにも負けない、うえださんの清澄なお声! 酔いしれましてございます。 本来であれば、無事に退院の日を迎えた「いく子」の晴れ晴れしい気持ちとともに、会場を出て東京の青空のもとウゥ~ンと大きく伸びをする…そんな美しいお天気に恵まれた一日でしたが、状況は大きく変わって各ご家庭の思い思いの一室でプツッとスイッチを切り暗い画面に映る自分の顔と不意に向き合う…そうした終わり方にも今後何か見えてくるものがあるのかもしれません。第3回、大木先生の講座もまたお楽しみに。 講座の最後にとくに文京区のみなさまに向けて協力展示のご案内をさせていただきました。真砂中央図書館さんの秋聲特設コーナーは7月末までの会期に、また竹久夢二美術館さんの本体の企画展「夢二デザイン1910ー1930―千代紙から、銀座千疋屋の図案まで―」の会期延長に伴い、中の秋聲コーナーもまた6月27日(日)までご覧いただけることになりました。ぜひぜひこちらもあわせてよろしくお願いいたします。 |
| 新グッズの件でお詫びと現況のご報告 |
| 2021.6.3 |
 1日から通販先行で発売いたしました新グッズの件、この数日でどどどっとご注文を賜り、昨日クリアファイルは早くも販売終了と相成りました。たくさんのご注文をありがとうございました。トートバッグも初日は生成りが、二日目は黒が人気で現在うまいことご注文数はとんとんに。よきバランスで通販分はなくなりそうです(残りは14日の再開館後、館内ショップで販売予定です)。もともと少量生産で恐縮ながら、ご丁寧にコメントを添えてくださるみなさまのご注文メールひとつひとつを有り難く拝読いたしております。秋聲生誕150年を各地からお祝いくださり、心よりお礼申し上げます。 1日から通販先行で発売いたしました新グッズの件、この数日でどどどっとご注文を賜り、昨日クリアファイルは早くも販売終了と相成りました。たくさんのご注文をありがとうございました。トートバッグも初日は生成りが、二日目は黒が人気で現在うまいことご注文数はとんとんに。よきバランスで通販分はなくなりそうです(残りは14日の再開館後、館内ショップで販売予定です)。もともと少量生産で恐縮ながら、ご丁寧にコメントを添えてくださるみなさまのご注文メールひとつひとつを有り難く拝読いたしております。秋聲生誕150年を各地からお祝いくださり、心よりお礼申し上げます。と、読むだけ読んでおいて、こちらからのご注文確認のご返信がまったく追いついておらず申し訳ございません! スタッフ少人数のうえ、この臨時休館中は在宅ワークの職員もおり、すれ違い勤務のなかで決して間違いのないよう懸命に慎重に作業をおこなっております。いやいや、呑気にそのブログを書いている間に…とお思いになるかもしれません。そこはすみません、発送作業は主に事務職員さんのほうでご担当いただいており、この件に関しまして学芸員はまったくの無能…せっせとメールを確認し、数量を確認し、送料を計算している職員さんたちを横目に企画展準備を進めさせていただいているのです。不慣れな者は下手に手を出さぬがよろし、ということで、休館を良いことにロビーまで広く使っていたるところに美しく積み上がってゆく包装されたトートたちの山の脇を通りすがるたび、ウワァーキレーイといいながら写真を撮ったり日々ただ愛でているだけのでくのぼう…。そう、みなさんちゃんとメール届いてるかな? 注文できてるかな? ってご不安ですよね、そうですよね、と想像しては涙を流し、送料? 文庫が一冊加わると? あっそっちのほうが?? お安いってわけぇ…! と極力お安くなるようあらゆるパターンでシミュレーションする職員さんたちを遠巻きにおろおろ眺め、みんなにでくのぼうと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに、今なってる…。 本当にすみません。おら、おらで、ひとりいぐも――なすべきことをいたします。次回企画展は平成21年に第一弾を開催した流れを汲みまして「俳句と遺墨vol.2~初公開/文士・画家20人の筆跡~」という名称に決まりました。詳細につきましてはまた後日!(注・20人の中に賢治さんは入っていません。) |
初オンライン講座 |
| 2021.6.2 |
 ご報告が遅れました。先月末29日(土)文京アカデミア講座の第1回、上田館長による「秋聲文学の評価の揺れ―漱石から川端へ」が無事終了いたしました。不慣れなZOOM操作により、映ってはいけないひとやものがちらほら画面端に見切れたりと、お見苦しい点も多くたいへん失礼をいたしました。ご参加くださったみなさま、ありがとうございました。緊急事態宣言の延長を受け、第2回・3回講座もオンラインでの開催となります。今週末の声優うえだ星子さんのご朗読はぜひ生で、あの迫力をこそ感じていただきたかったのですが残念無念…(うえださんブログでのご周知ありがとうございます!)。 ご報告が遅れました。先月末29日(土)文京アカデミア講座の第1回、上田館長による「秋聲文学の評価の揺れ―漱石から川端へ」が無事終了いたしました。不慣れなZOOM操作により、映ってはいけないひとやものがちらほら画面端に見切れたりと、お見苦しい点も多くたいへん失礼をいたしました。ご参加くださったみなさま、ありがとうございました。緊急事態宣言の延長を受け、第2回・3回講座もオンラインでの開催となります。今週末の声優うえだ星子さんのご朗読はぜひ生で、あの迫力をこそ感じていただきたかったのですが残念無念…(うえださんブログでのご周知ありがとうございます!)。初回の館長のお話は秋聲の出世作『黴』を中心に、秋聲作品に対する漱石の批判から川端康成による度を超した讃美の振り幅について考察するとともに、現代における秋聲作品の受容と批評までを視野に入れた縦にも横にも深く広く踏み込む内容でした。今からちょうど50年前、東京都近代文学博物館で開催された生誕百年記念「独歩花袋秋声三人展」のパンフレットを掲げながら、独歩・花袋・秋聲の明治4年生まれの自然主義作家たち(独歩は諸説あり…旧暦では一歳下にあたる藤村も交えつつ…)のうち「最も地味な秋聲」との発声に始まり、最終的に「秋聲文学を世界に開くためにわれわれは活動してゆく」と生誕150年にふさわしい力強くワールドワイドな宣言に終わり、隣で聞いていながらグッと拳を握りましてございます(とりいそぎましてスウェーデンのアンカルクローナさん、今後ともよろしくお願いいたします…!) また中で川端康成の秋聲評(ex.「私の最も敬ふ人」「小説の名人」「完璧の古典」「最高の小説」「最高のものに通じた作家」「天才」「神品」「名匠」「源氏にはじまって」云々…)をご紹介しながら、「これほど秋聲を高く評価した川端というのは一体何者か……」と一瞬、聴講者や周囲のスタッフの存在もわすれるほど深い問いの淵に片足を踏みいれてしまったようにも見えた館長。アッあぶない、館長まって 、戻って来て…!! とハラハラ願わずにいられないほどの底知れぬ川端の深淵が確かにそこに見えました。「秋聲を繋ぐ人々」展のリベンジとともに、今後の課題とさせていただきたく存じます。 終了後、「君、『黴』を舞台化しなよ。面白くなるよ」「いや、『赤い花』で手一杯ですね。館長、お願いします」とのライトな押し付け合いがございました。生誕200年のときにどうか。どなたか。 |
葱のある風景 |
| 2021.6.1 |
 本日解禁いたしました新グッズ通販、おかげさまでたくさんのお申し込みを賜り、現在グッズ担当者がおおわらわで対応にあたっております。ありがとうございます。 本日解禁いたしました新グッズ通販、おかげさまでたくさんのお申し込みを賜り、現在グッズ担当者がおおわらわで対応にあたっております。ありがとうございます。HPに新たに掲載するにあたり、写真のバリエーションを考えながら、お色のバランスも見つつ白トート(厳密には生成り)には葱、黒トートにはフランスパンを入れてみました。だいたいのサイズ感をお伝えするとともに、秋聲=生活感の演出をば。記念品ではありますが、生活に密着したものとして親しくお使いいただけましたら幸いです。 さて、葱といえば芥川龍之介の短編「葱」(大正9年)。芸術に関心高く、まるで夢二の絵から抜け出してきたようなカフェの女給のお君さん、ある夜若き芸術家の田中君とデートに出かけます。美しい町並みを歩きながら壮大な恋愛の歓喜と幸福に酔いしれる二人… 「その内にふとお君さんが気がつくと、二人は何時(いつ)か横町を曲つたと見へて、路幅の狭い町を歩いてゐる。さうしてその町の右側に、一軒の小さな八百屋があつて、明く瓦斯の燃えた下に、大根、人参、漬け菜、葱、小蕪、慈姑(くわい)、牛蒡、八つ頭、小松菜、独活、蓮根、里芋、林檎、蜜柑の類が堆(うずたか)く店に積み上げてある。その八百屋の前を通つた時、お君さんの視線は何かの拍子に、葱の山の中に立つてゐる、竹に燭奴(つけぎ)を挟んだ札の上へ落ちた。札には墨黒々と下手な字で、「一束四銭」と書いてある。あらゆる物価が暴騰した今日、一束四銭と云ふ葱は滅多にない。この至廉な札を眺めると共に、今まで恋愛と芸術とに酔つてゐた、お君さんの幸福な心の中には、其処に潜んでゐた実生活が、突如としてその惰眠から覚めた。 (中略) 『あれを二束下さいな。』」 本作について、お君さんのモデルと言われた宇野千代は、「ラヴシーンと言ふほどではなくても、そんなときに、ふいに、世帯じみた葱などが眼につくのかと思ふと、男は興醒めしました。つまり、さう言ふ話なのです。(中略)のちにこの話を聞いた私は、如何(いか)にも、そんなときに、走って葱など買ひに行きさうな自分のことを、をかしく、またちょっぴり可哀そうにも思ったものでした。」と語っています(『私の文学的回想記』)。 ……ぜんたい葱に罪はなし。生活に不可欠、ただそれだけなのです。 |
生誕150年記念協力展示⑤ |
| 2021.5.31 |
先日、秋聲生誕150年記念ロゴマークとともにオリジナル新グッズの発表もさせていただきました。いよいよ明日6月1日(火)午前零時よりお受け付けを開始いたします。ハイテクなカート式などでなく、普通にメールいただく形の通販体勢で恐縮です。職員が出勤ののち順次確認してまいりますが、もし万が一、エッうそ、メール殺到…!? みたいな事態になっておりましたら、ご返信までに少々お時間いただいてしまうかもしれません。極めて少人数で運営しておりますので、ご迷惑をおかけいたしますがどうか長い目でもってお待ちいただけましたら幸いです。 さて、トートなど布繋がりで本日は風呂敷のお話。以前から同じグッズページでご紹介をしておりますとおり、秋聲の代表作『縮図』モデルの風呂敷(大・小)も当館でお取り扱いをいたしております。こちらは館のオリジナルグッズでなく、ロカワークショップさんという秋聲でグッズつくってみたよ☆
との、前代未聞の奇特な制作会社さんによるご企画で、かねてより当館にて受託販売をさせていただいているもの(大は大型犬、小は小型犬を包めるくらいのサイズ。小で中型犬を包もうとするとけっこうはみ出ます→)。 さて、トートなど布繋がりで本日は風呂敷のお話。以前から同じグッズページでご紹介をしておりますとおり、秋聲の代表作『縮図』モデルの風呂敷(大・小)も当館でお取り扱いをいたしております。こちらは館のオリジナルグッズでなく、ロカワークショップさんという秋聲でグッズつくってみたよ☆
との、前代未聞の奇特な制作会社さんによるご企画で、かねてより当館にて受託販売をさせていただいているもの(大は大型犬、小は小型犬を包めるくらいのサイズ。小で中型犬を包もうとするとけっこうはみ出ます→)。と、その秋聲風呂敷を、当館と同じ財団仲間の金沢くらしの博物館さんの次回企画展「風呂敷の魅力」において展示していただけることになりました! ワ~~風呂敷1点だけだけど、「協力展示」って言っちゃう~~! 同じ財団仲間の館だから無理言ってねじこんじゃう~! 勢い大事~~!! というわけで、その展示準備のため、くらしさまが商店さんなどに向けてオリジナル風呂敷募集中! と広告を出されていたのを目ざとく見つけ、「ウチにも風呂敷あるんですけどもいかがか!?」と詰め寄りましたら「あっそうでしたね! ぜひぜひ!」と快くお引き受けをいただきました。「えっでも1点なのに協力展示とかかえって申し訳ないんですけど…」と恐縮される人の好いくらしさまに、「1点でもいいから」というコンセプトです、ぜひ入れさせてッッ!! とさらに血走った目で鼻先1mmの距離から詰め寄りまして、無理矢理そのお名前を連ねさせていただくことに成功いたしました。 あらいろんな風呂敷が見てみたいわ、と思ってくらしさまに出向かれ、そこに秋聲が待ち受けているだなんて誰が予想されるでしょうか。あらゆる角度から思いもかけない出会いを提供…それが協力展示の狙いのひとつでもございます。 すなわちどこで何をしていても秋聲生誕150年いうことを忘れないでね? いや、忘れさせませんよ?? というとんだ粘着気質な企画なのです。 |
生誕150年記念オリジナルロゴ |
| 2021.5.28 |
| 昨日、地元の「北國新聞」さんに取りあげていただきました。このたび秋聲生誕150年記念のオリジナルロゴマークが発表となりました! ハイ、ドーーーーン!↓ イエァーーーー! 館のテンションと館外のみなさまのテンションとの齟齬ーーーーー! 気にしません負けません(全国の秋聲会のみんな…! ついてきて…!!)  明治・大正・昭和の三代を常に第一線で活躍し続けた作家・徳田秋聲の文業を今も育ち続ける大樹になぞらえたデザインです(←クリックで拡大)。葉を成す部分は秋聲作品のタイトルの数々。その言の葉が豊かに繁る大樹の陰で、涼むなり読書するなり物思いに耽るなり柿を食うなり鐘が鳴るなり…人々に思い思いの憩いの場を提供するとともに、誰に対しても分け隔てなく多くの作家たちが彼のもとに集い、文壇の「大家」として広く慕われた秋聲の人物像をも象徴します。中央の太い幹には内部に静かに水を巡らし、この現代にも秋聲文学の根を張る力強さを持つ大樹……また全体を、秋聲の上品でモダンな人柄を表す雰囲気でまとめていただきました。 明治・大正・昭和の三代を常に第一線で活躍し続けた作家・徳田秋聲の文業を今も育ち続ける大樹になぞらえたデザインです(←クリックで拡大)。葉を成す部分は秋聲作品のタイトルの数々。その言の葉が豊かに繁る大樹の陰で、涼むなり読書するなり物思いに耽るなり柿を食うなり鐘が鳴るなり…人々に思い思いの憩いの場を提供するとともに、誰に対しても分け隔てなく多くの作家たちが彼のもとに集い、文壇の「大家」として広く慕われた秋聲の人物像をも象徴します。中央の太い幹には内部に静かに水を巡らし、この現代にも秋聲文学の根を張る力強さを持つ大樹……また全体を、秋聲の上品でモダンな人柄を表す雰囲気でまとめていただきました。デザイナーは当館の文庫や企画展ビジュアルのいくつか、また黴クリアファイルをはじめとするオリジナルグッズデザインでお馴染みの南知子さん。当館が最も厚く信頼を寄せるデザイナーさんでございます。今後、いろいろな催事のビジュアルなどにこちらを使ってゆくわけですが、それはそれとして持ち運びたいよねええ。四六時中身につけて眺めていたいよねええ。との湧き上がる物欲から、あわせて南さんに当ロゴを用いたトートバッグおよびクリアファイルをご制作いただきました! 詳細につきましてはグッズページからご確認ください。新聞でも報じられましたとおり、これらは6月1日(火)より当HPから通販にて先行発売いたします。お買い上げくださったみなさまとホラミテかわいーですよねぇ! とミュージアムショップ前でキャッキャはしゃぎたいのはやまやまですが、あいにく6月13日(日)まで臨時休館中につき、待ちきれなくなった記念館一味によるちょっとしたフライングです。 たいした数量もなく恐縮ですが(すみません、た、たくさんつくるおかねがなくて…)限定品につきご興味おありでしたらお早めにお買い求めいただけましたら幸いです。通販ではとりいそぎの50部、6月14日以降、再開館のおり正式にミュージアムショップにお目見えいたします! |
作家の眼 |
| 2021.5.26 |
今週末29日(土)の上田館長によります文京アカデミア講座第1回は、東京都の緊急事態宣言を受け対面からオンラインに変更になりました。館ではネット環境に自信がないため、急遽市役所の一室をお借りして接続リハーサルをおこなった昨日。第2回3回講座はまだ対面かオンラインか未定のため、東京と金沢の状況を睨みながら、あらゆる可能性を視野に入れつつシミュレーション中です。受講生のみなさまにはご迷惑をおかけいたしますが、もうしばらくお時間くださいますようお願い申し上げます。 パソコンから配信する際には画面を見てはならず、パソコン内臓のカメラを見るべし、と以前テレビ番組で配信時の注意事項が述べられていました。たしかにどうしたってカメラでなく、映っている相手さまのお顔を見てお話ししてしまうなァということで、リハーサルではカメラ横にキャラクターのお顔を貼って「ここ見て!!」と記してみたのですが、始まってしまえばなんのことはなし、画面の中の相手さまのお顔をしっかり見てお話ししている記念館一味なり…。これはまだまだ要練習です。 パソコンから配信する際には画面を見てはならず、パソコン内臓のカメラを見るべし、と以前テレビ番組で配信時の注意事項が述べられていました。たしかにどうしたってカメラでなく、映っている相手さまのお顔を見てお話ししてしまうなァということで、リハーサルではカメラ横にキャラクターのお顔を貼って「ここ見て!!」と記してみたのですが、始まってしまえばなんのことはなし、画面の中の相手さまのお顔をしっかり見てお話ししている記念館一味なり…。これはまだまだ要練習です。相手のお顔をじっくり見るといえば川端康成。あの大きな眼で無言のままジロジロ相手のお顔を見ること三十分…初対面の編集者を泣かせたとの伝説のあるあの御方です。秋聲の遠縁にあたる劇作家・岡栄一郎の娘富久子さんは康成の推薦で文芸春秋新社に入社したそうで、彼女の回想もまたその題からして「羞(は)にかみについて―川端康成氏の眼―」。オーバーにくるまっていても、康成の前に立つとその中の肉体まで透かし見られるかのような〝好色を沈めて好色を越えた眼〟、「すきとおるように美しい芸術」を生み出す〝限りなく虚しく美しい眼〟について綴られています(『作家の横顔』)。 「川端さんにもよくお会いしてね。あのギョロッとした眼でじっとこちらをご覧になって…」とは秋聲令孫・徳田名誉館長のお言葉です(ただお人柄はとてもお優しかったそう)。前回記事で企画展の差し替えをご案内いたしましたが、徳田家に伝わる康成制作・秋聲文学碑建設記念のお湯呑みはおかげさまで当館で保管させていただいておりますので、書斎かどこか別コーナーに展示させていただく予定です。昨年、いつもお世話になっている川端康成文学館さんと交わした大切なお約束につき。 |
近況報告とお詫び |
| 2021.5.24 |
| 派手に寸々語をおさぼりいたしまして申し訳ございません。一週間前の爆弾発表に心身がついてゆかれず、この一週間土に指で「いわなみぶんこ」と書いては消し…みたいなふわふわとした日々を送っておりました。一週間経ちようやく気持ちが落ち着きまして、しかし一週間も経たらばあれはもしや夢ではなかったろうか、と急に不安になって、その後何度も岩波書店さんからのメールを見返しております。そんな一週間です。 この11月、秋聲生誕150年という記念すべき今年の来る11月、岩波文庫『あらくれ・新世帯』(新版)、『縮図』(増版)がこの世に生まれ出る…これ以上おめでたいことがあるでしょうか? 当館の文庫の存在はしばらく忘れていただいてかまいませんので、何せこちらを是が非でもご購入いただきたく、切に切にお願いを申し上げます。この出版不況のなか、ご担当者さまが「現代の読者にこそ」と推してくださったと聞きました。どうかどうか、こればかりはご購読をお願いいたします。秋聲文学は需要があるのだと、どうか世に見せつけてやってください。ここで売れなければ秋聲文学は本当に失われてしまうかもしれません。記念館でちまちまと出している文庫だけでは限界がありますし、記念館の力だけではとてもとても足りません。秋聲の本ないのかな? あれっどこにも売ってないんだけど! と一度でも思われたことのある方、この機に何卒何卒よろしくお願いいたします。  記念館は残念ながら現在臨時休館中。4月のイベントを経て、椅子をがっつり拭き掃除したついでに強制相席秋聲もリニューアルいたしましたのに、なかなか一緒にすわってくださるおともだちが現れませんね。さびしいですね。 記念館は残念ながら現在臨時休館中。4月のイベントを経て、椅子をがっつり拭き掃除したついでに強制相席秋聲もリニューアルいたしましたのに、なかなか一緒にすわってくださるおともだちが現れませんね。さびしいですね。土に指でふわふわ文字を書きながら、正午にはブラインドの閉まったままの2階サロンでお座り秋聲と静かに語らい、そして午後には土に汚れた同じ指でもって各所にお詫びメールを打つ、そんな一週間でもありました。実は次回8月から予定しておりました生誕150年記念企画展「秋聲を繋ぐ人々」――このコロナ禍において川端康成や広津和郎、野口冨士男ら、秋聲作品を後世に繋いでくださった人々の資料借用の目途が立たず、いったん見送りとさせていただくこととなりました。以前に予告をしてしまった手前、本当に申し訳なく存じております。また機を改めて、ということで何卒お許しください。その代わりの展示内容につきましては、また後日ご案内を申し上げます。 |
| 朗報中の朗報 |
| 2021.5.18 |
| 今年11月 岩波文庫 『あらくれ・新世帯』(新版) 『縮図』(重版) 刊 行 決 定 ………!!!! 胸がいっぱいで今は何も言葉が出ません。 この感激が形をとるまで少しだけお時間ください。 アーーーーーー秋聲文学の夜明けぜよーーー………! |
まめくれ |
| 2021.5.16 |
先日例月の展示解説を開催いたしましたおり、ご参加くださったお客さまからとても可愛らしいプレゼントを頂戴いたしました。なんと縦4cm・横3cmほどの手作り豆本『あらくれ』でございます…! しかも函・チャリチャリ紙付きの本体に加え、ミジンコほどの文字サイズで肝心の本文もしっかり印刷、さらに巻末の広告から奥付の検印まで余すところなく忠実に再現されているというこだわりぶり。検印にいたりましてはその直径わずか5mmですから、もはや職人技と言うほかありません。「祝
150周年」と記された美しい台紙のうえに包装された2冊の『あらくれ』…ん? 2冊? 保存用と展示用? と思いきや、ご制作者さま曰く「文アルさんの秋声くんサイズになっています」とのこと。アッうちに秋声くんぬいぐるみが2人いることをご存じで…!? 思えば昨 年11月の文アル茶会に学芸員とともに出演させていたのでした。振り返って事務室の棚のうえにおすわりさせた秋声くんの座高はおよそ15cm。そのふたりに持たせてちょうど良いサイズに仕上げてくださったというわけです。お気遣いありがとうございます。おかげさまで可愛い『あらくれ』を取り合って喧嘩にならずに済みました(なお秋声くんたちは展示室にはお出ししておりません。すみません…)。 年11月の文アル茶会に学芸員とともに出演させていたのでした。振り返って事務室の棚のうえにおすわりさせた秋声くんの座高はおよそ15cm。そのふたりに持たせてちょうど良いサイズに仕上げてくださったというわけです。お気遣いありがとうございます。おかげさまで可愛い『あらくれ』を取り合って喧嘩にならずに済みました(なお秋声くんたちは展示室にはお出ししておりません。すみません…)。大正4年、新潮社刊の『あらくれ』自体がもともと小型で、ざっくりB6くらいでしょうか。着物の袂に入るほどのこうした携帯に便利なサイズの本は「袖珍本(しゅうちんぼん)」と呼ばれ、現在の文庫本のはしりとも言われています。初版はさすがにちょいとお高めですが、日本近代文学館から復刻版が出ていますのでそちらならば当時の雰囲気そのままに古書店さんなどで比較的安価にお求めいただけるかと存じます。 そういえば今年の7月に成瀬巳喜男監督映画『あらくれ』がついにDVDになるそうですね! 臨時休館で館の活動が制限されるいっぽう、こうした動きは本当にありがたいことです。今後いろいろな販売場所で「新発売」とかいうコピーを見るたび、お店の人の目を盗んでそのフレーズの前に「生誕150年を記念して」と勝手に書き足してまわることといたします。 |
| 生誕150年記念協力展示④ |
| 2021.5.12 |
 東京から岡山へ飛び、岡山から金沢に帰って再び東京へ! おかげさまで竹久夢二美術館さん同様、秋聲第二の故郷・文京区は本郷、区立真砂中央図書館さんにて、生誕150年記念協力展示の第四弾がはじまりました! ここへきて美術館、文学館とも異なる図書館さんのご参入です。幅広い世代のいろいろな利用者さんの集まるのが図書館さんですからものごとを広く周知するにはもってこい、これは非常にありがたいこと…! 厳密には展示というよりご所蔵の秋聲関連図書を集めた特設コーナーをつくっていただいた次第です。当館のオリジナル文庫もあわせてご紹介いただくほか(本日より休館ですが通販はご利用いただけます)、なんと当館図録にリーフレットまで…お心遣いに感謝申し上げます。エッへへ、一棚まるごと秋聲のしゅの字でひとりじめだーーーい! 東京から岡山へ飛び、岡山から金沢に帰って再び東京へ! おかげさまで竹久夢二美術館さん同様、秋聲第二の故郷・文京区は本郷、区立真砂中央図書館さんにて、生誕150年記念協力展示の第四弾がはじまりました! ここへきて美術館、文学館とも異なる図書館さんのご参入です。幅広い世代のいろいろな利用者さんの集まるのが図書館さんですからものごとを広く周知するにはもってこい、これは非常にありがたいこと…! 厳密には展示というよりご所蔵の秋聲関連図書を集めた特設コーナーをつくっていただいた次第です。当館のオリジナル文庫もあわせてご紹介いただくほか(本日より休館ですが通販はご利用いただけます)、なんと当館図録にリーフレットまで…お心遣いに感謝申し上げます。エッへへ、一棚まるごと秋聲のしゅの字でひとりじめだーーーい!これまで書店さんでも図書館さんでも秋聲の著作を探すのに難儀されたかもしれないみなみなさま、ここから一ヶ月ほどは探すお手間が格段に省けるってもんですぜ…! 目立ちすぎてかえって見逃しちゃうことだけご注意ください。しゅ、秋聲が最前線に配架されることだってあるんだから…! これを機に、改めて文京区に40年を暮らした秋聲の世界に触れていただけましたら幸いです。真砂中央図書館さん、お忙しいなか、ご協力ほんとうにありがとうございました。 また6月24日(木)には、真砂中央図書館さんとご近所の文京区民センターにて、シビックシアター☆トークショーと題しまして秋聲原作映画『縮図』の上映もございます。秋聲の生涯最後にして未完の長編小説を新藤兼人監督、乙羽信子主演で映像化したこの作品。同じ文京区内の白山が舞台になっていることもあり、ぜひ同地でこそ上映いただきたかった名作です。お申し込み方法等、詳しくはこちらからご確認ください。いまのところ上映後に学芸員がトークにうかがう段取りになってはいるのですが、いかんせん穏やかならぬこの状況…解説どころか映画の上映自体も見合わせになるかもしれません。そのあたりはっきりとご案内できず恐縮ですが、最悪すべて中止になってしまった場合には、真砂中央図書館さんにお寄りになって、秋聲特設コーナーのなかでも一際輝く黄色い表紙をお取りになって…おうちでじっくりお読みになって… |
臨時休館のお知らせ |
| 2021.5.11 |
| 残念ながら臨時休館のお知らせです。県下における「石川緊急事態宣言」の発令を受け、明日5月12日(水)~31日(月)まで休館することとなりました。急なお知らせとなり申し訳ございません。5月15日(土)に予定されておりました地元有志による「女川祭」も延期となりましたので、これにともない当日の当館の夜間開館も中止。 また5月22日(土)にスタートを切る予定でありました生誕150年記念連続講座の第1回「師・尾崎紅葉と秋聲」も開催延期といたします。おそらく秋頃に改めて…ということになろうかと思われますが、決定のおりには再度ご案内をさせていただくほか、一度お申し込みくださったみなさまには優先的にご予約いただけるよう手配いたします。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程お願い申し上げます。 繰り上げまして連続講座の第1回は7月18日(日)、泉鏡花記念館・秋山館長さまによる某K花さん講座ということになりそうです。こちらもまた先日サブタイトルをいただきまして、正式タイトルは「兄弟子・泉鏡花と秋聲―俳句で競う―」。因縁の兄弟弟子ですからこれまでにも何かと比較して語られてきたふたりではありますが、こちらはちょっと珍しい切り口なのではないでしょうか。7月には安心して開催できるはず! と信じて粛々と準備するほかありません。会場となる金沢ふるさと偉人館さんには、秋聲・某K花さん、犀星さんの金沢三文豪コーナーもございますので、無事開催・開館の暁にはどうか忘れずにご観覧ください。  先日お客さまからもご指摘いただきましたとおり、現在展示している秋聲愛用のティーカップとほとんど同じ柿の柄のお湯呑みが某K花記念館さんに展示されています。ふたりは「何等抵触する筈のない、異なった二つの存在」であるとは秋聲の言ながら(「和解」より)、そうは言ってもどこか似たところがあり、しかしここぞというところで決定的に正反対を向く…みたいなところがあるような気がいたします。と、そんなところを秋聲がすでに説明してくれていましたね。「生温い友情が、或る因縁で繋がっていて、それから双方の方嚮に、年々開きが出て来たところで、全然(まるで)相背反してしまったものが、今度は反動で、ぴったり一つの点に合致したように――」、とはいえそれは外面的なものであり、妥協的なものでもあり、ともすると一時的なものであり…ハァややこしや~ややこしや~…こじれたふたりの人間性・関係性・文学性を繙く糸口が、7月18日に見えてくるはず。7月ならばまだまだ柿も青いころです。 先日お客さまからもご指摘いただきましたとおり、現在展示している秋聲愛用のティーカップとほとんど同じ柿の柄のお湯呑みが某K花記念館さんに展示されています。ふたりは「何等抵触する筈のない、異なった二つの存在」であるとは秋聲の言ながら(「和解」より)、そうは言ってもどこか似たところがあり、しかしここぞというところで決定的に正反対を向く…みたいなところがあるような気がいたします。と、そんなところを秋聲がすでに説明してくれていましたね。「生温い友情が、或る因縁で繋がっていて、それから双方の方嚮に、年々開きが出て来たところで、全然(まるで)相背反してしまったものが、今度は反動で、ぴったり一つの点に合致したように――」、とはいえそれは外面的なものであり、妥協的なものでもあり、ともすると一時的なものであり…ハァややこしや~ややこしや~…こじれたふたりの人間性・関係性・文学性を繙く糸口が、7月18日に見えてくるはず。7月ならばまだまだ柿も青いころです。 |
| 「新金沢小景」第857景 |
| 2021.5.9 |
 先日、テレビ金沢さんの番組「新金沢小景」撮影クルーのみなさまがお越しくださり、現在開催中の生誕150年企画展「秋聲の家―徳田家所蔵品展」をご取材いただきました! 五木寛之先生のナレーションでお馴染みのあのご長寿番組です。今ほど番組のことをすこし調べにゆきましたら平成15年から放送されているそうで、当館は平成17年開館で今年17年目ですからちょっぴり先輩! 当館が1年生のときの3年生! だからなに、ということに敢えて触れにゆくのがこの寸々語でございます。新金沢小景先輩、秋聲をとりあげてくださりありがとうございます。 先日、テレビ金沢さんの番組「新金沢小景」撮影クルーのみなさまがお越しくださり、現在開催中の生誕150年企画展「秋聲の家―徳田家所蔵品展」をご取材いただきました! 五木寛之先生のナレーションでお馴染みのあのご長寿番組です。今ほど番組のことをすこし調べにゆきましたら平成15年から放送されているそうで、当館は平成17年開館で今年17年目ですからちょっぴり先輩! 当館が1年生のときの3年生! だからなに、ということに敢えて触れにゆくのがこの寸々語でございます。新金沢小景先輩、秋聲をとりあげてくださりありがとうございます。しかも当館の企画展のみならず、第857景ともなる今回のテーマは「生誕150年記念協力展示」だそうで、現在開催中の竹久夢二美術館さん、吉備路文学館さん、金沢ふるさと偉人館さんによる秋聲展示もあわせてご紹介くださるとか(予定)。なかなか県を跨いでの移動の難しい昨今、すぐすぐ金沢に来られない方々にも最寄りの地域で秋聲に触れていただければ…というのがこの協力展示を通じた願いのひとつでもあったのですが、逆に言うと各館のみなさまのご厚情により実現したせっかくの協力展示を、うわぁ~ん金沢から観にゆかれないよ~~~という秋聲会金沢本部のみなみなさまに向けてはとても有り難いご企画でした。まだ記念館でもお出ししていない今後の展示予定にも触れられるかもしれません。下記の日程で放送予定ですので、ぜひご覧くださいませ。 テレビ金沢「新金沢小景」 令和3年5月14日(金)18時30分頃~同40分頃 いつもそうは言っても急遽予定が変わるかもしれない…何か別の番組に差し替わるかもしれない…だって秋聲だもの…! と謂われのないネガティブから事前にご案内をいたしかねるところ、今回ばかりは是が非でもご放送いただきたい! との思いから強い気持ちで予告をさせていただきました。 なお、ついでのご案内となり恐縮ですが、来月のMROラジオさん「あさダッシュ!」への学芸員の出演は6月9日(水)10時頃より。いつもは当日30分前に控え室入りしてこれが現実であることを確認してからようやくそっと呟くところ、つ、強い気持ちで一ヶ月前にお伝えしてみました…! |
「生誕150周年 徳田秋聲の愛した音楽」 |
| 2021.5.6 |
 感動に咽び泣くこと三日三晩…すっかりご報告が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。去る3日(月・祝)、石川県立音楽堂交流ホールにて秋聲生誕150年記念コンサートが無事に開催されました! かの「風と緑の楽都音楽祭2021」の一環として、プログラムやチケット等に印刷された「秋聲生誕150年記念」の文字を何度も何度も見返しては胸を熱くする日々でした。当日午前中には例月のMROラジオ「あさダッシュ!」さんへの出演があり、そちらでも「今日! 午後からです!」と熱を入れてお話ししてきた結果、熱量と鼻息ばかりがマイクをボーボボ言わせ、肝心の出演者さまや演奏予定の曲目をなんにもご紹介してこなかったように思うのですがハテどうであったか……ボーボボに乗せ、ベートーヴェンの「月光」だけはなんとかお伝えできていたような……ちょっと興奮でもはや記憶が…… 感動に咽び泣くこと三日三晩…すっかりご報告が遅くなりましたことをお詫び申し上げます。去る3日(月・祝)、石川県立音楽堂交流ホールにて秋聲生誕150年記念コンサートが無事に開催されました! かの「風と緑の楽都音楽祭2021」の一環として、プログラムやチケット等に印刷された「秋聲生誕150年記念」の文字を何度も何度も見返しては胸を熱くする日々でした。当日午前中には例月のMROラジオ「あさダッシュ!」さんへの出演があり、そちらでも「今日! 午後からです!」と熱を入れてお話ししてきた結果、熱量と鼻息ばかりがマイクをボーボボ言わせ、肝心の出演者さまや演奏予定の曲目をなんにもご紹介してこなかったように思うのですがハテどうであったか……ボーボボに乗せ、ベートーヴェンの「月光」だけはなんとかお伝えできていたような……ちょっと興奮でもはや記憶が……この重厚なる「月光」から始まる秋聲コンサート、演奏の合間合間に北陸朝日放送の上野雅美アナウンサーによる朗読も交えていただきました。長篇小説『誘惑』『蘇生』『赤い花』、そして随筆「レコード音楽」からベートーヴェン、クライスラー、モーツァルト、ビゼー、ドビュッシーなど聞き慣れた作曲家たちが続々登場。選曲の所以がおわかりいただけたことと存じます。当日は後ろのほうから見ておりましたが、おかげさまの満・席…! ソーシャルディスタンスの必要がなければ、ほんとうはこの3倍の方に聴いていただけたかもしれないナ…と切なくもなりながら、ラジオでもお話しいたしましたとおり、そもそも秋聲に馴染みのない方にはあまりピンと来ない組み合わせかもしれない秋聲×音楽。記念館でも小さな規模のコンサートは何度か開催してまいりましたけれども、今回この生誕150年というまたとない機会に記念館を飛び出し、音楽好きの方々の集まる大きなホールにて、へぇ意外とそこ親和性高いんだァ~と広く知っていただくということが念願のひとつでもございましたので、これを皮切りとして今後とも秋聲×音楽イベント、続々と開催されることになりましたらば嬉しい限りです。 たくさんの方にかかわっていただき、秋聲の語る、秋聲の好きな音楽ばかりを集めて開催されたコンサート…こんなに贅沢なお誕生会は他にありません。ご準備くださったみなさま、ご演奏くださったみなさま、ご参加くださったみなさま、本当にありがとうございました。抱き合わせでもおまけでもなく、「正真正銘、あなたのためのコンサートですよ!!」と痛いくらいに拍手をしながら心の中で叫んだ言葉は秋聲の耳に届いたでしょうか。 |
| オリンピック座談会 |
| 2021.4.30 |
昨日の〝国宝〟記事の件、いつかの加能作次郎展の際にその初出誌を入手したように記憶します。もちろん風野先生のご著書にもこのくだりが引用されているのですが、念のためその前後も確認せんとて昨日、当該の「文芸春秋」を改めて眺めておりましたらば、誌面の後ろのほうに「オリンピック座談会」という記事の掲載がありました。あらタイムリー! と思いつつ、しかしよく見るとこちらはどうやらあのオリンピックのことでなく「極東オリンピック」というやや小さめの規模の別の大会のことのよう。出席者は平沼亮三や加賀一郎、高石勝男らのスポーツ関係者で、巻末の編集後記には「本号の発売後いくばくもなくして神宮外苑に開かれる極東オリンピツク」とあり、こちら昭和5年6月1日発行号ですからチャカチャカッとウィキペディア情報で恐縮ですが、この年5月末に東京で開催されたという第9回大会を指すのでしょうか。 秋聲が極東オリンピックに触れた文章はすぐすぐ思いつきませんでしたけれども、いわゆるあの〝オリンピック〟に言及した作品といえば長篇小説「心の勝利」。中で登場人物たちが静岡県の川奈ホテルに新婚旅行にやってきて、ホテルの豪華な建物のサロンでその窓の先を見詰め〝海辺のゴルフ・リンク〟の噂をする場面がございます。ゴルフはやったというほどやってないけどアレ翌朝疲れるんだよねーなどと言いながら、「尤も此処は観光客のための設備だらうから、ホテルもリンクも僕らには贅沢すぎて……何でも今の処ずつと赤字だといふ話だ。金持の道楽だからそれもいゝさ。こんな処泊るの少し癪だけれど、これもオリムピツクの用意だから、一つくらゐあつても可いね。」と語る新郎・木山――本作は昭和13年9月に連載が開始されていますから、ここに言う〝オリムピツク〟は昭和15年に予定されていた東京オリンピックを指しています。しかしこのころ勃発した日中戦争の影響等で、結局日本は開催権を返上、大会の開催は実現に至らず幻のオリンピックとなりました。 秋聲が極東オリンピックに触れた文章はすぐすぐ思いつきませんでしたけれども、いわゆるあの〝オリンピック〟に言及した作品といえば長篇小説「心の勝利」。中で登場人物たちが静岡県の川奈ホテルに新婚旅行にやってきて、ホテルの豪華な建物のサロンでその窓の先を見詰め〝海辺のゴルフ・リンク〟の噂をする場面がございます。ゴルフはやったというほどやってないけどアレ翌朝疲れるんだよねーなどと言いながら、「尤も此処は観光客のための設備だらうから、ホテルもリンクも僕らには贅沢すぎて……何でも今の処ずつと赤字だといふ話だ。金持の道楽だからそれもいゝさ。こんな処泊るの少し癪だけれど、これもオリムピツクの用意だから、一つくらゐあつても可いね。」と語る新郎・木山――本作は昭和13年9月に連載が開始されていますから、ここに言う〝オリムピツク〟は昭和15年に予定されていた東京オリンピックを指しています。しかしこのころ勃発した日中戦争の影響等で、結局日本は開催権を返上、大会の開催は実現に至らず幻のオリンピックとなりました。さらにこの〝オリムピツクの用意だから~〟のくだりは昭和13年3月発表の秋聲の随筆「灰皿」にも出てまいります。ここで秋聲は末娘の百子さんと〝広大なゴルフ・リンクにある〟〝川奈国際観光ホテル〟に遊びにきて、その〝サルンといふかサンルウム〟の豪壮なさまに目を驚かし…その後、食堂へゆき意地汚くたくさんの料理を詰め込んだせいでウフーとなりながら、連れ合いの小唄の師匠が「無論赤字に決まつてゐますよ。でもこんなものも一つや二つあつて可いでせうね。オリムピツクも近いことですから。」と呟くのを聞く…なるほどなるほど、実体験がこう活きる。 |
〝一種の国宝〟 |
| 2021.4.29 |
| 本日は島清こと島田清次郎のご命日です。石川県・現白山市の出身で、明治32年2月26日生まれの昭和5年4月29日没(享年31歳)。文壇の問題児として知られる28歳年下の清次郎をブーブー言いながらもよく世話していた秋聲ですが、清次郎からみる秋聲評の一端が同じ石川県は現羽咋郡出身の作家・加能作次郎の文章に表れてまいります。 清次郎の訃報を受け執筆された「島田清次郎君のこと」(「文芸春秋」昭和5年6月号)に曰く、大出世作『地上』発表以前の清次郎は「極く真面目な、寧ろ樸訥(ぼくとつ)愛すべき人懐つこい好青年」であると同時に、口を開けば「当時文壇の流行作家達を、殆(ほとん)ど一人残らず片つ端からこき下した」という…またその評が「中々奇抜な機智に富んだもの」で「而(しか)も頗(すこぶ)る肯綮(こうけい)に当つていた(=要点をついていた)」。そんな清次郎に、作次郎は「じゃあ秋聲さんの作品は?」とふたりにとって郷里の大先輩にあたる秋聲について問いかけます。 「すると彼はにやにや笑を浮かべながら、『徳田さんのものは、もう謂はゞ一種の国宝みたいなものですからあの儘そつとして置いた方がいゝでせう。』と巧みに外らして了(しま)つた。これは決して皮肉に言つたのではなく、寧ろ賞讃の意味で、同時に彼の如才なき一面をあらはしたものだつた。けだし彼は徳田さんの芸術に心服してゐたばかりでなく、例の『地上』の原稿の閲読を乞うて居た折柄でもあつたのだ。」 …とのことです。こ、国宝…! うまく話を逸らしただけにしても国宝…!! そういえば、秋聲生前に刊行された非凡閣版『秋聲全集』の月報で秋聲作品を「国宝級」と述べ、ホラこの全集を買えば「国宝を私蔵し得る機会だヨ!」との推薦文を寄稿してく  れたのは秋聲と仲良しの作家・上司小剣でした。二人も言っているのでもう今後「国宝」と言って良いことといたします。当時、秋聲が持ち込まれた『地上』原稿に対しどんな働きをしたかしなかったかは不明ですが、間もなくして大正8年6月、同作は新潮社から刊行され空前のベストセラーとなりました。作次郎はその後の彼の作家生活にも触れ、〝誰にも愛されない男〟清次郎の悲劇をここに語っています。それこれ含めて詳しくお知りになりたい方には、風野春樹先生著『島田清次郎 誰にも愛されなかった男』(本の雑誌社)をおすすめいたします。 れたのは秋聲と仲良しの作家・上司小剣でした。二人も言っているのでもう今後「国宝」と言って良いことといたします。当時、秋聲が持ち込まれた『地上』原稿に対しどんな働きをしたかしなかったかは不明ですが、間もなくして大正8年6月、同作は新潮社から刊行され空前のベストセラーとなりました。作次郎はその後の彼の作家生活にも触れ、〝誰にも愛されない男〟清次郎の悲劇をここに語っています。それこれ含めて詳しくお知りになりたい方には、風野春樹先生著『島田清次郎 誰にも愛されなかった男』(本の雑誌社)をおすすめいたします。そうか国宝か…、国宝……こくほう…… |
| 青くて渋い柿 |
| 2021.4.27 |
| 今朝ほど秋聲生誕150年記念連続講座・木谷喜美枝先生によります5月22日の第1回講座のお申し込み受付を開始いたしました。「○○と秋聲」と題した4回シリーズで、第1回のテーマは秋聲の師・紅葉先生。昨日講座のサブタイトルをいただきまして、正式名称が「師・尾崎紅葉と秋聲―『柿も青いうちは』で始まった―」となりました。 〝柿も青いうちは〟、ちょっとなにかしらの暗号めいていますね……その扉が3回ノックされたら中からそっと呟きましょう、「柿も青いうちは」――ここで表からなんと返ってくるかで秋聲一派か悠々一派か、あるいはまったくの部外者かがわかります。これに続けて「鴉も突つき不申候」と返ってくれば秋聲一派、「烏もつつき不申、赤くなれば、人間が銭を出しても、食べたがり申候」とまで流暢に返ってくれば桐生悠々一派、そのほかならまったくの部外者ですから決して扉を開けてはいけません。  と、ここまで妄想を膨らませておきながら、悠々バージョンは正確には「柿も渋いうちは」から始まっていました。「青い」は秋聲の記憶のほうでした。またこの発言の主は他でもない紅葉先生ですから、扉の向こうでカラス云々と答えたその人物は一周まわって紅葉一派の可能性もあるのでした。秋聲および悠々はこう言われたほう。それぞれ秋聲の自伝小説『光を追うて』と悠々の回顧録『想ひ出るまゝ』にふたりで体験した共通の出来事として描かれており、昨日ご紹介した金沢ふるさと偉人館さんの協力展示でもパネルに言及されています(あと当館オリジナル文庫『思い出るまま』所収の秋聲の随筆「紅葉先生と私」にも出て来ます)。 と、ここまで妄想を膨らませておきながら、悠々バージョンは正確には「柿も渋いうちは」から始まっていました。「青い」は秋聲の記憶のほうでした。またこの発言の主は他でもない紅葉先生ですから、扉の向こうでカラス云々と答えたその人物は一周まわって紅葉一派の可能性もあるのでした。秋聲および悠々はこう言われたほう。それぞれ秋聲の自伝小説『光を追うて』と悠々の回顧録『想ひ出るまゝ』にふたりで体験した共通の出来事として描かれており、昨日ご紹介した金沢ふるさと偉人館さんの協力展示でもパネルに言及されています(あと当館オリジナル文庫『思い出るまま』所収の秋聲の随筆「紅葉先生と私」にも出て来ます)。紅葉先生と秋聲の出会いにまつわるエピソードです。ここからどう展開してゆくのかは当日をお楽しみに。また会場は当館よりずっと広い上記の偉人館さんで、講座の参加費=偉人館さんの観覧料ですので講座の前後に展示をご覧いただくことも可能です。 なお繰り返しとなりますが、コロナの状況次第でこの先定員の増減など調整する場合がございますので連続講座とは言いながら各回のお受け付けとさせていただいております。お話の内容は独立したものになりますので、ご面倒をおかけいたしまして恐縮ながら、各回一ヶ月ほど前より毎度お申し込みのご案内をさせていただきます。 |
| 祝・偉人館企画展オープン! |
| 2021.4.26 |
 24日、われわれが秋聲生誕150年記念朗読会を開催している真裏で金沢ふるさと偉人館さんの秋聲生誕150年記念企画展「『光を追うて』に見る金沢―徳田秋聲と桐生悠々―」が開幕いたしました! ハァ~初日に駆けつけられず申し訳ございません!! テープカットはどなたが?? 世界のKAWABATA?(それは昭和45年、石川近代文学館さんの「徳田秋聲生誕百年記念展」オープニングのときのこと…) 24日、われわれが秋聲生誕150年記念朗読会を開催している真裏で金沢ふるさと偉人館さんの秋聲生誕150年記念企画展「『光を追うて』に見る金沢―徳田秋聲と桐生悠々―」が開幕いたしました! ハァ~初日に駆けつけられず申し訳ございません!! テープカットはどなたが?? 世界のKAWABATA?(それは昭和45年、石川近代文学館さんの「徳田秋聲生誕百年記念展」オープニングのときのこと…)本日遅ればせながら観覧にうかがい、当館所蔵資料たちのよそ行きの顔、あわせて偉人館さんのご趣向でもって集められた展示資料の数々をとくと拝見してまいりました。秋聲記念館で開催するとどうしたって固定した見方からの展示になってしまいますが、こうして他館さんにご紹介いただけるというのはとてもとても良いですね。『光を追うて』に登場する地名や施設のご解説が親切で、幼い秋聲がその足で歩き回った金沢の姿がよく見えてくるようです。また、そのあたりはさすがのふるさと偉人館。〝北陸の鉱山王〟横山隆興翁をはじめ、安宅彌吉など秋聲のまわりにいる人々が他でもない同館内の常設展で紹介されておりますので、ご解説の手厚さこのうえなし。今回はとくに同じく常設展にワンコーナー設けられている桐生悠々との交流に焦点を当てていただいておりますので、悠々サイドの資料がたいへん豪華でございました。悠々が亡くなったときにご長男に宛てて出されたお悔やみ状…小幡酉吉、小倉正恒、国府犀東など、秋聲とも同窓にあたる人々の筆跡が見事です。このメンツを見る限り、秋聲からのお悔やみ状もあって不思議ではないのですが、残念ながら現在はまだその存在が確認されておらず…今後どこかしらから発見されることを祈るばかりです。偉人館さん、ご協力ありがとうございます。8月29日(日)までの会期となっておりますので、常設展とあわせてぜひご観覧くださいませ。また当館資料的見どころは、キラキラでカラフルな綺麗なのもあるのに内容重視でご選択いただきお貸しした秋聲自筆短冊がことごとく地味な柄(というか無地)であったところです。秋聲らしいと思います。 末筆ながら、21日付の同館ブログ「偉人館雑報」もまた、アレッ秋聲記念館のブログかな!? と一瞬見紛うほどの秋聲ぶりですのでぜひぜひご一読願います。『光を追うて』展を紹介するにあたりさりげなくライティングの話題から入るそのスキル…こらァこれからも目が離せません。 |
いろいろな「徳田」 |
| 2021.4.24 |
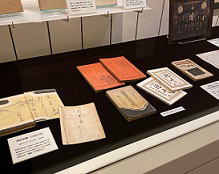 「古里の雪」原稿不在の穴を、秋聲がわかき日に読んでいた本たちで埋めました。紅葉先生、山田美妙、二葉亭四迷らのラインナップです(復刻を含みます)。そういえばドライな弟子と異なり秋聲の師・尾崎紅葉はとても多趣味な人でした。それについては秋聲が「先生は写真も玉突きも花もやつたが、どれも駄目で、弓だけは得意であつた」(『思ひ出るまゝ』)と絶妙に無礼に述べています。 「古里の雪」原稿不在の穴を、秋聲がわかき日に読んでいた本たちで埋めました。紅葉先生、山田美妙、二葉亭四迷らのラインナップです(復刻を含みます)。そういえばドライな弟子と異なり秋聲の師・尾崎紅葉はとても多趣味な人でした。それについては秋聲が「先生は写真も玉突きも花もやつたが、どれも駄目で、弓だけは得意であつた」(『思ひ出るまゝ』)と絶妙に無礼に述べています。同様に紅葉先生が亡くなったときの雑誌「新小説」追悼号(明治36年12月号)に寄せられた友人らの証言にも〝自分と同じ熱量で玉突きをやらないといって怒る紅葉〟〝熱中のあまり夜中までひとり玉を突きすぎて疲れてもう帰れないから泊めてくれと訪ねてくる紅葉〟〝写真うまくできたら送る、と言ったくせにたぶんうまく撮れなくて結局一枚も送ってこない紅葉〟〝字句にこだわりすぎた結果、作句の量が少ない紅葉〟(以上、巌谷小波談)、〝学生時代はテニスもボートもベースボールも嗜んだ紅葉〟〝足が非常に早く競争に勝利する紅葉〟〝生涯を通じ食道楽であった紅葉〟〝弓はけっこう長く続いた紅葉〟〝根ッ木(※ねっき、子どもの遊びの一種だそう)、竹馬など奇抜な趣味もあった紅葉〟(以上、川上眉山談)、〝煙草は喫うし、お菓子は常に二品揃えてお客と一緒に自分も食べる紅葉〟〝みんなで川で獲った雑魚を庭で揚げて即席天麩羅屋さんを始める紅葉〟(以上、広津柳浪談)、〝前を房々(ふさふさ)と長く、廻りをごく短く刈る独特の髪型をしていた紅葉〟〝筆をとって小栗の顔はこうだ、泉の腰つきはこうだとか言って漫画を描き出す紅葉〟(以上、後藤宙外談)など、いろいろな紅葉の趣味嗜好、そしてお人柄があらわれてまいります。 なおこの証言の第七を飾るのは秋聲の兄弟子・小栗風葉と某泉K花さんの談話。某K花さんのお言葉のなかにしばしば「徳田」が出て来てハッとさせられます。〝(紅葉先生の)病床へ小栗と伺う徳田〟〝(紅葉が入院することになったとき)いい機会だから病院でゆっくりすればいいと口癖のように言っていた徳田〟〝先に病室に行っていてドアをあけて先生を出迎える徳田〟〝(病床の紅葉に呼ばれ)「泉です」「徳田です」と順に名乗ってゆく徳田〟…おっといけない、いろいろな紅葉からいろいろな「徳田」に持っていかれてしまいました。 |
二頭の熊 |
| 2021.4.23 |
前回記事の秋聲クイズ(中級)、偉人館さんの秋聲展チラシにおいて秋聲が手にしているものの正解は「くまのパイプ」でした! 当館にお越しになったことがおありの方にはお馴染みの、また当HPの「徳田秋聲」のページの左側にあらわれるお写真で秋聲が握りしめているソレです。『古里の雪』の口絵も飾ったこちらは写真家・渡辺義雄氏の作品で、秋聲長男一穂さんによれば、昭和9年秋、銀座裏のオリエンタル乾板の写場で撮られたのだそう。当時秋聲64歳。 パイプの実物は徳田家よりお預かりして以来、当館1階再現書斎前のケースで主に展示させていただいておりましたが、現在は2階の企画展示室に一時的に移動いたしました。といいますのもこちら、実は父秋聲と子一穂のふたりがお揃いで購入したもので、さらにはこれと対になるもう一本が徳田家から新たに発見されたため。昨年刊行したオリジナル文庫『秋聲の家―徳田一穂作品集』の制作を通じてその事実が確認され、今回「家」をテーマとする企画展で初めて二本揃って展示をさせていただきました。 パイプの実物は徳田家よりお預かりして以来、当館1階再現書斎前のケースで主に展示させていただいておりましたが、現在は2階の企画展示室に一時的に移動いたしました。といいますのもこちら、実は父秋聲と子一穂のふたりがお揃いで購入したもので、さらにはこれと対になるもう一本が徳田家から新たに発見されたため。昨年刊行したオリジナル文庫『秋聲の家―徳田一穂作品集』の制作を通じてその事実が確認され、今回「家」をテーマとする企画展で初めて二本揃って展示をさせていただきました。〝発見〟と書きましたが、もちろん一穂さんご息女である徳田名誉館長はもう一本のパイプの存在自体はご存じであったところ、上記の文庫の編者である大木先生がどこにどれだけ載っているのかもわからぬ一穂作品をひたすらに収集してくださったうちの一篇「父の姿」でもって〝何故同じパイプが二本あるのか〟問題の答えが明らかになったというわけです。まさに記録と資料とが一致した瞬間でした。残念ながら今回初公開のもう一本は、熊のお顔の部分がポロッととれてしまってはいるのですが、二本並べることで二倍の意味と価値があるお品であり(厳密にどちらがどちらのものかは不明です…)「父の姿」も収録した文庫本後書きで名誉館長がこの件に触れてくださっています。 思えば、秋聲亡き後その作品集『古里の雪』の後書きを子・一穂がしたため、さらに一穂亡き後、その作品集の後書きをお子さんである名誉館長がしたためる…これぞ徳田家三代、「家」「もの」「思い」の三つが繋がってこそなせる技。なお今更ながら、文庫のカバーに使わせていただいた一穂さん画による白木蓮の色紙も徳田家からお借りして今回初公開いたしております。「下手くそよね? でもなんだか好きなのよ。」という名誉館長のお言葉が、カバーデザイン採用の決め手となりました。 |
| 祝・「偉人館雑報」更新 |
| 2021.4.20 |
| は、半年ぶりに更新されましたよ~ッ! 金沢ふるさと偉人館さんのブログ「偉人館雑報」、しかも内容が秋聲ですよ~~ッ!! ふァ~おめでたいことです、ありがとうございます。おかげさまで24日(土)から金沢ふるさと偉人館さんで開催予定の秋聲生誕150年記念企画展「『光を追うて』に見る金沢―徳田秋聲と桐生悠々―」に向け、先日、当館所蔵資料の貸出作業をおこないました。他館さんから資料をお借りすることはあっても、当館の資料がよそに借りられてゆくだなんていつぶりでしょうか…常設展にいつもお出ししている秋聲遺稿「古里の雪」(レプリカ)も旅の一味となりまして、秋聲没後に刊行された単行本『古里の雪』もろとも当館を旅立ってゆきました。ちなみに本書には中にピロリとした名刺大の紙片が挟まっており、こんな記述がございます。 「装幀は、玉井敬泉画伯の筆になる。表紙カバーは、北陸地方色豊かなカキ餅の図。見返しは、加賀友禅、遠く卯辰山、三十塔、五本松、近く天神橋、静明寺の甍を北都の冬、降りしきる雪景色の中に表わし、配するに、秋聲先生自筆の一句を以つて飾つた。 白山書房編輯部」 玉井敬泉は金沢出身の日本画家。「カキ餅」柄とはちょっとお珍しいですね。もし古本屋さんなどで本書をお見かけになることあらば、この貴重な情報満載なピロリが挟まっているかどうかをご確認ください。カキ餅柄の本体のほか雪印柄の函・帯・ピロリの3点が揃っていればかなり良いお品といえるでしょう。なお後書きは秋聲長男一穂さん。この本が刊行にいたった経緯とご家族でしか知り得ない秋聲の〝古里の雪〟への思いが記録されており、編者の大木先生のご推薦により『秋聲の家―徳田一穂作品集』のいちばん最後に収められました。  資料貸借の日、偉人館さんの企画展チラシもあわせて頂戴いたしまして、おおそのインパクトたるや! それぞれの道の先で貫禄あるお姿となった秋聲・悠々、その後方にはいまだ木造の四高校舎を前に語らう若く初々しいふたりの姿…偉人館さんのビジュアル担当としてお馴染み、イラストレーターの上出慎也さんの新作です。ご制作にあたり、ご丁寧にも改めて当館を訪ねてくださり、じっくりと展示をご覧くださった成果のひとつが秋聲の右手のソレ。 資料貸借の日、偉人館さんの企画展チラシもあわせて頂戴いたしまして、おおそのインパクトたるや! それぞれの道の先で貫禄あるお姿となった秋聲・悠々、その後方にはいまだ木造の四高校舎を前に語らう若く初々しいふたりの姿…偉人館さんのビジュアル担当としてお馴染み、イラストレーターの上出慎也さんの新作です。ご制作にあたり、ご丁寧にも改めて当館を訪ねてくださり、じっくりと展示をご覧くださった成果のひとつが秋聲の右手のソレ。○○の○○○――秋聲クイズ、中級編です。 |
「ダンス」(昭和5年5月発表) |
| 2021.4.19 |
 ふんわり昨日の記事のつづきです。昭和5年、60歳になって社交ダンスを習い始めた秋聲はことのほかそれに熱中し、このころ新しく得た趣味としていろいろな媒体においてダンスを語ります。「私は社交ダンスなどやらうとは夢にも思つていなかつた」と語り出される随筆「ダンス」では、その他の趣味嗜好に関する所感がそれぞれ述べられており、以下にざっくりまとめるとこう。 ふんわり昨日の記事のつづきです。昭和5年、60歳になって社交ダンスを習い始めた秋聲はことのほかそれに熱中し、このころ新しく得た趣味としていろいろな媒体においてダンスを語ります。「私は社交ダンスなどやらうとは夢にも思つていなかつた」と語り出される随筆「ダンス」では、その他の趣味嗜好に関する所感がそれぞれ述べられており、以下にざっくりまとめるとこう。花札・マーヂヤン→一向うまくならない 碁・将棋→数理的な観念を必要とするものは不得手(※幾何代数で落第経験あり) 野球→さう興味を惹かれない 球撞き(ビリヤード)→角度の微妙な感覚が乏しいので遣(や)れさうにもない ゴルフ→少し堪へがたいかも知れない 謡曲・義太夫→悪くはないかも知れない(が、やる気にはなり得ない) 勝負事→感興が唆られない(勝敗観念をもつことができない) 競馬→馬が可哀さうで見てゐられない 散歩→砂塵の深い東京の町では、鼻の穴が黝(くろ)くなつて、弱い気管を悪くす るばかり …麻雀、将棋、囲碁、競馬、野球、水泳、さらにはダンスと、かなり多趣味で多才な菊池寛さんのいっぽう趣味に関して秋聲はかなり限定的です。基本虚弱ですし(現在の企画展パネルで新聞記者に「るい弱(羸弱)」と言われている秋聲…)ビリヤードで角度が云々と言っているのはくわえてどうも方向音痴らしく、「頭脳がわるいので、角度や方向の観念に乏しい。省線に乗つてゐても、時々反対の方向に逆進してゐるやうな錯覚に陥つたり駅の出口をよく間違へたり、乗換へを誤つたりする。何処かの帰りに自動車で銀座の真ン中へ引ツ張(ぱり)出されてもどつちが新橋でどつちが京橋だかはつきりしないことも珍しくない」とのことですので周囲のみなさま、いい大人ですけれども秋聲先生をどうかおひとりで銀座の真ン中へ置き去りにしないでください。帰ってこられなくなりますので、そこはくれぐれもお頼みもうします…! そんな秋聲がではどうしてダンスには関心を示したかといいますと、「私に最も不似合で、又最も不得手な機械的動作の練習であることが、多少の好奇心を唆つたに過ぎない」…らしいです。大丈夫です、ダンスホールも白いシューズもよくお似合いです。 |
| 「雨を聴きつゝ」(昭和3年6月発表) |
| 2021.4.17 |
 菊池寛記念館さんで現在展示されているという将棋に触発されて今日この記事を書いております。菊池寛さんが将棋ならば、秋聲は花札。開催中の企画展「秋聲の家」では徳田家から秋聲愛用の花札をお借りして初公開をさせていただいております。かなり年季が入っていてくたびれた感じの札がたくさん(展示品はその一部です)…ご提供くださった名誉館長(秋聲令孫)は申し訳なさげにこう仰せでした。「でもこれ汚いでしょ? ほんとに出す?」「ええ、出しますね(キリッ)」「じゃあどこか隅っこのほうに賑やかし程度にね?」「ええ、では賑やかし程度に(ニコッ)」としていそいそと持ち帰らせていただき、秋聲ティーカップと秋聲シューズの間に堂々とお出しいたしました(長文キャプション付き)。名誉館長、あのとき一点の曇りもない良い笑顔でしっかりと嘘をつきまして申し訳ございません…しかしながらこの使い込まれた感こそ一朝一夕には演出できぬ味、そして歴史というものではございませんか。よくあるどなたかからいただいた献呈署名本があまりにもまっさらさらで、アッこれは確実に読んでないですね! といったパターンとは異なり(それはそれで愉快ですが)ハァ~~秋聲がこれで遊んでいたんですねぇ~~この感じだとけっこうな頻度ですねぇ~などと想像される非常に良い疲れ具合です。そして疲れてはいてもそこは花札ですから一枚一枚が華やかにてそれもまた良し。文字通り展示室の花。今回展の見どころのひとつです。 菊池寛記念館さんで現在展示されているという将棋に触発されて今日この記事を書いております。菊池寛さんが将棋ならば、秋聲は花札。開催中の企画展「秋聲の家」では徳田家から秋聲愛用の花札をお借りして初公開をさせていただいております。かなり年季が入っていてくたびれた感じの札がたくさん(展示品はその一部です)…ご提供くださった名誉館長(秋聲令孫)は申し訳なさげにこう仰せでした。「でもこれ汚いでしょ? ほんとに出す?」「ええ、出しますね(キリッ)」「じゃあどこか隅っこのほうに賑やかし程度にね?」「ええ、では賑やかし程度に(ニコッ)」としていそいそと持ち帰らせていただき、秋聲ティーカップと秋聲シューズの間に堂々とお出しいたしました(長文キャプション付き)。名誉館長、あのとき一点の曇りもない良い笑顔でしっかりと嘘をつきまして申し訳ございません…しかしながらこの使い込まれた感こそ一朝一夕には演出できぬ味、そして歴史というものではございませんか。よくあるどなたかからいただいた献呈署名本があまりにもまっさらさらで、アッこれは確実に読んでないですね! といったパターンとは異なり(それはそれで愉快ですが)ハァ~~秋聲がこれで遊んでいたんですねぇ~~この感じだとけっこうな頻度ですねぇ~などと想像される非常に良い疲れ具合です。そして疲れてはいてもそこは花札ですから一枚一枚が華やかにてそれもまた良し。文字通り展示室の花。今回展の見どころのひとつです。花札は社交ダンスを始める以前の秋聲唯一の趣味でして、おそらく今日のような雨の或る日に、こんなことを語っております。「私の道楽は花くらゐのものだ。別に面白いとも思はないが、相手があれば時間潰しに引くのである。これは不健全だ。しかし花には不分明な領域があるので、私のやうな頭脳のわるいもので相当楽しむことができる。碁や将棋のやうに割り切れないところに多少の興味が繋(かか)つてゐる。若(も)し花に不分明な領域がなかつたら、私は嫌ひになるだらう。人生も隅から隅までわかつたら、私のやうな悧巧でない人間は生きてゐられないかも知れない。」…あ~…これは全文をよまねばならぬやつですね…花札をきっかけとして思った以上に深い領域を語り出しております。このあと花札は引き方に個性が出ておもしろい、といったことにも触れており、たしかに秋聲作品には花札を引く場面が多く登場。たとえば『黴』と姉妹編『足迹(あしあと)』このふたつだけでも計30回くらいはありそうです。(つづく) |
| 「三猿」の世界 |
| 2021.4.14 |
| 石川近代文学館さんご所蔵の「三猿」の書幅が金沢出身の画家・小原古邨の肉筆であることが判明したとのニュースが話題になっていますね! 他でもない桐生悠々が所持していたもの。実は当館でも10年前の悠々展でお借りしたことがございまして、恥ずかしながらそのときには「三猿」のメッセージ性ばかりに飛びつきその作者を追究するところにまで発想も手も及びませんでした。ご存じこの〝見ざる、言わざる、聞かざる〟の精神について、悠々は晩年名古屋でひとり発行していた「他山の石」第2年第3号(昭和10年2月)掲載の「三猿の世界と死の世界」という評論中、これを反語的に用いながら当時の内務省および陸軍省の二重の監督下における言論統制を痛烈に批判しています。「私たちは、今『三猿』の世界に棲む。何事も、見まい、聞くまい、喋舌(しゃべ)るまい。否、見てはならない、聞いてはならない、喋舌つてはならない『死の世界』に棲まされてゐるのだ。」…間もなくして、「他山の石」は相次ぐ発禁処分との戦いに突入するのです。 同年同月、秋聲は文芸懇話会の例会に出席しておりました。ちょうど一年前に内務省が文学者たちを召集して開催した発会式で、「政府はちゃべちゃべと文学のことに口出すな!」(意訳)と秋聲がガツンと言い放ったうえ「口は出すな、金だけ出せ」(ひどい意訳)と畳みかけた島崎藤村の強烈な牽制により、同席した広津和郎曰く「文芸統制の目論見が崩れ、〝懇話会〟という単なるゆるゆるの懇親会になってしまった」(意訳)という例の会です。なお「ちゃべちゃべ」とはでしゃばって余計な口や手を出してくるさまを指す金沢弁。「いま『他山の石』っていうパンフレットを出して頑張ってる悠々のあの溌剌さったら鈍色の金沢とは縁遠いけども、あの奇矯性はやっぱり金沢人だよね~」(意訳)とは秋聲の回顧録『思ひ出るまゝ』に語られるところです。  「三猿」書幅は今月24日~5月23日までは石近文さんの「北辰の青春―赤レンガ校舎で学んだ作家たち」展で、5月26日~6月27日までは調査にあたられた石川県立歴史博物館さんの「小原古邨」展で公開されるそうですので、この機に改めてぜひご覧ください。 「三猿」書幅は今月24日~5月23日までは石近文さんの「北辰の青春―赤レンガ校舎で学んだ作家たち」展で、5月26日~6月27日までは調査にあたられた石川県立歴史博物館さんの「小原古邨」展で公開されるそうですので、この機に改めてぜひご覧ください。ちなみに古邨の師匠・鈴木華邨は某K花さんの『照葉狂言』その他の口絵を手がけているそうですね。秋聲でも調べてみたのですが、ざっと見たところ古邨も華邨も発見できず…いつものあわよくば精神で絡みにゆかれず残念至極です。 |
「生誕150年記念連続講座」開講! |
| 2021.4.11 |
| 先日、北國新聞さんの150年記念事業記事でもご紹介をいただきましたとおり、来月から11月にかけて、秋聲とゆかりの四人衆をテーマにした連続講座(全4回)を開講いたします! 今ほどイベントページに情報をアップいたしました。〝連続〟講座とは言いながら、とくに内容は連続しておりませんしお受け付けも各回になりますのでご興味おありの回、あるいはご都合のよろしい回だけのお申し込みも可能です。本当は全回通しでお受け付けをしたかったのですが、このご時世、金沢ふるさと偉人館さんの通常100人キャパの会場をもってしても現状は半数以下の40名設定が、今後コロナの状況如何で80名にも20名にもなり…といった先の読めない定員数となっておりますので、ご面倒をおかけいたしますがその都度約一ヶ月前から募集をかけさせていただくこととしております。 初回は他でもない紅葉先生にお出ましいただき、2回目は因縁の兄弟子・某K花さん、からの秋聲になくてはならない第3回川端康成氏を経て、最終回は今年ともに生誕150年を迎える花袋さん。とかく顔の広い秋聲につき〝○○と秋聲〟とやり始めると隔月どころか毎月でも足りなくなってしまいますので、断腸の思いでこの四名様に絞らせていただきました。初回は今月27日(火)朝9時半より電話受付開始です。  初回講師の木谷喜美枝先生は昨秋刊行された『尾崎紅葉事典』(翰林書房)の編者のおひとり。作品編・人名編・事項編・解説編・資料編の全5編からなるなかなかの鈍器的なボリューム(12,000円也)にて、今後紅葉先生について調べるときにはまずこちらを引かねば話にならぬ、といった紅葉研究に必携の書となろうかと存じます。ちなみに「徳田秋声」の項は当館上田館長が執筆を担当しております。 初回講師の木谷喜美枝先生は昨秋刊行された『尾崎紅葉事典』(翰林書房)の編者のおひとり。作品編・人名編・事項編・解説編・資料編の全5編からなるなかなかの鈍器的なボリューム(12,000円也)にて、今後紅葉先生について調べるときにはまずこちらを引かねば話にならぬ、といった紅葉研究に必携の書となろうかと存じます。ちなみに「徳田秋声」の項は当館上田館長が執筆を担当しております。 紅葉先生と言いましたら、明日より通販を開始いたしますオリジナル文庫『秋聲翻案翻訳小説集 怪奇篇』の巻頭を飾るホーソン原作「楓の下蔭」には「尾崎紅葉補」と付され、その初出は明治31年(秋聲28歳)。秋聲はこの前後に「紅葉補」とくっついた作品をちょこちょこと発表しており、それらも含めて後に紅葉補による紅葉門下生たちの作品を集めた『楓の下蔭』が刊行される際の表題作および口絵のテーマとなった一篇です。 |
館報「夢香山」第13号発行 |
| 2021.4.10 |
 毎年度末に発行している館報「夢香山」第13号をHPに掲載いたしました! 間もなくイベント登録をいただいているみなさまのお手元にもお届けいたします。今号では、昨年の秋聲忌内で開催された井口哲郎先生と上田館長による記念対談録「〝いちがい〟な金沢人
岡栄一郎と秋聲」を巻頭に、開館15周年記念刊行物である文庫本3冊のご紹介、事業報告、コロナにより縮小された事業一覧等々を記録として収めました。栄一郎を語るとどうしたって漱石、芥川龍之介がツルツルッと導き出されてまいります。おふたりの名も話題の区切りとして章立ていたしましたので、ぜひお読みいただけましたら幸いです。〝いちがいもん〟栄一郎に優しく寄り添った井口先生のお話は言うまでもなく、もうひとつの読みどころは上田館長による漱石の文学論に突入したあたりのくだりです(この続きがきっと文京アカデミア講座「秋聲文学の評価の揺れ―漱石から川端へ」でお話しされることでしょう。) 毎年度末に発行している館報「夢香山」第13号をHPに掲載いたしました! 間もなくイベント登録をいただいているみなさまのお手元にもお届けいたします。今号では、昨年の秋聲忌内で開催された井口哲郎先生と上田館長による記念対談録「〝いちがい〟な金沢人
岡栄一郎と秋聲」を巻頭に、開館15周年記念刊行物である文庫本3冊のご紹介、事業報告、コロナにより縮小された事業一覧等々を記録として収めました。栄一郎を語るとどうしたって漱石、芥川龍之介がツルツルッと導き出されてまいります。おふたりの名も話題の区切りとして章立ていたしましたので、ぜひお読みいただけましたら幸いです。〝いちがいもん〟栄一郎に優しく寄り添った井口先生のお話は言うまでもなく、もうひとつの読みどころは上田館長による漱石の文学論に突入したあたりのくだりです(この続きがきっと文京アカデミア講座「秋聲文学の評価の揺れ―漱石から川端へ」でお話しされることでしょう。) 文京アカデミアさんに触れたついでに、この講座の第3回テーマは大木志門先生による「秋聲と一穂、父子作家の森川町の家」。文京区に現存する徳田家にまつわるお話をいただく予定にしており、ちょうど現在の企画展「秋聲の家」とも重なります。先日、例月のMROラジオさんでこの企画展のPRをさせていただいた際、徳田家の保存活動は同じ文京区にある森鷗外旧宅「観潮楼」跡の保存活動と時期的に重なっていて…とご紹介しようと頭のなかに用意はしていたのですが、例によって緊張がそれをすべて覆い尽くし結局鷗外のおの字も出せなかったことを思い出します。ついでに漱石の「猫の家」のこととか愛知県にある明治村のこととか「観潮楼」跡に建つ鷗外記念館さんのこととか同館で開催されている特別展「観潮楼の逸品―鴎外に愛されたものたち」に勝手にシンパシーを感じていることとか、いろいろいろいろ巡ってはいたのですけれども何もお出しできずに、では何を申し上げてきたかといいますと、主に展示中の秋聲の左手のデッサンの説明です。ラジオではおよそ伝わらない描かれた「手」の角度などなどの下手な説明に持てる時間のすべてを尽くし…文京アカデミアさんにお申し込みくださった方、そして当選された方、大木先生による確かなお話をお楽しみに。 |
| 「そらあるき」臨時号 |
| 2021.4.8 |
| 昨日の開館記念日は催しとしてはとくに何もしないのですが、ただいつもよりすっと背筋を伸ばして、館の床に落ちているゴミを昨日よりも素早く拾う、みたいな気持ちにはなる、そんな日です。 「よく晴れた冬の朝に高く積もった雪の上をそっと歩いてみます。雪の表面がカチンコチンに凍って『ゴボ』らずに歩けたらそれが『そらあるき』。 ほんの少しだけ視線をかえてみるだけできっと心地よい浮遊感で金沢の街を歩けるはず。ちょっと得したような背筋をすっとのばしたくなるような、そんな『そらあるき』気分を楽しんでください。」  上記は地元有志により発行されている小冊子「そらあるき」さんのご紹介文で、これまでに二度ほど秋聲に関する記事を載せていただいたことがあり、そんなご縁から今回すでに〝小冊子〟とは呼べないほどの分厚い『そらあるき
Special Edition 2020』に学芸員が寄稿させていただきました。このコロナ禍において、これまで予想だにしなかったいろいろな制約を強いられるなか、イヤこんなときだからこそ書かねばならない、出さねばならない、との気概でもって発行された臨時号。さまざまな分野の方々によるのべ39篇のエッセイ、書評が収録されていますので、もしご興味ございましたらご購入いただけましたら幸いです。販売店および通信販売につきましては、公式HPからご確認願います。 上記は地元有志により発行されている小冊子「そらあるき」さんのご紹介文で、これまでに二度ほど秋聲に関する記事を載せていただいたことがあり、そんなご縁から今回すでに〝小冊子〟とは呼べないほどの分厚い『そらあるき
Special Edition 2020』に学芸員が寄稿させていただきました。このコロナ禍において、これまで予想だにしなかったいろいろな制約を強いられるなか、イヤこんなときだからこそ書かねばならない、出さねばならない、との気概でもって発行された臨時号。さまざまな分野の方々によるのべ39篇のエッセイ、書評が収録されていますので、もしご興味ございましたらご購入いただけましたら幸いです。販売店および通信販売につきましては、公式HPからご確認願います。実はこの中でご紹介させていただきました秋聲の短編小説「生活のなかへ」こそ、6月の文京アカデミアで声優のうえだ星子さんにご朗読いただく作品なのでした。ある疫病により病室に集められた女たち。互いに身の上話をしつつ聴きつつ、やがて病気が治ってそれぞれの生活のなかへ帰ってゆく……そんな物語が、今の世の中にどう響くのか――朗読のあとうえださんと学芸員とで語り合います。といった概要が記されているのが文京アカデミーさんの広報誌「スクエア」3月号。ご案内が遅くなり恐縮ながら、文京アカデミーさんHPよりバックナンバーがPDFでご覧いただけます。あわせて第1回・第3回講座の概要も掲載されています。 |
| 秋聲生誕150年記念事業発表! |
| 2021.4.7 |
本日4月7日は当館の開館記念日でございます。昨日で開館から丸16年、そして今日から17年目に入ります。毎年とりたてて何もお祝いはしていないこの日ながら、今年はタイミング良く地元の北國新聞さんに嬉しいお知らせを載せていただきました。 題して「秋聲生誕150年記念事業」開催決定! 「開催」「決定!」というと何か大きなひとつのイベントのようですが、この一年を通じ中身はあれやこれやと多岐にわたって展開してまいります。5月~11月にかけて開催される連続講座や、秋のトークイベント、その他まだ不確定で公表できないもろもろもろもろ、しかしつい気が緩むとみんな教科書で一度は見たことのある空也上人像のようにぽろぽろぽろぽろ次々口から飛び出てきそうになるそのもろもろたちを両手でムンッと押さえつけて暮らす記念館一味です。もうすぐ中庭に穴を掘りそうです。たぶん脇腹を棒で突いたら出てきます。 題して「秋聲生誕150年記念事業」開催決定! 「開催」「決定!」というと何か大きなひとつのイベントのようですが、この一年を通じ中身はあれやこれやと多岐にわたって展開してまいります。5月~11月にかけて開催される連続講座や、秋のトークイベント、その他まだ不確定で公表できないもろもろもろもろ、しかしつい気が緩むとみんな教科書で一度は見たことのある空也上人像のようにぽろぽろぽろぽろ次々口から飛び出てきそうになるそのもろもろたちを両手でムンッと押さえつけて暮らす記念館一味です。もうすぐ中庭に穴を掘りそうです。たぶん脇腹を棒で突いたら出てきます。中でもメインは12月23日(木)、秋聲150歳のお誕生日当日に開催予定の朗読劇「赤い花」。平成から令和に変わるタイミングで生憎この日は祝日から平日に変わってしまいましたが、ここは日和るわけにはまいりますまい…や、やっぱり直近の土日に…と弱気になる気持ちをぐっと堪えて敢えての平日にぶつけてみました。だって二度と来ない秋聲の生誕150年のお誕生日その日をみんなでお祝いしたいから…!!(たぶん夜の公演になるとは思います) というわけで、まだすべての中身を詳しくご紹介できず恐縮ですが、秋聲の150歳をお祝いしたい、というお気持ちをもってくださる天使のようなみなみなさまにおかれましては是非とも殊に12月23日(木)の夜のご予定を空けておいてやってくださいませ。ハイ、4月に言いましたよ! 12月のことを4月に言いましたよ…! ハ~~ようやく一部が公表され、少しすっきりいたしました。ここからは各所と調整調整の毎日です。今後一体二体三体と、館の口からぽろぽろと記念事業たちがその輪郭を露わにしてゆくことと存じますので、どうかどうかお見逃しなく。 |
『翻案集』通販のご案内 |
| 2021.4.4 |
本日、遠く岡山県の吉備路文学館さんにおきまして、秋聲生誕150年記念ミニ展示「近松秋江と正宗白鳥」が開幕となりました! すぐすぐ飛んでゆかれず悔しい思いをしている記念館一味でございます。かえって、アラ金沢はちょっと遠いわ…という中国地方のみなみなさま、ぜひ吉備路さんへお運びください。しかも同館ではありがたいことに当館のオリジナルグッズも一部取り扱っていただいております。クリアファイルとつれづれ箋(一筆箋)と封筒です。このHPから通信販売もご利用いただけますが、どうしても送料・振込手数料がかかってきてしまいますので、こちらもお近くのほうでお買い求めいただけましたら幸いです。何から何までお世話になって…もう東にも西にも足を向けて寝られずこの2月から毎晩嬉し苦しいです… さて、グッズページを覗いていただくついでに、お待たせしております新刊『秋聲翻案翻訳小説集 怪奇篇』の通販の件、先ほどご案内をお出しいたしました。今月12日(月)よりお受け付けを開始いたします! 1日に意気揚々と発売したはよいものの、いざ通販をシミュレーションしだしてからアレッお送りする用の封筒がないよ!? 年度替わりのもろもろで手が足りないよ!? といつもながらの計画性のなさでもってぐずぐずさせており申し訳ございません。上記グッズページをご参照の上、12日(月)以降にメールくださいますようお願い申し上げます。こちらに収録作品7篇の作品名も掲載いたしました。『秋聲少年少女小説集』以上に秋聲らしからぬ怪奇的な物語たち…そりゃあそう! 秋聲オリジナルでないのだもの! というわけで、館職員もいまだ見慣れずよそよそしい感じで接してしまう新しい秋聲のお顔、そして『秋聲翻案翻訳小説集』のその名。「あの、翻訳…翻案集の件ですけど…」「あの、秋聲の翻訳作品しゅ…小説集の販売の件…」みたいな感じでまだ館内でも通称が決まっておらずモジモジフガフガしております。いっそここで決めてしまいましょうかしら…『翻案集』、『翻案集』といたします。なぜなら『翻案翻訳小説集』の収録作品の内訳が翻案6・翻訳1だから! 数の暴力!! さて、グッズページを覗いていただくついでに、お待たせしております新刊『秋聲翻案翻訳小説集 怪奇篇』の通販の件、先ほどご案内をお出しいたしました。今月12日(月)よりお受け付けを開始いたします! 1日に意気揚々と発売したはよいものの、いざ通販をシミュレーションしだしてからアレッお送りする用の封筒がないよ!? 年度替わりのもろもろで手が足りないよ!? といつもながらの計画性のなさでもってぐずぐずさせており申し訳ございません。上記グッズページをご参照の上、12日(月)以降にメールくださいますようお願い申し上げます。こちらに収録作品7篇の作品名も掲載いたしました。『秋聲少年少女小説集』以上に秋聲らしからぬ怪奇的な物語たち…そりゃあそう! 秋聲オリジナルでないのだもの! というわけで、館職員もいまだ見慣れずよそよそしい感じで接してしまう新しい秋聲のお顔、そして『秋聲翻案翻訳小説集』のその名。「あの、翻訳…翻案集の件ですけど…」「あの、秋聲の翻訳作品しゅ…小説集の販売の件…」みたいな感じでまだ館内でも通称が決まっておらずモジモジフガフガしております。いっそここで決めてしまいましょうかしら…『翻案集』、『翻案集』といたします。なぜなら『翻案翻訳小説集』の収録作品の内訳が翻案6・翻訳1だから! 数の暴力!! とはいえ『怪奇篇』とくっついているのでそのうち別の『○○篇』が出るのでしょう。すると無邪気に『翻案集』と呼べなくなるやも…そのときはそのとき、さっくり『怪奇篇』に変更です。 |
秋聲と悠々 |
| 2021.4.3 |
| 新年度に入りまして、金沢ふるさと偉人館さんのHPに秋聲のしゅの字が出ました~! 『光を追うて』は秋聲の『光を追うて』で間違いありませんでした! 次回企画展の正式名称は「徳田秋聲生誕150年記念『光を追うて』に見る金沢―徳田秋聲と桐生悠々」とのことで、しっかり生誕150年記念協力展示でございました。ありがとうございますありがとうございます。また秋聲と連れだって、サブタイトルに桐生悠々もご登場です。年齢こそ2つ下ですが秋聲の大事な〝竹馬の友〟〝文学の相棒〟。秋聲が作家を目指し歩き出すその背中を押してくれた人物です。どちらかというと自己評価が低く消極的な秋聲ですから(その頃いわゆる「若気の至り」といった謎の自信は人並みに持ち合わせていたようですが)、自分とは反対に活発で「紅葉なんてなんぼのもんじゃい!」と言い合える悠々の存在はとても大きかったことと思われます。当館の悠々展もきれいに10年前…と見るとそのときの冠が「没後70年記念」となっており、ちょっと待ってそれすなわち今年が没後80年!? …確かに昭和16〈1941〉年9月10日に亡くなっていて、その3日後の9月13日に秋聲最後の長篇小説『縮図』打ち切りが発表になり、3ヶ月には太平洋戦争開戦。それをラジオで知る秋聲の様子は、オリジナル文庫『秋聲の家―徳田一穂作品集』にご長男一穂さんの目線から繰り返し描かれています。 悠々なくして作家「徳田秋聲」は存在しなかったかもしれません。金沢ふるさと偉人館らしく、同館の展示では金沢における若き末雄青年に出会えることと存じます。  そして悠々つながりで、偉人館さんの協力展示と同日4月24日(土)から始まる石川近代文学館さんの企画展「旧制第四高等中学校校舎本館完成130周年記念 北辰の青春―赤レンガ校舎で学んだ作家たち」のメインビジュアルに、それこそ学生時代の悠々のお姿が…! はっはァ~あの校舎がつくられて今年で130年なのですかァ~…つまり明治24〈1891〉年7月に完成、そのとき秋聲と悠々はまだ四高に在学しておりますが同年10月に中退。この校舎が実際に使われだしたのは翌25年4月以降のようで、先立つ3月にふたりは一路東京へ…そして紅葉先生による例の「柿も青いうちは烏も突き不申候」をバチコーン! とくらって悠々は帰郷し四高に復学、秋聲は大阪の長兄直松のもとへ…ということで、無事四高を卒業した悠々の一方、秋聲はあの新築の赤レンガ校舎で学んではいないため、残念ながらこの企画展の仲間には入ってこないのでした。 そして悠々つながりで、偉人館さんの協力展示と同日4月24日(土)から始まる石川近代文学館さんの企画展「旧制第四高等中学校校舎本館完成130周年記念 北辰の青春―赤レンガ校舎で学んだ作家たち」のメインビジュアルに、それこそ学生時代の悠々のお姿が…! はっはァ~あの校舎がつくられて今年で130年なのですかァ~…つまり明治24〈1891〉年7月に完成、そのとき秋聲と悠々はまだ四高に在学しておりますが同年10月に中退。この校舎が実際に使われだしたのは翌25年4月以降のようで、先立つ3月にふたりは一路東京へ…そして紅葉先生による例の「柿も青いうちは烏も突き不申候」をバチコーン! とくらって悠々は帰郷し四高に復学、秋聲は大阪の長兄直松のもとへ…ということで、無事四高を卒業した悠々の一方、秋聲はあの新築の赤レンガ校舎で学んではいないため、残念ながらこの企画展の仲間には入ってこないのでした。 |
『秋聲翻案翻訳小説集 怪奇篇』 |
| 2021.3.31 |
| 4月4日(日)から生誕150年記念協力ミニ展示をしてくださる吉備路文学館さんのメイン企画展のチラシに米川正夫氏のお名前がございます。岡山出身のロシア文学者で、今回は展示しておりませんが徳田家からお預かりしている秋聲蔵書の中に2冊ほど米川氏の訳書あり。いずれもツルゲーネフ作『父と子・処女地』(世界文学全集21、昭和2年、新潮社)、『初恋ひ』(昭和10年、岩波文庫)で、さらに〝ツルゲーネフの翻訳〟から思い出されるのは二葉亭四迷。「年少のをり『浮雲』(※四迷の代表作)やツルゲネフの翻訳『あひゞき』『片恋』『ルウヂン』などは一方ならぬ刺戟を受けた」(「二葉亭の印象」)また、「チェホフやツルゲネーフ、トルストイの作品は、早くから瀬沼夏葉、二葉亭四迷等の手で訳されて、青年達の間に大きい影響を及ぼしてゐた、あの頃の私達は、ツルゲネーフの思想を、最も強く受けてゐたやうに思はれる」(「私の『黴』が出た頃」)とは秋聲が語るところです。
ツルゲーネフと秋聲…外国文学と秋聲…翻訳の仕事と秋聲…ツ、ツルゲーネフは入っていないがプーシキンは入っている…! というわけでたいそうな力技でこじつけました当館オリジナル文庫、今年度最後の一冊となる第13弾は『秋聲翻案翻訳小説集 怪奇篇』! ハァ~やっとこさこの文庫を手にすることができました。と言っている今日は3月も31日、文字通り年度末の最終日。おそろしいことです。なんとか今年度中に納品を間に合わせていただきましたので、明日4月1日より早速販売を開始いたします!  当館開館15周年記念出版として昨年7月にオリジナル文庫初の回顧録『思い出るまま』、12月に初の秋聲以外の作品集『秋聲の家―徳田一穂作品集』、そしてこのたび初の『〝翻案翻訳〟小説集』をもちましてこの企画の締め括りといたします。文字面を追いすぎてもはや目がチョロチョロ(3_3)になっておりますが、今回もまた前作の大木志門先生同様、館の外からロシア文学研究者の蓜島亘先生をお招きすることができ、本編の編集と作品の解題にくわえ超専門的な解説のご執筆を賜りました。恥ずかしながらこれは館の職員だけではとてもできないお仕事。蓜島先生におんぶに抱っこでなんとか刊行に漕ぎ着けました次第です。上述プーシキンのほかには『思い出るまま』にも頻出のナサニエル・ホーソンをはじめ、ウィルキー・コリンズ、マーガレット・オリファント、コナン・ドイルの原作作品計7編を収録して税込1,000円。この一冊が秋聲の翻訳・翻案作品分野における研究が進むひとつのきっかけとなれましたら幸いです。 当館開館15周年記念出版として昨年7月にオリジナル文庫初の回顧録『思い出るまま』、12月に初の秋聲以外の作品集『秋聲の家―徳田一穂作品集』、そしてこのたび初の『〝翻案翻訳〟小説集』をもちましてこの企画の締め括りといたします。文字面を追いすぎてもはや目がチョロチョロ(3_3)になっておりますが、今回もまた前作の大木志門先生同様、館の外からロシア文学研究者の蓜島亘先生をお招きすることができ、本編の編集と作品の解題にくわえ超専門的な解説のご執筆を賜りました。恥ずかしながらこれは館の職員だけではとてもできないお仕事。蓜島先生におんぶに抱っこでなんとか刊行に漕ぎ着けました次第です。上述プーシキンのほかには『思い出るまま』にも頻出のナサニエル・ホーソンをはじめ、ウィルキー・コリンズ、マーガレット・オリファント、コナン・ドイルの原作作品計7編を収録して税込1,000円。この一冊が秋聲の翻訳・翻案作品分野における研究が進むひとつのきっかけとなれましたら幸いです。※通信販売につきましては、取り扱い開始までに数日お時間いただきます。 手続きが完了いたしましたら、当HP・ツイッター等でご案内申し上げますので 今しばらくお待ちくださいますようお願い申し上げます。 上記記事中、言葉足らずで申し訳ございません…! (4月1日追記) |
定休日のご案内 |
| 2021.3.28 |
 当HPトップページと、ツイッターのほうで先んじてご案内いたしましたとおり、当館の所属する金沢文化振興財団所属の各施設におきまして、このたび「定休日」なるものが設けられることになりました。16年前に生まれてこのかた、年末年始と展示替え休館以外「定休日」なるものを知らずに育った当館ですのでいまだ若干どぎまぎしておりますが、はやくも今年の7月から導入とのことで、なんと開催中の「秋聲の家」展会期が当の7月に食い込んでいる…! この舞台裏では、定休日導入なるかならぬかの段階で今回展のチラシ印刷決行という経緯があり、その結果、チラシに記載の企画展会期中における休館情報のあたりがごく歯切れのわるい文言になるという…。しかも同じ財団所属施設のなかで7月まで会期がかぶっているのは当館だけ…。間の悪いことでほんとうにすみません。とてもとても申し訳ないのですが、これにより6月30日(水)までは無休、そして企画展会期中でも7月に入りましたなら6・13・20日の毎週火曜は休館とさせていただきますことをどうかお許しください。ご来館をご計画の際にはどうかくれぐれもご注意ください。 当HPトップページと、ツイッターのほうで先んじてご案内いたしましたとおり、当館の所属する金沢文化振興財団所属の各施設におきまして、このたび「定休日」なるものが設けられることになりました。16年前に生まれてこのかた、年末年始と展示替え休館以外「定休日」なるものを知らずに育った当館ですのでいまだ若干どぎまぎしておりますが、はやくも今年の7月から導入とのことで、なんと開催中の「秋聲の家」展会期が当の7月に食い込んでいる…! この舞台裏では、定休日導入なるかならぬかの段階で今回展のチラシ印刷決行という経緯があり、その結果、チラシに記載の企画展会期中における休館情報のあたりがごく歯切れのわるい文言になるという…。しかも同じ財団所属施設のなかで7月まで会期がかぶっているのは当館だけ…。間の悪いことでほんとうにすみません。とてもとても申し訳ないのですが、これにより6月30日(水)までは無休、そして企画展会期中でも7月に入りましたなら6・13・20日の毎週火曜は休館とさせていただきますことをどうかお許しください。ご来館をご計画の際にはどうかくれぐれもご注意ください。かつまたこの定休日はエリアごとに分けられており、当館を含む某K花館ら東山界隈および夢二館ら湯涌の施設は火曜休館(もともと火曜休館であった当館ご近所の金沢文芸館にあわせた形)、金沢ふるさと偉人館等のある広坂界隈は月曜休館(もともと月曜休館であった周辺の金沢21世紀美術館や大拙館にあわせた形)、しかしながらどっちかというと広坂寄りの犀星館さんは三文豪しばりで火曜休館のわれらの仲間。今後は何曜日に金沢を訪れるかが非常に重要となってまいります。 ご観覧のみなさまにはたいへんご不便をおかけいたしますが、これにより資料が守られ、館内や収蔵品のメンテナンスもしやすくなり、よりよい展示空間を提供させていただけることと存じます。博物館の仕事は展示・収集・保存。後ろの方にゆくにつれ、どうしても表からは見えにくい部分にはなりますが、どうか長い目でもってご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 |
[K5033]生誕150年記念コンサート |
| 2021.3.27 |
 記念展示のみならず記念コンサートをも開催しちゃう今年は秋聲生誕150年です! と、まるで自らの手柄かのように申し上げましたけれども実は毎年恒例、金沢で大々的に開催されております「いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭2021」中、5月3日(月・祝)14時~14時50分(開場13時半)、秋聲生誕150年記念のプログラムをねじ込んでいただけることになりました! ウワーありがとうございまーす!! 自分たちの主催でなく、かつこんなに大きな音楽祭の中でご開催いただけるだなんてまるで夢のようです。会場は石川県立音楽堂(金沢駅前です)交流ホール。主催者さまと何度か打ち合わせのうえ、秋聲が好んだ作曲家や作品の中に描かれている楽曲を中心に選曲していただき、とくに一昨年記念館で開催いたしました企画展「レコオドと私~秋聲の聴いた音楽~」をご観覧くださった方には、アッこれ! この曲! とご反応いただける構成となっているかと存じます。公演中、秋聲の人となり、また作品についてのご紹介があるかもないかも!? 全席自由で一般1,000円でございます。なんとすでにチケット購入受付が始まっておりまして、ご案内が遅くなり申し訳ございません。詳細は「いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭2021」公式サイトよりご確認ください。合い言葉は公演番号「K5033」、嬉しさがまわりまわって今後何かしらのパスワードを「K5033」に設定してしまう勢いです。貴重な枠をくださった楽都音楽祭実行委員会さまにこの場を借りて心よりお礼を申し上げます。当日、まるで仕事みたいな顔をして会場にお邪魔して、開始早々滂沱の涙で呼吸困難に陥っている人物がおりましたならそれが記念館一味です。できるだけ声を殺してまわりのお客さまにご迷惑をおかけすることのないようがんばりますので何卒ご容赦くださいませ。 記念展示のみならず記念コンサートをも開催しちゃう今年は秋聲生誕150年です! と、まるで自らの手柄かのように申し上げましたけれども実は毎年恒例、金沢で大々的に開催されております「いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭2021」中、5月3日(月・祝)14時~14時50分(開場13時半)、秋聲生誕150年記念のプログラムをねじ込んでいただけることになりました! ウワーありがとうございまーす!! 自分たちの主催でなく、かつこんなに大きな音楽祭の中でご開催いただけるだなんてまるで夢のようです。会場は石川県立音楽堂(金沢駅前です)交流ホール。主催者さまと何度か打ち合わせのうえ、秋聲が好んだ作曲家や作品の中に描かれている楽曲を中心に選曲していただき、とくに一昨年記念館で開催いたしました企画展「レコオドと私~秋聲の聴いた音楽~」をご観覧くださった方には、アッこれ! この曲! とご反応いただける構成となっているかと存じます。公演中、秋聲の人となり、また作品についてのご紹介があるかもないかも!? 全席自由で一般1,000円でございます。なんとすでにチケット購入受付が始まっておりまして、ご案内が遅くなり申し訳ございません。詳細は「いしかわ・金沢 風と緑の楽都音楽祭2021」公式サイトよりご確認ください。合い言葉は公演番号「K5033」、嬉しさがまわりまわって今後何かしらのパスワードを「K5033」に設定してしまう勢いです。貴重な枠をくださった楽都音楽祭実行委員会さまにこの場を借りて心よりお礼を申し上げます。当日、まるで仕事みたいな顔をして会場にお邪魔して、開始早々滂沱の涙で呼吸困難に陥っている人物がおりましたならそれが記念館一味です。できるだけ声を殺してまわりのお客さまにご迷惑をおかけすることのないようがんばりますので何卒ご容赦くださいませ。公式サイトの本イベントの紹介欄に「徳田秋聲はクラシックを愛した!」と潔すぎるキャッチコピーがついており、そうそうよく分からないながらにね…「音楽は己(おれ)には解らんが、しかし聴いてゐて何か知ら好い気持だよ。」「己は今夜の音楽会に酔はされてしまつたらしいよ。己のやうな音楽のおの字も知らないビヂネス・マンの頭を酔はせる音楽家の腕は大したもんぢやないか。かういふ気持は一体何と解釈したらいゝんだらう。」「してみると音楽には国境や人種はない訳だな。」(長篇小説『黄昏の薔薇』より)――まだ聴いてもいないのに、そう呟く準備だけはできました。 |
生誕150年記念協力展示③ |
| 2021.3.23 |
| 東京都文京区・竹久夢二美術館さん(開催中)からスタートして岡山は吉備路文学館さん(間もなく開幕)へ飛んだ展示のバトンがふたたび金沢へと帰ってまいりました! 秋聲生誕150年記念協力展示の第3弾は金沢ふるさと偉人館さん! 4月24日(土)~8月29日(日)の会期で、「『光を追うて』に見る金沢(仮)」という名の企画展を開催してくださるそう…(当館も所属する金沢文化振興財団所属館の催しが一覧できる「催しもの案内」なる刷り物で確認できます。当館HPトップページからもPDFで見られます)って…ぇっ…き、企画展レベル…!? いやおののくにはまだ早い…、(仮)ですから、蓋を開けたら「『光を求めて』に見る金沢」とかになっていて、『光を求めて』!? なにそれ知らない…!! と急に置いてけぼりにされるやもしれません。『光を追うて』ならば秋聲の自伝小説なのでよく知っています。が、文字面で早とちりして浮かれてしまってはきっときっと痛い目に……そんなわけで今後もふるさと偉人館さんの動向をよくよく注視してまいりたく存じます。そうでなくとも偉人館さんはちょっと目を離すとすぐに可愛いグッズを新発売されるのでまったく油断なりません。昨年会場をお借りしたイベントの際にもトートバッグやらスケッチブックやらノームハンカチやら可愛らしいものがたんとおありですなァ…! と眺めてきたもので  すが(そしてまんまとハンカチを買いました)、またちょっとぼんやりしている間にかの西田幾多郎も愛用した田井屋100年ノート復刻版、そして日本で最初のマッチを作った清水誠にちなんだレトロマッチがざくざくと増え…!(ちなみにこの清水誠氏は金沢市御歩町生まれだそうです。御歩町すなわち現東山、われわれ秋聲記念館のあるエリアです。画像は偉人館さんHPからお借りしました!) すが(そしてまんまとハンカチを買いました)、またちょっとぼんやりしている間にかの西田幾多郎も愛用した田井屋100年ノート復刻版、そして日本で最初のマッチを作った清水誠にちなんだレトロマッチがざくざくと増え…!(ちなみにこの清水誠氏は金沢市御歩町生まれだそうです。御歩町すなわち現東山、われわれ秋聲記念館のあるエリアです。画像は偉人館さんHPからお借りしました!)さらにこのたび北原白秋や柳田国男らとともに日本野鳥の会を創設した中西悟堂にちなむコースター、そして悟堂と天文学者・木村栄をモチーフにしたLEDルーペが新たに仲間入りして、その勢いとどまるところを知りません。ショップがあまりに楽しすぎて、ゆめゆめ秋聲協力展を見に行ったのにショップだけ見て満足して帰る、ということのございませんよう…また、もしあの『光を追うて』がわれわれの知っている『光を追うて』でなかったならば、こちらにて即座にお知らせします。 |
春来(きた)る |
| 2021.3.20 |
 2ヶ月半におよぶ長期工事休館も終わり、本日20日(土・祝)より新企画展「秋聲の家―徳田家所蔵品展」をひっさげ当館再始動をいたします! 最初にも最中にも最後にも言うてゆきましょう。徳田秋聲生誕150年の今年、改めまして何卒よろしくお願いいたします。 2ヶ月半におよぶ長期工事休館も終わり、本日20日(土・祝)より新企画展「秋聲の家―徳田家所蔵品展」をひっさげ当館再始動をいたします! 最初にも最中にも最後にも言うてゆきましょう。徳田秋聲生誕150年の今年、改めまして何卒よろしくお願いいたします。記念の企画展ですからいつも以上に気合いが入っており、今回展では徳田家旧蔵の初公開なる秋聲遺愛品の数々を惜しげもなくドッと出品させていただきました。展示資料につきましては、今後こちらでもちょこまかとご紹介してまいります。またおさまりきらずに諦めた資料も数知れず…それらは次回、次々回、とにかく今年開催する記念企画展のすべてで順次お出ししてゆく予定ですのでゆるゆるとご期待ください。なにせ年が明けるまでずっと秋聲生誕150年です。 企画展の始まりが終わり、そして次の準備期間の始まり……いつまでも余韻に浸っている暇はなく、スッと切り替えて次回企画展のことを考えねばなりません。次回は生誕150年記念企画展第二弾「秋聲を繋ぐ人々」(仮)。今回展ともすこぅし重なる部分がありながら、秋聲の名を、そして作品を後世に繋ぐ役割を果たしてくれた川端康成・広津和郎・野口冨士男らのはたらきについてご紹介する予定です。以前に開催いたしました「秋聲をめぐる人々」展の続編といいましょうか、スピンオフといいましょうか、ご観覧くださったみなさまにおかれましては主に後半でご紹介をしておりました秋聲の後進にあたる人々にとくにスポットを当てた内容を考え中です。昨年、茨木市立川端康成文学館さんとお約束いたしましたとおり、秋聲文学碑建設記念の川端康成オリジナルお湯呑みをふたたびお披露目しなくてはなりませんから…! 今回展でも秋聲愛用のかわいいお湯のみが出ておりますので展示室で探してみてください。あと当館図録の表紙に用いたティーカップもお隣に並んでいますし、秋聲が俳句を揮毫して制作した楽焼のお皿もお出ししました(こちらはめぐる人々展以来ですね)。なお、この楽焼の由来をお知りになりたい方は、販売中のオリジナル文庫『秋聲の家―徳田一穂作品集』をお買い求めください。急に商売ッ気を出してすみません。177頁です。 なんだかんだと言いながら、今年は秋聲生誕150年ですってね! |
| 「あつまれ! ハンジョー屋台」 |
| 2021.3.18 |
| 14日付記事で触れましたように、文京アカデミア講座に全力投球するため6月の展示解説はお休みにさせていただき、と先ほど改めてイベントのラインナップを眺めながらふと4月の展示解説を復活させるのを忘れたことに気がつきました。会期中のイベントを決める際、実は4月恒例のお茶会にひっかけて特別な催しを考えており、そのためにやはり展示解説をお休みの予定にしていたのですが結局お茶会もそれも中止にしてしまった上旬、イベントが取りやめになったのですから、せめて展示解説は実施すればよかったのでした。こいつぁうっかり…! HPだけならしれっと修正できますが、チラシにも開催日程をすべて載せてしまったものですから、すみません4月回はお休みのままとさせてくださいませ。そろそろイベント登録者のみなさま方のお手元に新企画展チラシが到着したころでしょうか(なお開催初日の展示解説は定員に達しましたので受付を締め切らせていただきました。お申し込みありがとうございました!)。 ただいま18日16時半、企画展の設営は8割方終了いたしまして、なかなかお賑やかな展示室となりました。あいかわらずギッチリミチミチに資料が詰まっておりますので、狭いお部屋ではありますがなかなか見応えがあろうかと存じます。なお開催初日のあさって20日(土)はそんなお賑やかな展示室の外でも、ご近所で愉快なイベントが開催されるようですよ! 「あつまれ! ハンジョー屋台」と書かれたかわいらしいチラシが先ほど館に届きました。  この東山界隈のお店屋さんが協力して、10時~12時半、浅野川の河川敷にキッチンカーを出没させるもよう。淹れ立てコーヒーやサンドイッチ、メロンパンにその他スイーツ、雑貨、金魚すくいも……金魚すくい!? そうチラシに書いてございますのでいわゆるあの「金魚すくい」なのでしょう。午後からは屋台が近隣の古書店・あうん堂さんやカフェくわじまさんに移動されるとのこと。詳しくはこちらからご確認ください。雨天中止とも書き添えられていて、この日きっと晴れたらいいですね…(今のところは大丈夫そう)。川に臨む白木蓮もあさってにはもう咲きそうです。 この東山界隈のお店屋さんが協力して、10時~12時半、浅野川の河川敷にキッチンカーを出没させるもよう。淹れ立てコーヒーやサンドイッチ、メロンパンにその他スイーツ、雑貨、金魚すくいも……金魚すくい!? そうチラシに書いてございますのでいわゆるあの「金魚すくい」なのでしょう。午後からは屋台が近隣の古書店・あうん堂さんやカフェくわじまさんに移動されるとのこと。詳しくはこちらからご確認ください。雨天中止とも書き添えられていて、この日きっと晴れたらいいですね…(今のところは大丈夫そう)。川に臨む白木蓮もあさってにはもう咲きそうです。 |
| 気持ちを形に |
| 2021.3.17 |
| 14日、地元の北陸中日新聞さんに、生誕150年記念協力展示のことを大きく記事にしていただきました。東京・竹久夢二美術館さんにはじまり、来月頭からは岡山・吉備路文学館さんで開幕する、平たく言うと「多かれ少なかれ徳田秋聲にちょっと触れるよ」展のご紹介です。実は紙面のほうは当館学芸員の言葉「秋聲は地味な作家じゃない。」(キリッ)で締められていて、言…いましたね、ハイ言いましたね…ご取材いただいた当時、いかに鼻息荒く興奮状態であったかを思い返しては今頃恥ずかしくなっております。これまでさんざ地味地味と誰よりも率先してまず記念館が「地味」を発信しておいて、急にこれまでの秋聲史および館の十数年をあっさり裏切りにかかる驚きの身の翻し方…。あの…地味は地味なのですけれども…決してそれだけじゃないと言いましょうか…「秋聲? 地味だよねぇ~(笑)」で終わらせてもらっては困ると言いましょうか…ちょっとあの…地味は滋味でね、あのほんと、それだけでないいろんな含みが…へへ、言葉足らずで…すみません…… いずれにせよ秋聲の名のもと全国の施設さまがこうして動いてくださるのですから、そこは派手に誇ってよいところ。秋聲の人脈とあわせてこの機にぜひ色々な側面を知っていただけましたら幸いです。  そんな気持ちでこの展示替え期間中に館の表のタペストリーもかけ替えまして、いつもなら企画展名を載せるところ今回ばかりは「徳田秋聲生誕150年」の文言に差し替えてみました。デザインの段階から「ちょっと文字おおきいですかねぇ…?」とびくびくしていたのですが、実際に設置してくださるさまを見守るうちにも「…ッやっぱりちょっとおおきかったですかねぇ…!?」と心臓がばくばくしはじめ、設営業者さんが「いいえ、これくらいでちょうどいいです!」ととてもいい笑顔で自信を持って言ってくださらなければ危うく心臓が爆発してしまうところでした。と、そこにいらした別の工事業者さんも(浅野川の土手に降りる階段を修理していただいています)ふと見上げて「生誕150年かぁ…」と小さく呟かれたので、これはこれ、大正解です。秋聲に関し、たとえ他に何の情報も関心もなくても通りがかられる方々に「徳田秋聲という人が生誕150年らしい」ととりいそぎそれだけインプットされれば万々歳です。 そんな気持ちでこの展示替え期間中に館の表のタペストリーもかけ替えまして、いつもなら企画展名を載せるところ今回ばかりは「徳田秋聲生誕150年」の文言に差し替えてみました。デザインの段階から「ちょっと文字おおきいですかねぇ…?」とびくびくしていたのですが、実際に設置してくださるさまを見守るうちにも「…ッやっぱりちょっとおおきかったですかねぇ…!?」と心臓がばくばくしはじめ、設営業者さんが「いいえ、これくらいでちょうどいいです!」ととてもいい笑顔で自信を持って言ってくださらなければ危うく心臓が爆発してしまうところでした。と、そこにいらした別の工事業者さんも(浅野川の土手に降りる階段を修理していただいています)ふと見上げて「生誕150年かぁ…」と小さく呟かれたので、これはこれ、大正解です。秋聲に関し、たとえ他に何の情報も関心もなくても通りがかられる方々に「徳田秋聲という人が生誕150年らしい」ととりいそぎそれだけインプットされれば万々歳です。地味に生きてきた当館ですが、今年ばかりは大人しくしている場合でなく、協力してくださる他館さんへの感謝の気持ちもこめて、慣れぬ精一杯の「派手」さでもってがんばってみたタペストリーです。 |
「浅野川の春」 |
| 2021.3.15 |
アッお茶会の依頼文…! とか、アッお茶会の広報締め切り…! とか、この時節柄おりおり白昼夢に脅かされておりますが、この春は毎年恒例のお茶会がないので準備する必要がないのでした…。昨年も泣く泣く中止といたしました「桜の季節のおもてなし」(呈茶会)、今年も春は開催を諦めましたのでお含みおきのほどよろしくお願いいたします。開館5周年記念事業として始まり、その翌年のうちに多くの再開催を望むお声をいただき、そんなら…と茶道裏千家
井奈宗孝社中のみなさまのご厚意に甘え7周年から春の恒例行事として復活をいたしましたこの催事。そこから毎年続けてきたものが、また1年2年と間があいて…10年後くらいにこの年はなんでやってないんだろう? と、きっと回数が飛んでいる謎について後継の人々が思いを巡らすことでしょう。「桜の」が無理でも「新緑の」とか「海開きの」とか「紅葉の」とか、ぜひどこかの季節には開催いたしたく、今は伏しその機をジッとはかっているのです。時季が変われば毎年この日にあわせ名店「吉はし」さんにオリジナルで作っていただいているお菓子の風情も変わりますのでそれはそれで楽しみですね。 そしてまた、お茶会はないけれども朗読会はある! というわけで、4月24日(土)、生誕150年記念朗読会「浅野川の春」を開催いたします! 茶菓子なくとも桜は咲くし、川原に春はやってくるのでございます。以前に館内見学でお越しくださった金沢中日文化センターさんのご厚意により、そのお教室「心を繋ぐ朗読」メンバーのみなさまが秋聲作品を朗読しに来てくださることになりました。指導を担当されるのは大橋のり子先生(フリーアナウンサー)。金沢市民なら誰しもが知っている、長く地元の放送局で夕方ニュースの顔として活躍なさった御方です。お打ち合わせのなかで、春らしくほっこりとする作品を…(超難題)とのことで金沢とも微妙に絡む秋聲の短編「丸薬」をチョイスさせていただきました。無理想・無解決・無道徳・無常識・無感動で知られる基本淡泊な秋聲には珍しいご家族ほっこり感を味わっていただけることと存じます。また、秋聲のお人柄がわかるような作品もあったらいいなぁとの観点から、「秋聲会」を代表して室生犀星さんを強制出演させる目論見…! 犀星さんが郷里の先輩として某K花さん、そして秋聲を語る随筆「夢香山」もあわせてプログラムにイン! お茶もお菓子も出ませんが、記念館より「浅野川の春」をお届けします。 そしてまた、お茶会はないけれども朗読会はある! というわけで、4月24日(土)、生誕150年記念朗読会「浅野川の春」を開催いたします! 茶菓子なくとも桜は咲くし、川原に春はやってくるのでございます。以前に館内見学でお越しくださった金沢中日文化センターさんのご厚意により、そのお教室「心を繋ぐ朗読」メンバーのみなさまが秋聲作品を朗読しに来てくださることになりました。指導を担当されるのは大橋のり子先生(フリーアナウンサー)。金沢市民なら誰しもが知っている、長く地元の放送局で夕方ニュースの顔として活躍なさった御方です。お打ち合わせのなかで、春らしくほっこりとする作品を…(超難題)とのことで金沢とも微妙に絡む秋聲の短編「丸薬」をチョイスさせていただきました。無理想・無解決・無道徳・無常識・無感動で知られる基本淡泊な秋聲には珍しいご家族ほっこり感を味わっていただけることと存じます。また、秋聲のお人柄がわかるような作品もあったらいいなぁとの観点から、「秋聲会」を代表して室生犀星さんを強制出演させる目論見…! 犀星さんが郷里の先輩として某K花さん、そして秋聲を語る随筆「夢香山」もあわせてプログラムにイン! お茶もお菓子も出ませんが、記念館より「浅野川の春」をお届けします。 |
文京アカデミア講座~秋聲スペシャル~ |
| 2021.3.14 |
 ご案内が遅くなり申し訳ございません! まさにまさに秋聲が人生の半分以上を暮らした文京区にて、金沢市連携講座「~生誕150年記念~文京区に生きた作家・徳田秋聲」の開催が決まりました! 三年前に一度お邪魔いたしました文京アカデミアさんの講座で、この機に再び秋聲回を当てていただいた次第です。文京区のみなさま、ありがとうございます。こちらに全力を傾けたく、6月の展示解説はお休みとさせていただきました。館の都合にて恐縮です。 ご案内が遅くなり申し訳ございません! まさにまさに秋聲が人生の半分以上を暮らした文京区にて、金沢市連携講座「~生誕150年記念~文京区に生きた作家・徳田秋聲」の開催が決まりました! 三年前に一度お邪魔いたしました文京アカデミアさんの講座で、この機に再び秋聲回を当てていただいた次第です。文京区のみなさま、ありがとうございます。こちらに全力を傾けたく、6月の展示解説はお休みとさせていただきました。館の都合にて恐縮です。全3回講座で、内容といたしましては下記のとおりです。 第1回:講座「秋聲文学の評価の揺れ―漱石から川端へ」 日 時:5月29日(土)14時~15時30分 講 師:上田正行(当館館長) 第2回:朗読&トーク「生活のなかへ」 日 時:6月5日(土)14時~15時30分 出 演:うえだ星子氏(声優)、薮田由梨(当館学芸員) 第3回:講座「秋聲と一穂、父子作家の森川町の家」 日 時:6月12日(土)14時~15時30分 講 師:大木志門氏(東海大学教授、当館初代学芸員) 会 場:(全回とも)アカデミー文京 学習室 〔〒112-0003 東京都文京区春日1-16-21 文京シビックセンター内〕 ご応募いただける条件が「文京区内在住・在勤・在学者(15歳以上、中学生を除く)」となっており、なかなかピンポイントなのですが、あてはまるという方、ご興味ございましたらすでにお申し込み受付開始されておりますのでこちらから詳細ご確認くださいませ。三年前には〝三文豪〟がテーマにつき当館館長が総括的に、学芸員が秋聲のお話をしに伺ったところ、今回はオール秋聲回! オリジナル文庫『秋聲の家―徳田一穂作品集』を編集していただいた大木先生による文庫にはとても収まりきらなかったお話や、YouTubeで秋聲作品を配信しつづけてくださっているうえださんのお声をじかにお聴きできるまたとないチャンスです。 |
「新 美の巨人たち」 |
| 2021.3.13 |
| 約二ヶ月半におよぶ工事等休館を経て、あれよあれよと開館まで残り一週間となりました。ウワァアア~~~なにもかもまにあわないよ~~~! と浅野川に向かって叫びつつ、積んだもろもろを横目に久しぶりに寸々語を書きにきております。テスト前にお部屋のお掃除をはじめる、同じ同じ、みんな同じ。 さて、花袋秋聲生誕150年記念事業における東京・文京支部こと竹久夢二美術館さんおよび館林本部こと花袋記念文学館さんなど、諸方面よりお知らせをいただきました(ありがとうございます!)本日夜10時~10時半、みんなァ~テレビの前にあ~つま~れェ~~! テレビ東京系列「新 美の巨人たち」にて夢二さんの特集放送がおありだそうですよ! 以前の記事でご案内申し上げました竹久夢二美術館さんや群馬県立館林美術館さんで開催中の夢二展についてもそれぞれご紹介があるとか。もちろん本題である夢二さんについての内容が楽しみであることは言わずもがな、いずれも展示室に潜む秋聲作品の映り込みのありやなしや、全国の秋聲会のみなみなさまにおかれましても固唾を呑んで見守る30分間となりそうですね(十中八九映らない)。 オゥ…テレビ東京見られないよう…! とお嘆きの当館を含む関東圏外のみなさまもどうかご安心ください。BSテレビ東京さんにて3月20日(土)夜11時30分より再放送がございます。おそらく本日の放送後、ツイッター等で「夢二」「秋聲」などとこっそり検索してしまう未来も薄目に見えておりますが、それはそれとして北陸地方のわれわれは来週の放送をじりじりとお待ちすることといたします。ちなみにBSのほうの本日の特集テーマは「ウィリアム・メレル・ヴォーリズ『山の上ホテル』(東京/神田)」。とりいそぎのウィキペディアさま情報によりますと、昭和12年にその建物ができ、昭和29年にホテルとしての営業を開始したという山の上ホテルです。曰く、〝「文化人のホ  テル」として知られており、川端康成、三島由紀夫、池波正太郎、伊集院静らの作家が定宿としていた〟ほか、檀一雄の『火宅の人』の舞台ともなっているそうな。こちらはこちらで面白そうな内容となっておりますので、ご興味おありの方ぜひご覧ください。 テル」として知られており、川端康成、三島由紀夫、池波正太郎、伊集院静らの作家が定宿としていた〟ほか、檀一雄の『火宅の人』の舞台ともなっているそうな。こちらはこちらで面白そうな内容となっておりますので、ご興味おありの方ぜひご覧ください。改めまして夢二さんBS放送のある20日は当館再オープンの日。すなわち新企画展「秋聲の家―徳田家所蔵品展」の開催初日。おかげさまで春らしく美しいチラシも納品されてまいりました。やりきった充実感とともに、心穏やかに放送を見られることを今はただ祈るばかり……(と、一瞬の現実逃避を終えスッと作業に戻ります)。 |
生誕150年記念協力展示② |
| 2021.3.7 |
去る3月3日は、正宗白鳥、有本芳水のお誕生日であったということを吉備路文学館さんのツイッターで知りました。たいへん遅ればせながらお誕生日おめでとうございます! 白鳥さんにつきましては、いつでも当館で話題にのせてよいほどの秋聲との仲良し具合ですが、有本芳水さんにつきましては、ここ数日夢二さんづいている当館にとってハッとさせられるこのタイミング…竹久夢二美術館さんおよび群馬県立館林美術館さんでご紹介いただいている秋聲の『めぐりあひ』(実業之日本社刊)の担当編集者こそ有本芳水でございました。白鳥同様、岡山ゆかりの方だったのですね。 さて、今度は急激に岡山へと傾きました当ブログ、実は秋聲生誕150年記念協力展示の第二弾は他でもない吉備路文学館さんなのでございます! ワーありがとうございまーーーす! 来る4月4日(日)より吉備路文学館さんでミニ展示「徳田秋聲生誕150年記念展 近松秋江と正宗白鳥」(~7月11日(日))をご開催いただけることになりました! 秋聲が金沢から東京、群馬、そして岡山へとポンと飛ぶ、これは痛快!!(メイン企画展は「吉備路の文学者となつかしの校歌」、芳水さんのご紹介あり。画像クリックでPDFが開きます。) さて、今度は急激に岡山へと傾きました当ブログ、実は秋聲生誕150年記念協力展示の第二弾は他でもない吉備路文学館さんなのでございます! ワーありがとうございまーーーす! 来る4月4日(日)より吉備路文学館さんでミニ展示「徳田秋聲生誕150年記念展 近松秋江と正宗白鳥」(~7月11日(日))をご開催いただけることになりました! 秋聲が金沢から東京、群馬、そして岡山へとポンと飛ぶ、これは痛快!!(メイン企画展は「吉備路の文学者となつかしの校歌」、芳水さんのご紹介あり。画像クリックでPDFが開きます。)そのバックヤードで「すみません、だけど秋聲さんの資料ぜんぜんなくって…!」と仰る吉備路文学館さん、いいんですいいんです、秋聲の資料でなくともこの記念の年に各地で秋聲の面影を浮かびあがらせていただけるのならそれだけで御の字なのです。題におわします、ともに岡山のご出身である白鳥さんと近松秋江さんとは最も交流の深い秋聲ですから当館における秋聲の秋聲(第一主義の当館)による秋聲のための展示でなく、かえって親友おふたりから見る新しい秋聲のお顔を、この春ぜひお近くのみなさま観におでかけくださいませ。 当館の次回展では秋江さんは生憎出てこないのですが(すみません、ギャラリートークなどで補足します!)、白鳥さんは資料キャプションに二度三度ご登場です。展示にちょいとスパイスを利かせるのにちょうどいい白鳥さん…秋聲曰く「文壇では何といつても、正宗白鳥氏と私交上で尤も接触が多かつた。氏の言ふことは、ちよつとした芝居の批評でも、私には一番適切だし、又た一番私を知つてゐてくれるやうに思ふ」。また「あれほど親しくしてゐた秋江氏が、最近めきめき腕を上げて来たのは、私も尤も悦ぶところで、私交の上では忌憚なく口の利けるなかだと、今でも信じてゐる」(「交遊の広狭」)。 |
館林と金沢 |
| 2021.3.3 |
 その親切ぶり天井知らずの竹久夢二美術館さんより教えていただきました…現在、群馬県立館林美術館さんで開催中の企画展「竹久夢二の美人画とモダンデザイン―美しいもの・可愛いもの―」(1月23日(土)〜3月21日(日))にも秋聲作×夢二さんご装幀による『めぐりあひ』が出品されているそうな…!?(実際の展示状況につきましては主催館さんにお問合せください) 立派な図録にも秋聲のしゅの字を載っけていただき、夢二美術館さんしかり、なかなか「美術館」さんでめぐりあふことの少ない秋聲ですのでちょっとドキドキしております。う、美しいもの・可愛いもの、に秋聲も入れてもろうたよ…! 美術畑に生きる夢二さん(のバーター秋聲)のおかげさま、その存在のありがたみ…。同館のHPを拝見すると、先月20日には当館と同じ金沢文化振興財団所属の金沢湯涌夢二館・太田館長さんによる記念講演会が開催されたとのこと。なんと、われわれのアンテナ、休館の間にすっかり錆びついておりました。館林と金沢、こんな形でしっかりと結びついていたというに…! その親切ぶり天井知らずの竹久夢二美術館さんより教えていただきました…現在、群馬県立館林美術館さんで開催中の企画展「竹久夢二の美人画とモダンデザイン―美しいもの・可愛いもの―」(1月23日(土)〜3月21日(日))にも秋聲作×夢二さんご装幀による『めぐりあひ』が出品されているそうな…!?(実際の展示状況につきましては主催館さんにお問合せください) 立派な図録にも秋聲のしゅの字を載っけていただき、夢二美術館さんしかり、なかなか「美術館」さんでめぐりあふことの少ない秋聲ですのでちょっとドキドキしております。う、美しいもの・可愛いもの、に秋聲も入れてもろうたよ…! 美術畑に生きる夢二さん(のバーター秋聲)のおかげさま、その存在のありがたみ…。同館のHPを拝見すると、先月20日には当館と同じ金沢文化振興財団所属の金沢湯涌夢二館・太田館長さんによる記念講演会が開催されたとのこと。なんと、われわれのアンテナ、休館の間にすっかり錆びついておりました。館林と金沢、こんな形でしっかりと結びついていたというに…!館林と金沢といえば他でもない、それぞれともに今年生誕150年を迎える田山花袋さんと秋聲のホームグラウンド。同地の花袋記念文学館さんと当館とは、今年はよりいっそう両館でがんばってゆきまっしょい! と互いに鼓舞し合っている間柄です。前述の図録には秋聲の『めぐりあひ』のシリーズ本となる夢二さんご装幀による花袋さん作『小さな鳩』をはじめ、その他著作もたくさん掲載されていますので、花袋さんファンのみなさまもぜひチェックされてみてください。群馬県立館林美術館さま、このたびは花袋さんと生誕150年ハッピーセット・秋聲のご紹介までありがとうございました! ふたりは同い年ですし同じ自然主義作家として基本的に仲良しですが、正直なところ〝無二の友〟というほどには親しくないかもしれません(自然主義仲間の藤村とも)。秋聲とはどちらかというと、互いに遠くからその存在を意識し合い、困ったときにはそっと支え合い、気遣い合うような間柄――その距離感がちょうど館林と金沢、また花袋記念文学館さんと当館の関係性に反映されているような気がして、かえってとても頼もしくもあるのです。文京区、館林、金沢…意図せぬところに後乗りでもって図々しくもありながら、ふたりの生誕150年の輪が徐々に広がっている予感…! |
生誕150年記念協力展示① |
| 2021.2.26 |
 肝心の記念館が休館中なばかりにすっかり影が薄くなってしまっておりますが、今年は秋聲(と同年生まれの田山花袋氏)の生誕150年記念イヤーでございます。口はもう酸っぱ酸っぱだけれどもいまだ設備改修工事の裏側でウズウズモダモダしているそんな当館に代わり、なんと東京は文京区・秋聲第二のホーム(実は金沢暮らしより長いのでもはや第一やも…)において、かの竹久夢二美術館さんがその展示に秋聲を登場させてくださっておりますよ…! 現在開催中の企画展「夢二デザイン1910ー1930―千代紙から、銀座千疋屋の図案まで―」(2月11日(木・祝)~6月6日(日))中、夢二さんと秋聲の関係性をご紹介いただくほか夢二さんご装幀による秋聲著作をひとつならずふたつみっつ、贅沢にもどどんとワンコーナーおつくりいただいているのです! いつもありがとうございます!! ご紹介が遅くなり申し訳ございません!!! しかも秋聲のお隣には花袋さんもおわしまして、なんとも小粋な夢二美術館さんのおはからいではございませんか。 肝心の記念館が休館中なばかりにすっかり影が薄くなってしまっておりますが、今年は秋聲(と同年生まれの田山花袋氏)の生誕150年記念イヤーでございます。口はもう酸っぱ酸っぱだけれどもいまだ設備改修工事の裏側でウズウズモダモダしているそんな当館に代わり、なんと東京は文京区・秋聲第二のホーム(実は金沢暮らしより長いのでもはや第一やも…)において、かの竹久夢二美術館さんがその展示に秋聲を登場させてくださっておりますよ…! 現在開催中の企画展「夢二デザイン1910ー1930―千代紙から、銀座千疋屋の図案まで―」(2月11日(木・祝)~6月6日(日))中、夢二さんと秋聲の関係性をご紹介いただくほか夢二さんご装幀による秋聲著作をひとつならずふたつみっつ、贅沢にもどどんとワンコーナーおつくりいただいているのです! いつもありがとうございます!! ご紹介が遅くなり申し訳ございません!!! しかも秋聲のお隣には花袋さんもおわしまして、なんとも小粋な夢二美術館さんのおはからいではございませんか。 タイトルに協力展示「①」と入れましたように、実はこちらのご出品、昨年のうちよりふだんからお世話になっている関係施設さまにじわじわとお声がけをさせていただき、資料1点でもかまいませんから貴館にてどうか秋聲をご紹介いただけますまいか…? とダメ元でお訊ねをしてまわった結果の形。夢二美術館さんにいたりましては「よっしゃこーーーい! どんとこーーーい!!」と二つ返事でご承諾をくださり、当館で想像するより遥かに大きく、パネルまでご作成いただく特別待遇にて秋聲を大事に取り扱ってくださいました。ウッ…ウッ…なんたる懐の深さであろう…夢二さんとは微妙に恋のライバルなのに…いやそれはそれとして夢二×秋聲の作品たちは掛け値なしに美しいから…(作品はいずれも三角関係以前ですね)。ふたりの関係性およびその装幀本につきましては、ぜひ同館でご観覧ください。生誕150年協力展示の記念すべき第一弾! たくさんの施設のみなさまに支えられている果報者の秋聲記念館でございます。この場を借りて深くお礼を申し上げます。 そのようなわけで、こちらの展示を皮切りに、全国津々浦々、思いもかけないところから秋聲が飛び出してくる可能性のある今年です。今後とも情報が固まり次第、ご協力くださったみなみなさまをどしどしご紹介させていただきます! |
追悼 |
| 2021.2.23 |
| 3日、川端香男里先生が逝去されました。 平成28年、御尊父にあたる川端康成と秋聲との関係性をご紹介した企画展「康成、秋聲を読む。」の展示準備のなかで初めてお目にかかり、他でもない秋聲さんのところだもの! と気さくにご対応くださったうえ展示に多大なるご協力を賜りました。また資料借用に伺った際の帰り時間、お宅のある鎌倉が急な大雨に見舞われ「この時間じゃタクシーもなかなか来ないでしょう」と人を頼んで駅まで車でお送りくださるというお心遣い…時代を超え、秋聲と康成の関係性に改めて思いを馳せるとともに、そうしたゆかりをもさらに超えたところで川端先生その人の、温かいお人柄に感激をいたしました。 記念館一同、謹んでお悔やみを申し上げます。 |
| ぴったりとした場所 |
| 2021.2.22 |
| 昨日、写真撮影のお話をいたしました。秋聲と写真に関しましては当館オリジナル文庫『秋聲の家―徳田一穂作品集』収録の随筆「父の姿」に、〝どの場所で写真を撮ってもしっくり来ない父秋聲〟のお話がございます(一穂さんは秋聲ご長男)。雑誌社の人に「お好きな場所で」と言われなんとなく浅草の瓢箪池の傍で撮影してみたはいいがどうも違う…。〈七十三年の生涯を、飄々として、浅草を歩き銀座を歩き何処をでも歩いたが、結構、四十年間、気に入らないままに、動くことの出来なかった日当りの悪い、冬は寒く夏は暑い森川町の家さえも父には余りぴったりとしたものではなかった〉とはご長男一穂さんの書き添えるところです。この同じ出来事について秋聲曰く〈私には特別好きと思ふところもなく嫌いなところもない。本郷通りだけは死んだ妻と二人の子供のことを想ひ出すのと、余り長く住んでゐるので何だか遣り切れない気持になり懐しいといふ感じは少しも起らない。過去がいつでも後から喰(くっ)ついて来るやうである〉(「灰皿」昭和12年12月17日)――もはや好き嫌いの次元を超え、「家」を含んだ本郷森川町一帯が秋聲の過去、そして人生そのものと不可分であるようです。 あの暗い書斎を出て、どこか明るい海岸町で思うままに執筆させてやりたい、もし執筆すら重荷であるなら、居心地の良い部屋でただのんびりと暮らさせてやりたい、それが秋聲の晩年にもいちばん近くに寄り添った一穂さんの願いでした。しかし、秋聲の口癖は「書けなくなったら死んだ方がいい」。作家たる父はそうした生活を望まなかっただろう、とも記す一穂さんの一方、環境の良い大磯への転居を勧める川端康成さんらの誘いに揺れながらも最晩年の秋聲が選んだのはこの家で家族とともにあること(随筆「病床より」)。それを思うと、クッ…この親子…!! とゴロンゴロンに身悶えるほどの切なさに襲われるのです。  と、しんみりしてしまったところでティーブレイク。これぞ秋聲記念館にぴったりとしたおやつかな(※写真では文字まで見えませんがたまたま見つけた市販品のチョコレートで緑が「秋声(しゅうせい)」、赤いのが「紅葉(こうよう)」。一般名詞で作家名と直接の関係はなさそうです。Facebookには別途お写真載せておきます。なおなんとかして柄をお見せしたかった秋声モチーフのティーカップは収蔵品で撮影用。永遠に未使用です)。 と、しんみりしてしまったところでティーブレイク。これぞ秋聲記念館にぴったりとしたおやつかな(※写真では文字まで見えませんがたまたま見つけた市販品のチョコレートで緑が「秋声(しゅうせい)」、赤いのが「紅葉(こうよう)」。一般名詞で作家名と直接の関係はなさそうです。Facebookには別途お写真載せておきます。なおなんとかして柄をお見せしたかった秋声モチーフのティーカップは収蔵品で撮影用。永遠に未使用です)。 |
「夕方までテカリを抑える最強ファンデ」 |
| 2021.2.21 |
 雪に降り込められたここ数日、館内では次回企画展で展示予定の資料撮影会が開催されておりました。今回は立体物が多く難易度が高いものですからプロのカメラマンさんにまるっとお願いすることに。設備工事の隙間を縫って、かつこの休館をよいことにガランとした企画展示室を一時的な撮影スタジオに仕立てていただき本格的な資料撮影をおこないました。 雪に降り込められたここ数日、館内では次回企画展で展示予定の資料撮影会が開催されておりました。今回は立体物が多く難易度が高いものですからプロのカメラマンさんにまるっとお願いすることに。設備工事の隙間を縫って、かつこの休館をよいことにガランとした企画展示室を一時的な撮影スタジオに仕立てていただき本格的な資料撮影をおこないました。カメラマンさんというのは撮影技術は言わずもがな、目の前の資料のいちばん良い表情を引き出す才能をもお持ちの選ばれし人々…秋聲遺品のお帽子をいくつか撮っていただくなかでも、こっちのコレは正面もあったらいいですネ、と瞬時に判断して複数のカットをご提案くださるのです。また額装のもの(秋聲自筆のデッサンも久々に展示予定です!)を大きな板を駆使しながらお撮りになるさまに「は~そうやってテカリを抑えるんですか~」と思わず漏らすと「あっハイこれで反射を防いでます~」とより折り目正しき言の葉でご返答いただき(※訂正ではなくナチュラルなリアクション)、(お人柄…)と感動すると同時にアッやだッ夕方の化粧品のコマーシャルみたいだった今…! と顧みてひとり照れくさくなったりしておりました文学館職員です(この場にふさわしかったかどうかはともかく、商品のコピーとしては頗る優秀なのだと思います)。池田紀幸さん、お忙しいところ長丁場のご撮影をありがとうございました! 超売れっ子さんにもかかわらず、奇跡的なスケジュールの合い方に心からの感謝を捧げます! こちらの池田作品は間もなく完成予定の次回企画展チラシでご覧いただけますのでどうぞお楽しみに。 今回プロのカメラマンさんにお願いすることにいたしましたのは、先行するチラシのデザインが素敵だったから、ということもございます。毎回カッコイイチラシを作っているつもりではありますが(ひとえにデザイナーさん方と当館の好みを把握しきっている印刷会社さんたちのお力)今回もまた、こりゃ下手な写真は入れられないぞ!? との素晴らしい出来となっております。なにせ生誕150年記念企画展の一発目、当館の本気をご覧ください。 |
| 「ふとんの日」 |
| 2021.2.16 |
| なんと先日「2(ふ)10(とん)の日」を華麗にスルーしてしまいました! これはいけない、秋聲と同じく今年生誕150年を迎える盟友・田山花袋氏の代表作こそ「蒲団(ふとん)」でございます。とはいえ、あの日(前回記事)花袋さんの弟子筋にあたる作次郎さんのことを一生懸命にご紹介していたと思えば、花袋さんをスルーしてしまったその罪も多少軽くなろうってぇもの…。 それより何が罪深いといって「ふとんの日」すなわち「花袋の日」と言い換えても差し支えのないほどのこの日をわざわざ遡ってまで捕まえにいっておいて、ここからお話しし始めるのが花袋さんでなく秋聲のおふとんエピソード、というところです。その業、来世まで引き受けます。 明治40年発表の「蒲団」のあとを追いかけるようにして発表されたのが秋聲の出世作「黴」(明治44年)。本作には、後に妻となるはま夫人をモデルとする「お銀」に主人公「笹村」が愛用の蒲団のあまりに汚いことを笑われるくだりが出てまいります。その汚さたるや、自分の持ちものでもないのになんだか申し訳ない気がしてお銀が笹村のために敷くのを躊躇うほど。やがてふたりは所帯をもち、お銀とともに新しい蒲団を買いに出かけると同時に彼の「べとべとになつた蒲団」は「襤褸屑(ぼろくず)のなかへ突つ込まれて」しまい…所帯をもつということはきっとそういうことなのでしょう、蒲団が変わる――新居に移る、よりももっとずっと皮膚に近いところの感覚です。  実は同じエピソードが大正15年、はま夫人急死(享年46歳)直後に書かれた短編「過ぎゆく日」にも表れており、「融(とおる)は下宿屋から行李や蒲団や机やランプのやうなものを車に積んで、友人の建てた長屋風の家に入つて、初めて一箇の世帯主となつて間もなく妻と同棲することになつた当初に遡つて考へた。硬い蒲団や着物の汚ないのに驚いて、融が気味わるく思ふやうな綿のふかふかした蒲団を新調してくれたことや、裾の破けた着ものを釈いたり、汚れものを洗濯してくれた頃のことを思ひ出した」(ほほう、秋聲先生は好んでせんべい蒲団派…)。 実は同じエピソードが大正15年、はま夫人急死(享年46歳)直後に書かれた短編「過ぎゆく日」にも表れており、「融(とおる)は下宿屋から行李や蒲団や机やランプのやうなものを車に積んで、友人の建てた長屋風の家に入つて、初めて一箇の世帯主となつて間もなく妻と同棲することになつた当初に遡つて考へた。硬い蒲団や着物の汚ないのに驚いて、融が気味わるく思ふやうな綿のふかふかした蒲団を新調してくれたことや、裾の破けた着ものを釈いたり、汚れものを洗濯してくれた頃のことを思ひ出した」(ほほう、秋聲先生は好んでせんべい蒲団派…)。かつて「黴」の中で「十年もあんな蒲団に包(くる)まつてゐるなんて、痩せツぽちのくせによく辛抱が出来たもんですね。」と笑った妻はあっという間にこの世を去り、いま彼女の面影とともに秋聲の胸をよぎるものこそ、慣れないふかふかの蒲団の匂い…。 |
傍道(わきみち) |
| 2021.2.10 |
| 去る8日にお邪魔いたしました例月のMROラジオ「あさダッシュ!」さんにて、今話題の加能作次郎さんのお話をさせていただきました。先般、大学入学共通テストにその作「羽織と時計」が出題されたことで注目を浴びる自然主義作家です。現石川県羽咋郡志賀町のご出身で、苦学して早稲田から博文館を経て、大正7年、苦しかった丁稚時代に材をとる長篇小説「世の中へ」で一躍文名をあげますが、そのころすでに自然主義も退潮の気配あり、ひとり取り残された〝自然主義の末流〟を自称した作次郎。 明治18年生まれで秋聲より14歳下になりますので、少し乗り遅れた感はあったでしょうか。「小秋聲」とも呼ばれ、博文館発行「文章世界」の編集を通じ多くの作家たちに愛された一方、創作者としては不遇な境涯であったといえるかもしれません。  大正9年の田山花袋徳田秋聲生誕50年記念祝賀会の発起人のひとりであり、大正15年に結成された秋聲を囲む「二日会」の一員でもあり、会には昭和3年から少なくとも10回以上の出席が認められます。当館で今からちょうど10年前に開催をいたしました企画展「加能作次郎―もうひとりの秋聲」でもご紹介のとおり、「二日会」では主に〝お賑やか〟担当としてしばしば得意の宴会芸が披露されたとか。会津の盆踊り歌を独自にアレンジした「チロリ節」に合わせ、リズミカルにヒジでお餅をつく、その名も「肱餅搗き(ひじもちつき)」は当時の文士たちの間にも有名であったようで、「二日会」の記録冊子に「加能チロリ作次郎」とさえ記されています。そういえば秋聲も負けじと後日の「二日会」で得意のダンスを披露したことがありましたね。そのとき出席していた後輩作家・牧野信一に「気障(きざ)だ」と嘲笑されたことを随筆に記し、ムーーーとなったりもしています。なおこの随筆、「通人」(昭和8年)との題で、秋聲の思う〝気障〟について分析されるのですが、紅葉先生のお話が出たり、洋装について語られたり、趣味である社交ダンスに言及して前述の牧野氏への反駁が記されたりしたその最後の最後に「あ、ちがうちがう全部傍道。久米氏の話がしたいんだったわ」と、本題はわずか3行でまとめられる「気障気のないインテレ通人」こと久米正雄氏のお話なのでした。 大正9年の田山花袋徳田秋聲生誕50年記念祝賀会の発起人のひとりであり、大正15年に結成された秋聲を囲む「二日会」の一員でもあり、会には昭和3年から少なくとも10回以上の出席が認められます。当館で今からちょうど10年前に開催をいたしました企画展「加能作次郎―もうひとりの秋聲」でもご紹介のとおり、「二日会」では主に〝お賑やか〟担当としてしばしば得意の宴会芸が披露されたとか。会津の盆踊り歌を独自にアレンジした「チロリ節」に合わせ、リズミカルにヒジでお餅をつく、その名も「肱餅搗き(ひじもちつき)」は当時の文士たちの間にも有名であったようで、「二日会」の記録冊子に「加能チロリ作次郎」とさえ記されています。そういえば秋聲も負けじと後日の「二日会」で得意のダンスを披露したことがありましたね。そのとき出席していた後輩作家・牧野信一に「気障(きざ)だ」と嘲笑されたことを随筆に記し、ムーーーとなったりもしています。なおこの随筆、「通人」(昭和8年)との題で、秋聲の思う〝気障〟について分析されるのですが、紅葉先生のお話が出たり、洋装について語られたり、趣味である社交ダンスに言及して前述の牧野氏への反駁が記されたりしたその最後の最後に「あ、ちがうちがう全部傍道。久米氏の話がしたいんだったわ」と、本題はわずか3行でまとめられる「気障気のないインテレ通人」こと久米正雄氏のお話なのでした。 |
| 「お風呂の日」 |
| 2021.2.6 |
| 本日2月6日は「ふ(2)ろ(6)」の語呂合わせから「お風呂の日」だそうですね。お風呂といえば秋聲の名篇「風呂桶」! 当館オリジナル文庫の短編小説傑作集Ⅰに収録がございます。「改造」大正13年8月号に発表された短編小説で、文字通り徳田家の壊れた風呂桶を新調するお話です。実はこれと対になるのが「女性」昭和2年2月号に発表された短編小説「売り買ひ」。何を売って買うかといってまさに〝風呂桶〟なわけですが、はま夫人とともに風呂桶を新調したあの時からわずか2年半の間に徳田家に何が起こったのか…ご存じ、大正15年1月にはま夫人が脳溢血で急死したことにより徳田家は大混乱に陥ります。残された6人の子どもたちとともに途方に暮れる父秋聲…間もなくそこから心機一転を図るかのように秋聲は自宅の増改築を思い立ち、その一環としてお風呂もまたそれまで石炭で沸かしていたものから瓦斯(ガス)風呂に取り替えることになったもよう。もとは80円か85円で購入したというこの桶を、一体いくらで引き取ってもらえるか――35円なら? えっ25円? そんな駆け引きと、桶屋さんや瓦斯会社との慣れぬやりとりを描くのが後者の作品です。 あの頃、新調された風呂桶に入り、まるで○○のようだ…と感じたそれを売ってしまった秋聲に、子どもたちは「おとうさん、あの○○をとうとう売っちゃったんだね」と笑いながら囃し立てる…どちらも結末部分に触れますのでちょいと伏せ字にさせていただきました。とくに前者は犀星さんや広津和郎らが高く評価した作品ですのでぜひ原文をお読みいただけましたら幸いです。  なお、次回の「秋聲の家―徳田家所蔵品展」ではこの徳田家増改築計画の背景も少しご紹介する予定で、いつも常設展にお出ししている「風呂桶」原稿(レプリカ)のオリジナル(徳田家寄託品)も出品いたします。現在だいたいパネルのテキストを書き終え、残念ながら「売り買ひ」までご紹介する余裕がなかったものですからこちらにて補足、というかフライング、というか予告です。 なお、次回の「秋聲の家―徳田家所蔵品展」ではこの徳田家増改築計画の背景も少しご紹介する予定で、いつも常設展にお出ししている「風呂桶」原稿(レプリカ)のオリジナル(徳田家寄託品)も出品いたします。現在だいたいパネルのテキストを書き終え、残念ながら「売り買ひ」までご紹介する余裕がなかったものですからこちらにて補足、というかフライング、というか予告です。と、ここで書いてしまったらあさって8日(月)10時~のMROラジオ「あさダッシュ!」さんでお話しするネタがなくなってしまいました! えっ、あっ、2月8日は何の日か…! |
「加賀の三たろう」展 |
| 2021.2.4 |
 先日、石川近代文学館さんで開催中の「加賀の三たろう」展(~3月21日)を観覧させていただきました。「加賀の三たろう」すなわち西田幾多郎・鈴木貞太郎(大拙)・藤岡作太郎のお三方ですね! 三人揃って秋聲の一歳年上、明治3〈1870〉年のお生まれですので昨年2020年が生誕150年の年でした。それを記念した企画展で、毎度のことながらアーアー惜しげもなくまた全部だしましたねーーーー! と思わず溜息の出る展示資料の豪華さとともに、それらを収蔵する全国で2番目に歴史のある石川近代文学館という存在の大きさに改めて思いを馳せるのです。 先日、石川近代文学館さんで開催中の「加賀の三たろう」展(~3月21日)を観覧させていただきました。「加賀の三たろう」すなわち西田幾多郎・鈴木貞太郎(大拙)・藤岡作太郎のお三方ですね! 三人揃って秋聲の一歳年上、明治3〈1870〉年のお生まれですので昨年2020年が生誕150年の年でした。それを記念した企画展で、毎度のことながらアーアー惜しげもなくまた全部だしましたねーーーー! と思わず溜息の出る展示資料の豪華さとともに、それらを収蔵する全国で2番目に歴史のある石川近代文学館という存在の大きさに改めて思いを馳せるのです。秋聲と同郷、わずか1歳差、そして同じ第四高等中学校の出身ということで、展示中、幾多郎と作太郎がアメリカ出身のベントン先生送別会に出席したときの集合写真が秋聲的な見所でした。ベントン先生といえば秋聲が嫌っていた雰囲気のある英語教師。秋聲こと末雄青年(18歳)入学当時の四高の名簿には「第一外国語(※英語)」と「地理」の欄に「オー、エン、ベントン」の記載があり、一方そのお隣に同じ「第一外国語」と「羅甸(ラテン)語」担当として「ヂー、アル、マクケンジー」とあるこちらのマッケンジー先生のほうはどうやら好いていたらしく、回顧録『思ひ出るまゝ』に〈二学年もかゝつて厳密に文法を教へてくれたカナダ人のマツケンヂイといふ教師の熱心で真面目な教授振(ぶり)は今でもはつきり思ひ出せるが、米人のベントンといふ男は、少し生徒に軽蔑されてゐた〉と記しています。 展示写真の送別会は明治24年のこと。たしかに次年度の名簿にはすでにベントン先生の名の記載なし。あわせて秋聲が四高の同級生の思い出を綴った短編小説「郊外の聖」(大正11年)に「小山や佐々村たちのやうな旋毛(つむじ)の曲つた連中が、学校で幅を利かしすぎてゐた或(ある)外人教師を排斥したとき…」との記述があり、えっまさか…と思いながら主人公格の「佐々村」…ささむら…笹村…『黴』!! …こらァ末雄青年らの仕業であったかもしれません。三たろうはじめ四高の生徒たちは基本的に優秀なので、尊敬できない教師が赴任するとはけっこうやんちゃしたそうです。 |
徳田家所蔵品展 |
| 2021.2.3 |
内臓がわるいといえば秋聲、秋聲といえば基本病弱! 心臓も気管支も肺も胃も、あまつさえ頭脳(あたま)もわるいとは秋聲の口癖です(そして膝に古傷あり)。わりと病院好き、お薬好きで知られる秋聲さんの書斎のお机にはさまざまな種類の薬が常備され、その抽斗もお薬でいっぱいであったとか(それは某K花さんに「薬くさい」と言われてしまうというもの…)。この休館が明けたところの3月20日からの生誕150年記念企画展「秋聲の家―徳田家所蔵品展」では、徳田家に残る秋聲が服用していた件の漢方薬の箱を展示予定のほか、これまでちょこちょこと小出しにしてまいりました作家のお手回り品の数々を一挙公開いたします! 基本的にどうしたって紙資料の多い文学館の展示ですが、今回はいつになく立体物が多くなる予定です。ふだんケースからせいぜい5cmくらいの高さの視界で生きておりますもので不馴れも不馴れ、改めて秋聲先生遺品の二重回しの丈をはかりながら、アレッうちのケースに入る? 丈たりる…? 裾がぶつかる…!? とマネキンのサイズを調整したりしています。…そう、一昨年の夏、東京は弥生美術館さんで初公開され、ギエエ先をこされたァ~~~! と当館が大いに奥歯をギリギリ言わせました徳田家所蔵のあのコートと鞄、そしてステッキがこのたび金沢へと帰ってまいりました! おそらく東京で購入されたものですので、「帰る」という表現はあたらないかもしれません。が、それを着用のうえ帰省されたこともあったかもしれません。弥生美術館さんの素敵企画展「アンティーク着物万華鏡―大正~昭和の乙女に学ぶ着こなし―」(図録代わりの当該書籍にコート等のお写真載ってます!)をつい見逃されたみなさま、この春、当館でお会いいたしましょう。その当時、弥生美術館さんと徳田名誉館長(秋聲令孫)にさんざん気を遣わせ、あっじゃあ帽子は? ね、ホラ、お帽子もってく!? と名誉館長がご提供くださったフェルトの帽子は本邦初公開になろうかと存じます。 おそらく東京で購入されたものですので、「帰る」という表現はあたらないかもしれません。が、それを着用のうえ帰省されたこともあったかもしれません。弥生美術館さんの素敵企画展「アンティーク着物万華鏡―大正~昭和の乙女に学ぶ着こなし―」(図録代わりの当該書籍にコート等のお写真載ってます!)をつい見逃されたみなさま、この春、当館でお会いいたしましょう。その当時、弥生美術館さんと徳田名誉館長(秋聲令孫)にさんざん気を遣わせ、あっじゃあ帽子は? ね、ホラ、お帽子もってく!? と名誉館長がご提供くださったフェルトの帽子は本邦初公開になろうかと存じます。7月末までの展示につき、見ためにも会期の途中で衣替えが必要でしょうか…なお、あわせて展示予定の件のダンスシューズは真っ白ですので夏でもさわやか! |
ホームページ復活のお知らせ |
| 2021.1.31 |
| 約一ヶ月間メンテナンスのため更新停止しておりました当HPがこのたび元気になって戻ってまいりました! パッと見た目には変わらないのですが、しっちゃかめっちゃか無理をさせ続けてきた内臓がすっかりきれいに…。心なしか顔色も良く見えてまいります。見えないところ大事大事。 館は変わらず休館中ですが(見えないところの空調設備工事です)、ぼちぼちとリハビリを兼ね寸々語の更新もがんばってゆく所存です。改めまして今年もよろしくお願い申し上げます。 そして復活と同時に新たに誕生いたしました当館Facebook! いつも親切にしてくださる関係施設の方からありがたいことにFacebookのススメを受け、今更ながらに始めてみることといたしました。基本的にはこちらの寸々語のコピペで運営してゆきますので目新しいことといって特にないのですが、何せ秋聲生誕150年の今年ですからTwitter、Facebookとさまざまな角度から秋聲情報にアプローチしやすい環境を整えてゆきたい、そんな心持ちでございます(ただしインスタグラムは今後もおそらく開設いたしません。だってご存じビジュアルに弱い当館だから…!)。Twitter、Facebookともにトップページにボタンを新設していただきましたのでよろしければご覧ください。  さらに遅ればせながら「早稲田文学」2020年冬号におきまして、山岸郁子先生のご高論「文学館、文豪、そしてほんとうの『資源』とは」中、この寸々語のことをご紹介いただきました! ウワァ! 山岸先生ありがとうございます! 発行された途端に寸々語休業とはなんとも間の悪いこと…! 一月空いてようやくご紹介つかまつります。こちらでは三文豪館ほか全国の文学館とゲーム「文豪とアルケミスト」さんなどのコンテンツとのかかわり方、またコロナ禍における文学館の取り組みなどについて論じてくださっております。ぜひ秋聲のしゅの字、見つけてやってくださいませ! さらに遅ればせながら「早稲田文学」2020年冬号におきまして、山岸郁子先生のご高論「文学館、文豪、そしてほんとうの『資源』とは」中、この寸々語のことをご紹介いただきました! ウワァ! 山岸先生ありがとうございます! 発行された途端に寸々語休業とはなんとも間の悪いこと…! 一月空いてようやくご紹介つかまつります。こちらでは三文豪館ほか全国の文学館とゲーム「文豪とアルケミスト」さんなどのコンテンツとのかかわり方、またコロナ禍における文学館の取り組みなどについて論じてくださっております。ぜひ秋聲のしゅの字、見つけてやってくださいませ! |
ホームページ更新停止のお知らせ |
| 2021.1.8 |
 空調工事休館中でも寸々語の更新はできる限り!! と申し上げておりましたが、この期間を利用して当HPのメンテナンスも一緒にやってしまうことになりました。もののわからぬアナログ脳たちがあっちゃこっちゃといじり回し、ページを破壊しては素知らぬ顔をしてひとまず寝かせ、翌朝また根拠のないやれる気持ちで叩き起こしては適当に撫でつけ、なにをどうしたかはわからないけどもなんか直ったっぽい、みたようなことをさんざ繰り返した結果つぎはぎだらけになってしまった(もう手の施しようがない→)このHPを新年度を前にいったん綺麗にしようという試みです(館同様、リニューアルではございません)。 空調工事休館中でも寸々語の更新はできる限り!! と申し上げておりましたが、この期間を利用して当HPのメンテナンスも一緒にやってしまうことになりました。もののわからぬアナログ脳たちがあっちゃこっちゃといじり回し、ページを破壊しては素知らぬ顔をしてひとまず寝かせ、翌朝また根拠のないやれる気持ちで叩き起こしては適当に撫でつけ、なにをどうしたかはわからないけどもなんか直ったっぽい、みたようなことをさんざ繰り返した結果つぎはぎだらけになってしまった(もう手の施しようがない→)このHPを新年度を前にいったん綺麗にしようという試みです(館同様、リニューアルではございません)。そんなわけで、明日より今月末くらいまで寸々語をはじめとするすべてのページの更新がストップいたしますので、あらかじめご案内を申し上げます。その間のご連絡事項は主にツイッターにておこなうほか、あまりにも緊急! という事態が何かしら生じた場合には臨時に浮上することもあろうかと存じます。またオリジナルグッズの通販ページにつきましては期間中も通常通りご利用いただけますのでご遠慮なくメールくださいませ。秋聲生誕150年に突入した途端にどこもかしこも急に動きの鈍くなる記念館で恐縮です。 決して前年のうちにはしゃぎすぎてエネルギー切れ、などというわけでなく、水面下では日々忙しく走り回っております(が、見た目にはデスクから一歩も動かざること山の如き学芸員、一方その処理速度の疾きこと風の如き通販担当職員。吹雪のなかを封筒を山盛り抱えて郵便局へと向かうその背を今日もあたたかく見送りました)。 それではみなさましばらくの間こちらからはさようなら! 来月またお会いいたしましょう! |
白木蓮の咲くころ |
| 2021.1.7 |
| 4日に発売となりました新刊『秋聲の家―徳田一穂作品集』、HPとツイッターにご案内を掲載してからタタタタッとご注文をいただきまして、現在じゃんじゃん発送をさせていただいております! ありがとうございます!(図書館さん等への献本の手配にはもうしばらくお時間いただきます、申し訳ありません…!) 編者の大木志門先生も折々にご紹介くださっているとおり、今回の一穂集の表紙には一穂自身が描いた白木蓮の絵を使わせていただきました。一穂さんのご次女である徳田名誉館長からご提供いただいたもので、表からは見えませんが表紙カバーの本体折り込み部分に一穂の署名が入っています。  秋聲作品において、秋聲がその〝家〟について描写するときには必ず出てくるお庭の植栽のこと。白木蓮、柘榴、山吹、コブシなどなどに触れ、自らシャベルをもって(←)執筆の合間にせっせと手入れをする様子もしばしば描き込まれています。その庭の植栽が、秋聲没後、家を取り巻く周囲の環境の変化によりどんどんと枯れ落ちてゆくのをずっと見ていた一穂さん。何度となく、こんな家、取り壊してしまえ! と思われたことすらあったようですが、秋聲を愛する人々の支えもあり、どうにかこの〝家〟を残すというお気持ちを繋いできてくださったようです。そしてその思いが徳田名誉館長にも引き継がれ、今なお徳田家は文京区本郷に現存し、かつ単なる観光名所でなく〝家〟としての機能を果たし続けているのです。 秋聲作品において、秋聲がその〝家〟について描写するときには必ず出てくるお庭の植栽のこと。白木蓮、柘榴、山吹、コブシなどなどに触れ、自らシャベルをもって(←)執筆の合間にせっせと手入れをする様子もしばしば描き込まれています。その庭の植栽が、秋聲没後、家を取り巻く周囲の環境の変化によりどんどんと枯れ落ちてゆくのをずっと見ていた一穂さん。何度となく、こんな家、取り壊してしまえ! と思われたことすらあったようですが、秋聲を愛する人々の支えもあり、どうにかこの〝家〟を残すというお気持ちを繋いできてくださったようです。そしてその思いが徳田名誉館長にも引き継がれ、今なお徳田家は文京区本郷に現存し、かつ単なる観光名所でなく〝家〟としての機能を果たし続けているのです。その〝家〟が守る秋聲の遺品等を一挙公開! と企図したのが前回の「思ひ出るまゝ」展同様、文庫本とリンクさせた形の次回「秋聲の家」展(仮)だったのですが、正直なところ首都圏の緊急事態宣言発令かといったこの状況下で公開のタイミングをつかみきれず…企画展ページに予告を出してしまったあとで恐縮ながら、もしかすると館の収蔵資料展に切り替えるかもしれません。とはいえ初公開でこそなくとも、当館の収蔵品の三分の一は徳田家からの寄贈・寄託品。一穂さんの思いや葛藤なくしては残らなかった貴重な品々に違いありません。 |
| 謹賀新年 |
| 2021.1.4 |
あけましておめでとうございます。いよいよ秋聲生誕150年の記念イヤーに突入いたしました! そんな勢いでヌォッッと年を越しておきながら、館はひきつづき休館中でございます……ウウウもてあます! このエネルギィー…ッ!!! そんな要エネルギーな展示撤去は年末のうちにやってしまったものですから、いまは設備工事の傍らガランと薄ら寒い館内で、新発売のオリジナル文庫第12弾『秋聲の家―徳田一穂作品集』を両手に持ってウロウロとしております。 おかげさまで開館15周年記念に3冊出す! と無謀な宣言をしてしまったうちの2冊目がようやく完成いたしまして、今ほど通信販売用ページに概要をアップいたしました! 改めましてご紹介を申し上げます。今回は秋聲の作品でなく、秋聲ご長男で作家の徳田一穂による小説・随筆・秋聲著作の跋文から計20編を収録した作品集で、秋聲でない人物の著作はオリジナル文庫初のこと。またこちらも初めて館外より編者に当館初代学芸員・大木志門先生(現東海大学教授)をお招きし、作品の選定から校正から解説からなんと一穂さんの著作目録まで手がけていただいたという超豪華版です(その節はことごとくこちらの手配が遅くご迷惑をおかけいたしました…!)。いつかの一穂展でもご紹介のとおり、秋聲まわりでは絶対にお見かけする一穂さんのお名前ながら、一穂さんご自身の作品、また秋聲に関するお仕事の全貌となると一言でご紹介するのがなかなか難しかったところ、今後この一冊があればそのおおよその輪郭がつかめてくるのではないでしょうか。ご推薦いただいた中から作品数を欲張り(全350頁)、口絵まで入れたら(一穂さん肖像写真)ちょいとお高め(税込1,000円)にはなってしまいましたけれども、この機にぜひご注文(通販にて)をいただけましたら幸いです。 おかげさまで開館15周年記念に3冊出す! と無謀な宣言をしてしまったうちの2冊目がようやく完成いたしまして、今ほど通信販売用ページに概要をアップいたしました! 改めましてご紹介を申し上げます。今回は秋聲の作品でなく、秋聲ご長男で作家の徳田一穂による小説・随筆・秋聲著作の跋文から計20編を収録した作品集で、秋聲でない人物の著作はオリジナル文庫初のこと。またこちらも初めて館外より編者に当館初代学芸員・大木志門先生(現東海大学教授)をお招きし、作品の選定から校正から解説からなんと一穂さんの著作目録まで手がけていただいたという超豪華版です(その節はことごとくこちらの手配が遅くご迷惑をおかけいたしました…!)。いつかの一穂展でもご紹介のとおり、秋聲まわりでは絶対にお見かけする一穂さんのお名前ながら、一穂さんご自身の作品、また秋聲に関するお仕事の全貌となると一言でご紹介するのがなかなか難しかったところ、今後この一冊があればそのおおよその輪郭がつかめてくるのではないでしょうか。ご推薦いただいた中から作品数を欲張り(全350頁)、口絵まで入れたら(一穂さん肖像写真)ちょいとお高め(税込1,000円)にはなってしまいましたけれども、この機にぜひご注文(通販にて)をいただけましたら幸いです。 生誕150年没後77年を経てなお秋聲の名が今に在るのは、いわゆる〝二世〟であった一穂さんの苦悩と父秋聲に対する深い愛情の賜物なのです。 |
